目次
研究計画書、完璧を求めすぎていませんか?
大学院進学を目指す社会人にとって、「研究計画書」は避けて通れない提出物です。
それはほとんどの大学院で出願時に研究計画書の提出が求められているからです。

ですが、この研究計画書を作成するにあたり、「完璧に仕上がるまでは提出できない」と感じてしまう方も少なくありません。
確かに、研究計画書は自分の研究の方向性を示す重要な書類であるためきちっと作り上げる必要がありますが、実はそれほど気負わなくても大丈夫なのです。
なぜなら、研究計画書は大学院入学後に改めて作り直すことが多いからです。
今回は「研究計画書は完璧でなくてもOK」をテーマにお届けします!!
研究計画書の役割とは?
大学院受験の出願時、研究計画書の提出が求められます。
これは一体何のためでしょうか?
それは「この人は大学院で研究する意欲があるのか」「どんなテーマに興味を持っているのか」を確認するためです。
出願段階では、研究の完成形を求められているわけではありません。
むしろ、「今の段階でどのように考えているか」を示すことが重要なのです。
そのため、完璧なもの・そのまま修士課程の研究に直結するもの(=修士論文に使えるもの)を提出しなくても問題ないのです。
大学院では出願時の研究計画において次のポイントをチェックしています。
・一人で研究できそうか
・研究のルールを理解しているか
・やる気があるか
ちなみに、大学院受験では、「放っておいてもちゃんと2年で研究して修了できそうな人」「手がかからなそうな人」を合格させたいのが本音です。
そのため、面接で「ゼロから学びたいです」という発言は避けたほうがいいです。
研究計画書の中で「先行研究」を記載するのも、「どのレベルまで研究を理解しているか」を試験官に伝えるという意味があります。
☆研究計画書の書き方はこちらもご覧ください↓
完璧を求めすぎるデメリット
ここまで、「研究計画書は完璧でなくてもいい」という内容をお伝えしてきました。
研究計画書の完成度にこだわりすぎると、以下のようなデメリットが生じることがあります。
(1)提出が遅れる
完璧を目指すあまり、締め切りギリギリまで手を加えてしまい、最悪の場合提出自体が間に合わなくなることもあります・・・。
(2)内容が固まりすぎる
入学後に研究の方向性を変えたくなっても、すでに固めすぎた計画書があると、自分で自分を縛ってしまう可能性があります。
(3)精神的な負担が増す
研究計画書の作成に時間をかけすぎると、他の試験対策や面接準備に充てる時間が減り、結果的に全体の準備が不十分になってしまうかもしれません。
大切なのは「考えるプロセス」
研究計画書を作成する過程で大切なのは、「どのようにして自分の興味を掘り下げるか」というプロセスです。
テーマに関して自分なりに調べ、どのような課題があるのか、どのようにアプローチしたいのかを言葉にしてみましょう。
たとえ未完成でも、その過程で自分の思考が整理され、面接などでも自信を持って話せるようになります。
研究計画書作成のアドバイス!
ここでは研究計画書作成の上でのアドバイスを3点にわけてお伝えします!
(1)大枠を決める
自分が興味を持っている分野やテーマをまずはざっくりと決めます。
細かい部分は後から詰めればOKです。
(2)簡単な目次を作る
研究計画書には「背景」「目的」「方法」「予想される結果」「意義」など、基本的な構成があります。
これらの項目を簡単に埋めていくことで、計画書の全体像が見えてきます。
(3)面接対策も兼ねた取り組みを!
試験本番の面接では研究計画書を基に質問されます。
そのため計画書を通して自分の考えを整理し、言語化できるようにしておくと面接対策にもなります。
なお、研究計画書作成でつまづいてしまった際は誰かに読んでもらってアドバイスを受けるのも有効です!
そういう機会としてうちの塾の体験授業もご活用くださいね!
入学後に研究計画をブラッシュアップ
大学院に入学してからは、指導教官やゼミの仲間と意見交換をしながら、研究計画をより具体的で実現可能なものに仕上げていきます。
最初に出した研究計画書が最終形ではなく、あくまで「出発点」として捉えましょう。
実際、多くの大学院生が入学後に研究テーマを変更することも珍しくありません。
そのため、「とりあえずの形」で提出しても問題はないのです。

1年制修士の場合は「そのまま使う」イメージを!
ただし、1点だけ注意事項があります。
ここまでの話は修士課程を2年で卒業する通常のケースの話だということです。
通常2年の内容を1年に凝縮する「1年制修士」で修了を目指すケースがあります。
この場合、研究計画書を試行錯誤しているとあっという間に時間切れになります。

なので「1年制修士」の場合、当初の研究計画書をそのまま実行することも多いのです。
…とはいうものの、実際は1年制修士の場合も研究計画書をイチから書き直すケースもあります。
1年制修士の場合は時間も短いので完成度の高い研究計画書が求められると考えておくといいですね!
まとめ!気負わずに研究計画書をまず完成させよう!
研究計画書は完璧である必要はありません。
重要なのは、自分の興味や関心を素直に表現し、大学院での学びに対する意欲を示すことです。
入学後にブラッシュアップすることも前提においた上で、まずは提出することを優先しましょう!
…こういうことをお伝えするのは、「完璧でないと大学院に出願できない」と思うあまり何年も受験を先延ばしにする人が時折いらっしゃるからです。
まずは「完ぺきでなくてもOK!」という気持ちで、ぜひ研究計画書作成に取り組んでみてください!
ひとりで作りにくいときはぜひうちの塾の体験授業もご活用くださいね!

☆研究計画書についてはこちらもご覧ください。
「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!







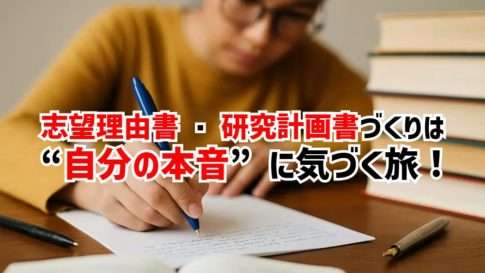

























大学院受験出願を阻む研究計画書。
これ、実は完璧なものでなくてもOKです。
入学後に修正する前提で、まずは提出を優先しましょう!
完璧を求めすぎると提出が遅れたり、方向転換が難しくなることもありますので…。