(インタビュー実施日:2024年11月23日@Zoom)

香川大学工学部・横浜国立大学大学院博士課程前期(修士課程)を経て大手メーカー企業に勤務。
製品のリスク管理担当になったことを機に長岡技術科学大学専門職大学院に進学。修了後はそのまま長岡技術科学大学大学院の博士後期課程に進学し博士号を取得。
現在はメーカー勤務の傍ら大学非常勤講師・在野の研究者としても活躍。
目次
『なぜ社会人大学院生で学ぶのかⅠ』
――今日は『なぜ社会人大学院で学ぶのか1』の執筆も手掛けられた岡部さんにお話を伺います。
お忙しい中ありがとうございます。
岡部:こちらこそ、お声掛けいただきありがとうございます。こういった形で私の経験を振り返る機会をいただけるのは非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。
岡部知行さんは『なぜ社会人大学院生で学ぶのかⅠ』に著者として参加さなっています。
私・藤本も本書執筆に関わっていますのでその御縁でインタビューをご依頼いたしました。

働きながらも学び続ける!その原点はどこ?
――岡部さんは現在メーカーでリスクマネジメントや製品安全管理の業務を担当されていると伺いました。
そのキャリアの中で2016年には長岡技術科学大学専門職大学院で専門職学位を取得され、さらに博士後期課程を修了し博士号も取得なさっています。
学び続ける意欲の原点について教えていただけますか?
岡部:私の学びの原点は、高校時代の経験にあります。
地元の工業高校に進学したのは、手に職をつけるためでした。
当時は「学ぶ」ということを楽しむというよりも、技術を身につけるための手段としてとらえていました。
ですが工業高校在学中に中間試験でクラス1位を取ったことが、私の人生を大きく変えるきっかけとなりました。
この成功体験を通じて、「努力は結果を生む」ことを実感したのです。
それ以来、学ぶことが楽しくなり、知らないことを知る喜びを感じるようになりました。
工業高校→短大→四大編入→一回目の大学院進学!
――その成功体験が学びのモチベーションに繋がっているのですね。その後、工業高校での学びをさらに深めたいと考え、大学進学を目指されたそうですが、その具体的な経緯を教えていただけますか?
岡部:高校では主に電気工学を学びましたが、学ぶほどにその分野の奥深さに惹かれました。
高校時代に学んだ知識をさらに発展させるため、地元の工業大学への進学を目指しました。
ですが、工業高校のカリキュラムでは一般大学受験に必要な教養科目に十分対応できず、第一志望には進学できませんでした。
その際、進路指導の先生から勧められたのが、地元の理工系短期大学でした。
指定校推薦を受け、そこに進学することを決めました。

――短期大学ではどのような学びを得られたのでしょうか?
岡部:短期大学では電気工学からさらに範囲を広げ、電子情報工学を2年間で学びました。
この分野では、コンピュータや情報通信といった電気以外の領域も含まれており、幅広い知識を身につけることができました。
特に、講義で参考文献を深掘りするうちに、自分の学びをもっと専門的なものにしたいと思うようになり、「3年次編入制度」を利用して4年制大学でさらに学ぶことを決意しました。
――その制度を利用して香川大学工学部に進学されたのですね。香川大学ではどのような研究に取り組まれましたか?
岡部:香川大学工学部では材料創造工学科に所属しました。
材料そのものの特性を研究する中で、特に半導体材料や光と物質の相互作用(光物性物理学)に興味を持つようになりました。
卒業研究では、半導体を含む材料の応用について深く掘り下げ、研究成果を具体的なプロジェクトに落とし込むことができました。
この経験を通じて、自分の知識をさらに深めるために大学院での研究が必要だと感じ、(以前から地元の国立大学として憧れのあった)横浜国立大学大学院工学府物理情報工学専攻物理工学コースへの進学を決意しました。
――大学院ではさらに専門的な研究を進められたのですね。横浜国立大学大学院での学びはどのようなものでしたか?
岡部:横浜国立大学大学院では、物理工学に関心が移り、半導体材料の光物性に関する研究(実験系)に取り組みました。
特に、半導体材料の微細構造が機能に与える影響についての研究は、自分にとって非常に興味深いテーマでした。
この大学院では、ただ知識を得るだけでなく、それをいかに現場で活かすか、実際に社会に貢献できる形にするかを意識した学びが多かったです。
仕事をしながら2回目の大学院修士課程進学!
――その後、岡部さんはメーカーに就職されていますね。
その後、仕事をしながら社会人として大学院に再度進学されていますね。
もう一度進学を決意なさった理由を教えてください。
岡部:一度就職してからも、学びを続けたいという思いが強くありました。
社会人大学院を選んだ理由は、仕事と学びを並行させることで、学びを実務に直接結びつけられる点に魅力を感じたからです。
私は技術経営、いわゆるMOT(Management of Technology)と製品安全を同時に学べる環境を探し、長岡技術科学大学専門職大学院技術経営研究科システム安全専攻を選びました。
――社会人大学院での生活はどのようなものでしたか?
岡部:平日は関東で本業に集中し、金曜日の夜には長岡に移動、週末の講義を受講するという生活でした。
土曜日の夜には同級生と懇親会を開くこともありましたが、そこでも学びに関する議論が尽きることはありませんでした。
当時の同級生は全国各地から集まっており、異なるバックグラウンドを持つ方々との交流は自分の視野を広げる良い機会となりました。
また、東京にもサテライトキャンパスがあり、そちらでも授業を受けることもできたため、学びの環境が非常に充実していました。

「時間管理が一番の課題でした」
――仕事との両立は大変だったと思いますが、特に苦労された点や工夫した点を教えてください。
岡部:やはり時間管理が一番の課題でした。
研究テーマを実務に結びつけることで効率化を図り、週末の学びが平日の業務にも活かせるよう工夫しました。
その上で、職場の理解を得ることも重要でした。
職場では「週末の一部を休暇にあてるかもしれない」と事前に相談し、早めに上がらせてもらうなどの配慮を受けました。

学びが業務にも役立っているのを実感!
――その経験が現在の業務にどのように役立っていますか?
岡部:社会人大学院で学んだシステム安全のフレームワーク(特にリスクアセスメント)や製品安全に関する法規制・規格の解釈の仕方が実務に直接役立ちました。
また、専門職大学院では論文の代わりにプロジェクト研究がありましたが、そこで培った知識を当時所属していた事業部門の品質マニュアルに組み込みました。
現在でも活用されていると思います。
――学んだ内容を活かされていますね!!!

大学院は自分自身の成長への投資になる!
最後に、これから社会人大学院を目指す方々に向けてメッセージをお願いします。
岡部:社会人大学院は、自分のキャリアを見直し、学び直す絶好の機会です。
ただし、進学には目的意識が必要です。
「なぜ学びたいのか」をしっかり掘り下げ、目標を明確にしてください。
また、家族や職場の理解を得ることも不可欠です。
実際の進学においては説明会に参加し、大学院の雰囲気を肌で感じることもお勧めします。
社会人大学院での学びは、単なる知識の習得ではなく、自分自身を成長させる投資となります。
ぜひ挑戦してみてください。
――ありがとうございます。
岡部さんの経験から、学び続ける意義を強く感じました。
本日は貴重なお話をありがとうございます!
岡部:こちらこそ、ありがとうございます。
インタビューを終えて
岡部さんとはインタビューの一年前、『なぜ社会人大学院で学ぶのかⅠ』執筆の打ち合わせではじめてお話を伺いました。
アクティブに動き回っていらっしゃる様子をその際に伺い、「一度詳しくお話を聞いてみたい」と思っていたのを思い出します。
その念願が今回のインタビューで実現できたこと、嬉しく思っています。
インタビュー前に御本人から伺ったのですが、岡部さんは「ほとんどすべての学校種を経験している稀有なキャリア」の持ち主です。
高校を出た後に短大→四大編入→修士課程進学、就職後は専門職学位課程→博士後期課程を終えられています。
これだけ多様な学びを経験なさっていることからも、人生における勉強の価値を誰よりも実感なさっていることが伝わってきます。
今後のご活躍も祈らせていただきます!!!
☆これまでのインタビュー記事はこちら↓




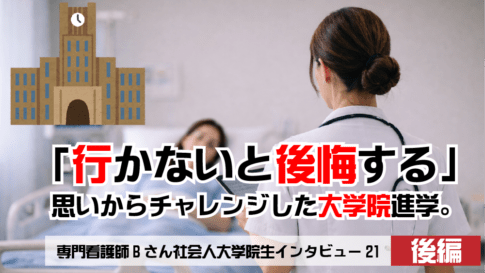
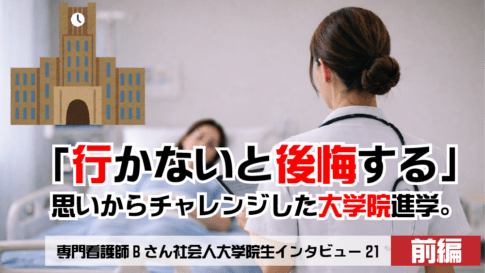


















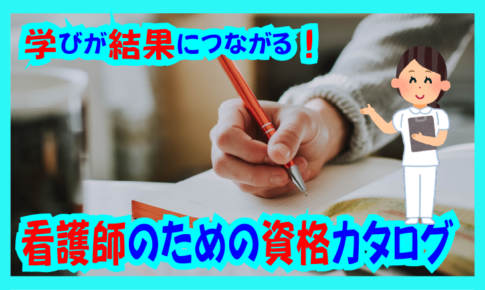






社会人として大学院で学んだ経験を持つ方々へのインタビューシリーズ。今回紹介する岡部知行さんはメーカー勤務の傍ら一念発起して専門職大学院への進学を決意。修了後はそのまま博士後期課程に進学し博士号を取得なさいました。
学んだことを職場でも活かされている様子を詳しく伺いました!