目次
働きながら大学院に通うと可能性が一気に高まる!リスキリングとリカレントで夢を叶える!
働きながら大学院に通う。
それによって転職のチャンスが広がったりキャリアチェンジが可能になったりします。
自分の今後の人生の可能性が大きく開けるのです。
現在はリスキリングやリカレント教育が注目されるため、大学院進学に興味を持つ社会人の数も増えてきています。
もちろん、働きながら学ぶのは多くの社会人にとって時間とお金・体力の点で困難なところもあるかも知れません。
ですが、それを上回る大きなメリットもあります。
今回は実際の社会人大学院生のインタビューを交えながら、働きながら大学院に通う際のポイントをさらに具体的に見ていきましょう。

1. 長期履修制度で時間を有効に使う戦略
長期履修制度は、大学院のカリキュラムを3〜4年に延長できる制度です。
つまり、通常2年間の修士課程の学習を3〜4年に引き伸ばせる制度となっています。
これにより、仕事をしながらでも大学院に通いやすくなります。
例えば2年間で修士課程を終える場合、週に7~8コマ、あるいはそれ以上の授業コマ数を履修する必要があります。
大学・大学院の授業は通常1コマ90分で実施されています。
平日の昼間に7~8コマ、時間にして10時間30分(7コマ)〜12時間(8コマ)もの時間を捻出するのは困難が予想されます。
ですが、長期履修で4年間履修する場合、この負担が半分ですみます。
週に3~4コマの通学で済むとすれば、週に4時間30分〜6時間の時間を捻出するだけで済むからです。
北海道大学公共政策大学院で学ぶ私のケース
私は現在、1対1大学院合格塾を運営し、㈱藤本高等教育研究所の経営もしながら北海道大学の公共政策大学院(通称HOPS)に通学しています。
2023年4月入学で現在修士課程2年生となっています。
仕事しながらでも通学できるのは長期履修制度を用い、4年間で履修する計画を立てている事が大きいです。
2024年度の前期の授業では、月曜日に2コマ(14:45~18:00)、木曜日に1コマ(18:15~19:45)、土曜の授業1コマ(変則的時間帯でした)の合計4コマ8単位を履修できました。。
北大公共政策大学院の卒業要件には42単位以上の履修が条件となっています。
なので、このペースでも卒業要件はラクに満たせる計算となります。
実際、2023年の前期後期と合わせ1年半で累計25単位履修しています。
長期履修制度を活用すれば1週間の授業負担が少なくて済むのでの制度を活用することで、仕事と学業の両立がしやすくなります。
忙しい社会人でも通学しやすくなるのです。

番外編 履修単位を極限まで増やすことも可能!
なお、卒業要件というのは「最低でも42単位の履修が必要」という基準ですのでそれ以上履修しても問題ございません。
公共政策大学院ご出身で私が先日インタビューした方は2年間で72単位を履修したと言っていました。
まさに、「猛者」です。
社会人でこれだけ履修しているのって本当にすごいことだと感じています
(公共政策大学院の授業だけでなく、北大の他の大学院の授業科目も履修しています)。
公共政策大学院の他の友人にも、やはり70単位を超える単位を履修された人がいます。
この方は4年間の長期履修でそれだけの授業数を履修しています。
長期履修といっても1年間に履修する授業数も半分に制限されるわけではないのでこういう履修の仕方も可能となります。
授業を受けることだけで見ると、学費のモトを取っていると言えるのではないでしょうか?
2. 仕事と学業の調整方法〜インタビュー事例から学ぶ〜
仕事のスケジュールを調整することが、働きながら大学院に通うための最初のステップです。
その際、可能であれば会社に対し勤務方法の変更を相談してみるのも働きながら大学院に通う上で有効です。
本ブログでインタビューをした小樽商科大学大学院のアントレプレナーシップ専攻(通称OBS)でMBAを取得した山田さんは、大学院進学を機に会社に勤務形態を変えてもらった、といいます。
ちなみにOBSに入って社会人大学院生としての生活をスタートするにあたり時短勤務で週3回しか会社に行かない形にしてもらったんです。
なおかつ会社の定時は6時半なんですけど、4時半には終わるような感じにしてもらいました。
こういう工夫をしていたからこそ少し余裕を持って通学ができるようになったわけですね。
経営者であれば時間調整がしやすい!
あなたが会社の経営者である場合、通学時間を捻出するのは一般社員よりは容易であるかも知れません。

当然、事前にスタッフを育成したり分業体制を整えたりする必要はありますが、経営者であれば平日昼間にも大学院に通学するのは比較的やりやすいと言えるでしょう。
私がインタビューをした湊さんは会社の権限委譲を進めていき、社長が現場に出なくても済む体制を整えていきました。
それがあるからこそ、大学院で地域創生についてを研究する時間的余裕を作り出すことに成功しています。
大学院で培った専門知識や人脈を業務にも活かせていらっしゃるそうです。
経営者つながりでいいますと、私もいちおう社長なので、時間の余裕を作りやすいという特徴があります。
経営者でなくても、たとえばフレックスタイム制のほか自由裁量制のある職場などでしたら日中に大学院に通うことも比較的容易でしょう。
いまそういう職場でない場合はいちどキャリアアップのために学習しやすい制度が整っている場所に異動・転職してから挑戦してみるのも1つの戦略としてオススメです。
給料をもらいつつ大学院進学!職場派遣で大学院に行けるケースも!
職場によっては職場から派遣される形で大学院に進学することが可能なケースがあります。
本ブログでインタビューした阿部さんも、職場である北海道庁からの派遣制度を活かし大学院に進学なさっています。
北海道庁では毎年1名限定ですが、給料をもらいつつ公費で北大公共政策大学院に通えるという派遣制度が整っています。
当然、北海道庁内部での審査はありますが、こういった背医度に勇んで申し込んでみるのもオススメです。
北海道庁以外にも、行政・民間企業のなかでこういった大学院への派遣制度を持つ組織はたくさんあります。
大学院を目指す際、職場にこういった制度がないか調べてみるのをオススメします!
3. 学費負担を軽減するための工夫。教育訓練給付制度や奨学金制度の活用を!
大学院の学費は大きな負担となります。
ですが、教育訓練給付制度や日本学生支援機構の奨学金制度を利用することで費用を軽減することが可能です。
教育訓練給付制度の活用を!
大学院の中には、教育訓練給付制度に対応した場所があります。
この制度を使う場合、学費の2割または5割が履修後に還付されます。
さらに、条件を満たす場合は最大7割もの学費が還付されます。
(教育訓練給付制度には一般教育訓練給付と専門教育訓練給付の2種類があります。
一般教育訓練給付は最大2割が還付されます。
専門教育訓練給付は5割が還付されるだけでなく、修了後どこかに雇用されていた場合は最大7割が還付されるという制度となっています)
教育訓練給付制度の詳細はこちらをご覧ください。
1対1大学院合格塾から多数の合格者を輩出している小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻も、専門教育訓練給付制度の対象となっています。
日本学生支援機構奨学金制度の活用を!
通学資金を用意する上では日本学生支援機構の奨学金制度制度も外すことができません。
日本学生支援機構の奨学金制度は社会人の大学院進学にも活用可能です。
一種での採用時は利子が免除、二種での採用時にも比較的低い利子率で奨学金を借りて進学する事が可能です。
実際、この制度を私もフルに活用しています。
教育ローンなどよりも低い利子率で奨学金を借りて通学できるのはありがたいメリットだと実感しています。
当然、一定期間後は返済義務が発生しますが、返済が必要なときに仮に家計が逼迫している場合は返済猶予を申請することも可能です。
そのあたりが一般の銀行系のローンと違いありがたいところであると感じています。
4. オンライン授業の活用。時間と場所に縛られない学びの活用
コロナ禍のなかではオンライン授業を提供する大学院が増えました。
いまはオンラインから通学に戻っている所も多いのですが、オンラインであれば通学の手間が省けるだけでなく、全国どこにいても学ぶことができます。
社会人に人気のあるMBA(経営管理修士)コースにもオンライン授業を多用する場所やオンラインだけで修了できる大学院があります。
オンライン実施が多い大学院を活用するのもオススメです!
5. モチベーションを保つ!
長期間にわたり仕事と学業を両立させるには、モチベーションを維持することが不可欠です。
大学院進学をし、無事終了するには少なくとも2年の時間がかかります。
これだけの期間、モチベーションを維持するのはなかなか大変です。
モチベーションを保つために「自分の目標を紙に書き出し、日々の進捗を記録すること」などを行っている人もいます。
同じく大学院で学ぶ仲間と情報交換をすることもモチベーション維持につなげることができます。
仲間と励まし合いながら学ぶことで、長期間の学習も続けやすくなります。

6. ネットワーキング(人脈形成)
社会人大学院では、人脈形成が非常に重要です。
大学院で知り合った人が経営する会社に転職したひとが私の塾の受講生にもいらっしゃいます。
MBAコースでは特に、学生同士が現役のビジネスパーソンであることが多く、学びながら新たなビジネスパートナーと出会う機会が豊富です。
この人脈自体が、5で述べたモチベーション維持にも直結しています。
まとめ。働きながら大学院に通うためのポイント
働きながら大学院に通うためには、長期履修制度やオンライン授業の活用、スケジュールの調整など、様々な工夫が必要です。
特に、モチベーションを保ち、仕事と学業のバランスをうまく取りながら学ぶことが成功の鍵となります。
また、給付金制度や企業支援制度を活用することで、費用の負担を減らすことが可能です。
社会人が大学院に入って学ぶことは、キャリアアップやネットワーキングにもつながり、転職や昇進を目指す上での大きな力になります。
あなたも、自分に合った方法で働きながら大学院進学を実現し、キャリアを一歩前進させてみてはいかがでしょうか?

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!
社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」
という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料プレゼントしています。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾では早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績も豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらからどうぞ!



















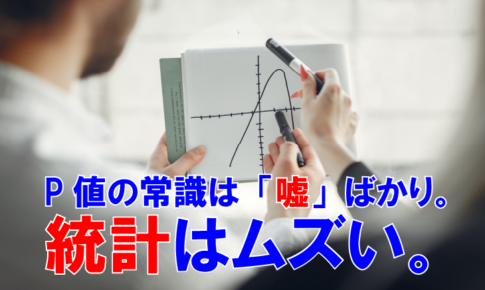


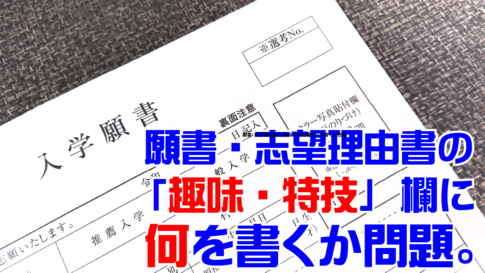










働きながら大学院に通うと自分の今後の可能性を一気に広げる事ができます。長期履修制度や職場の派遣制度、奨学金の活用などを通じて、仕事と学業の両立が可能になります。モチベーションの維持やネットワーキングをしながらキャリアアップや転職のチャンスを掴みましょう!