目次
卒業から13年!母校・早稲田大学大学院に行ってきました!
私が普段仕事しているのは北海道の札幌。
ですが、仕事の打ち合わせも兼ねて先日 東京出張に行ってきました。
その際、久しぶりに自分の母校である早稲田大学を訪れました。
向かったのは、大学院教育学研究科が入っている16号館。

ここで大学院時代の恩師とお話することができました。
今回はこの際の学びをもとに、「大学院での「意味があるかわからない学び」が、人生を変える!」というテーマでお届けします!
変わらぬ風景と、恩師との再会
私が早稲田大学に通っていたのは、学部生として2006年から2010年、そして大学院修士課程で2010年から2012年まで。
通算6年間です。
早稲田大学教育学・大学院教育学研究科の授業が行われるこの16号館に通い続けていました。
周囲には新しいピカピカの建物もたくさんできていますが、16号館だけは当時のまま(笑)。
よく言えば「歴史がある」と言えるのですが、悪く言えば「古くてボロい」という建物。
自分が在学していたときから(耐震補強が入ったものの)ほぼそのままということに逆に「驚き」を感じました。
いま学んでいる学生さんには悪いですが、卒業生としては「そのまま」というのがちょっとうれしく感じたのも事実です。

今回の訪問では、大学院時代の恩師である吉田先生とも再会することができました。
先生の変わらぬ笑顔と接することができ、自分にとっても大学院時代を思い出し、背筋が伸びる思いがしました。
大学院での学びが、今の仕事に生きている
私が吉田先生のゼミで学んでいたのは、教育社会学や高等教育論といった分野です。
教育社会学というのは教育という現象を社会学の視点から批判的に考察する学問です。
高等教育論というのは専門学校・大学・大学院という「高等教育機関」や「高等教育制度」についてを研究する学問となっています。
当時の私は将来研究者になるつもりでゼミに参加していたため、先輩方の論文や発表に対して遠慮なくダメ出しをしていたのを覚えています(笑)。
(当時の先輩方、すみません…9
でも、その経験が今の仕事に確実につながっています。
私は現在、社会人の方々の大学院進学をサポートする塾を運営しています。
その中では受講生の方の研究計画書の添削のほか、小論文・論文指導も行っています。
吉田先生のゼミで培った「批判的に読む力」や「論理的に構成する力」がまさにそのまま活きているのです。
さらに吉田先生の専門でもある「高等教育」に関する知見は、現在の塾運営や講義にも直結しています。
(そもそも私の法人名は「藤本高等教育研究所」ですので、そのまんまです)

吉田先生のゼミ在籍中は「研究者になる」ためにこれらの学問に取り組んでいました。
当時は修士課程からそのまま博士後期課程に進学予定だったのです。
ですが、自身のうつや今後の進路展望の見えなさから、博士後期課程の進学ではなく高校教員になる道を選択することになります。

高校教員を辞めて塾を開業することになるのですが、いま塾運営において吉田先生のゼミで学んだことがそのまま役立っています。
研究者になるという道を選ばなかったとしても、大学院での学びが確実に自分のキャリアを支えてくれていることを実感しています。

「これ、意味あるの?」と思っても、やってみる価値はある
社会人として大学や大学院に通っていると、ときどきこう感じる方もいます。
「これって何の役に立つんだろう……?」
「別にこの内容、今後の自分にはなんの役にも立たないのではないだろうか…?」
特に必修科目や、自分の興味とは違う領域の授業を取らざるを得ないとき、そう感じることは少なくありません。
でも、私は声を大にして伝えたいのです。
「取った以上、せっかくなら真剣にやってみましょう!」
これはスティーブ・ジョブズの有名なエピソードにも通じます。
スティーブ・ジョブズはリード大学在学中、たまたまカリグラフィー(西洋書道)の授業を受けていました。
その時は何の役に立つか分からなかったのですが、なんとなくおもしろそうと思い熱心に授業を受けていたそうです。
結局大学を中退し、ウォズニアックとともにアップル社を創業することになるのですが、その際カリグラフィーの学びがMacの美しいフォント設計につながったのです。
その結果、世界に影響を与える要素となったのです。
ジョブズはこのような経験を「点と点をつなぐ(コネクティング・ドッツ)」と語っています。
「予定外の出会い」が、人生の方向を変えることもある
「点と点をつなぐ」というスティーブ・ジョブズの発想は自分自身のキャリアを見ても当てはまる用に思います。
私は大学院において吉田先生のゼミで教育社会学と高等教育論について研究することになりました。
ですが私、最初から高等教育に興味があったわけではありません。
もともとはフリースクールを教育社会学の視点から研究したいと考え、修士課程に進学したわけです。
たまたま吉田先生のゼミが教育社会学だけでなく高等教育も専門となさっていたため、高等教育に関する分野も学ぶことになったのです。
結果的に、私は放送大学などの通信制大学をテーマに修士論文を書き上げました。
たまたま学ぶことになった高等教育論の分野が自分の専門になったわけです。
大学院に入学した当初考えていたテーマとは全く異なる内容を研究することになったのが面白いところだと思います。
(大きな声では言えないのですが、フリースクールの研究に挫折してテーマを変更することにしました…)

在学中は「十数年後、まさに今やっている高等教育論の分野、なかでも社会人の大学院進学支援という仕事を自分でやることになる」とは全く思ってもいませんでした。
ですが、大学院時代に学んでいたことがいまそのまま自分の仕事に直結していることにちょっとした「驚き」を感じています。
吉田ゼミに入り、高等教育研究をすることになった御縁が、今の自分につながっているのです。
あらためて、吉田先生への感謝の思いが湧いてきます。
今回、再びお会いできてとても嬉しいです!ありがとうございます!!
インタビューから学んだ「視点が増える学び」
ちょうど先日、社会人大学院生のAさんにもインタビューをしました。
Aさんはもともと工学系分野の大学院を出て、工学分野で専門の仕事をなさっている方です。
Aさんは社会人になってから人文系の大学院に入り直した経験を持っています。
その時、人文系の学問のあり方に相当な「違和感」を持った、と語っていました。
工学分野では実験するのが研究です。
ですが人文系では人間にインタビューしたことがそのまま研究に直結します。
そのことに違和感を覚えていたそうなのです。
「なんでこういうことをするのか」「なんで人の話を聞くだけで研究になるのかわからない」などと疑問を感じていたAさん。
ですが学びを進めるうちに、工学系の視点だけでなく人文系の視点からも物を見れるようになった、と話されていました。
「2つの視点で物事を見られるようになったことが仕事においてもお客さんと話すうえで役立っています」とも語ってくださいました。
これこそが、学びの力なのだと思います。
最初は「なんでこういうことをするのか」と疑問を感じていても、その学びがあとあと自分の今後にも役立っていく。
こういうことは実際にあるのです。
(Aさんのインタビューは近日公開予定です)
どんな授業にも、意味はある!
大学や大学院に社会人の方が入ると、いろんな授業を履修することになります。
「この授業、取って意味があるのだろうか」
「なんでこんな内容をやるの?」
そう感じる授業や課題もあるかもしれません。

ですが、学びというのは、その瞬間には意味がわからなくても、後から役立つことが必ずあるのです。
たまたま取った授業が、自分の今後に直結する。
こういうことも実際にありますし、こういう授業がいつかあなたの未来を変える「点」となるかもしれないのです。
だからこそ、私は「せっかく授業を取ったのなら、全力で学んでみましょう!」とお伝えしたいのです。
社会人の場合、仕事の関係で「取りたい授業よりも時間的に取れる授業しか受けられない」ケースは実際にあります(けっこうあります)。
ですけど、「卒業するために仕方なく出席する」だけだともったいないのです。
やるならとことん。
履修したなら全力で学んだほうが良いのです。
その学びが、いつか自分のキャリアにおける「点と点をつなぐ」ことにもなるからです。
ぜひ「意味があるかわからない」学びこそ、自分のキャリアに直結する可能性があると考えて取り組んでみてくださいね!

「社会人大学院のリアル」はこちら!













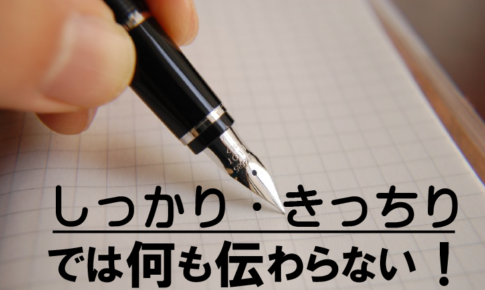



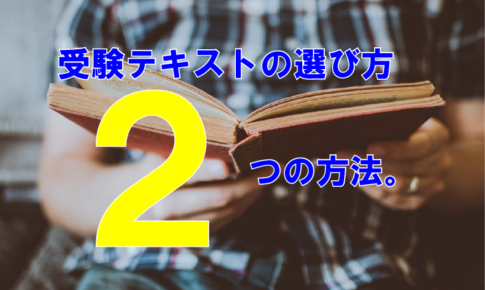









久々に母校・早稲田大学/大学院に行き、大学院時代の恩師と再会しました。そのなかで、当時「意味があるかわからない」と思っていた学びが、今の仕事に深く役立っていると実感しました。「意味があるかわからない」学びこそ、やってみる価値がありますよ!