目次
取りたい授業に限って、スケジュール的に履修不可能なツラさ。
「どうしよう、この授業を取りたいのに、この時間は毎週会議が入っている…」
社会人として大学院に通う際、多くの方が悩むのが「授業の開講時間問題」です。
取りたい授業があるのに、なぜか定例会議など外せない業務の時間帯とかぶってしまう・・・。
逆に、取りたくもない授業に限って平日夜間に開講されている・・・。
取りたい授業ほど仕事や家事の時間とかぶり、どうでもいい授業ほど履修しやすい時間に開講されている・・・。
こういうジンクスは実際にあります。
社会人として働きながら大学院に通うのはキャリアアップにつながる素晴らしい挑戦であると私は思います。
ですが、実際にその道を歩んでみると想像以上に「スケジュール」との戦いであることに気づかされます。

今回は「社会人大学院生の切ない現実」と題し、「取りたい授業よりも取れる授業ばっかりを取りがち問題」について見ていきます!
取りたい授業ほど、取れない時間に開講されているジンクス。
私は現在 北海道大学の公共政策大学院に在籍しつつ、塾経営と研修講師の仕事を行っています。
北大公共政策大学院に入ったのは2023年4月。
「長期履修制度」をつかっている関係上、今年で修士課程3年となります。
研修講師の仕事って、基本的に平日昼間に1日かけて行われます。
これまでも北海道内各地(札幌・旭川・函館・帯広・釧路・根室・稚内など)で開催してきましたし、今年度もあちこちで研修のご依頼を頂いています。

半年〜1年以上前からご依頼を受けることもあります。
そうなると、新年度の授業履修を考える「前」からすでに研修の予定が決まっています。
私が毎年4月に悩むのは、研修の予定を見たうえで「何曜日のどの時間帯なら大学院の授業を履修できるか」を必死で考えること。
まるでギチギチに詰まったパズルを前にしているかのように「どの時間帯にどの授業を履修するか」に悩むことになります。

このパズルの難しさこそ、社会人大学院生が直面するリアルな課題なのです。
(履修し始めても、大抵は数回出席できない日程になっているのが毎回切ないところです…)
「この時間だけは絶対に無理」が積み重なる日々
なかなかツライのは、スケジュールが先に決まっている関係上、「取りたい授業よりも取れる授業」を優先せざるを得ないこと。
大学院で学びたい授業があっても、それがたとえば平日昼間などに設定されていた場合、社会人にとっては「絶対に無理」ということがよくあります。
特に会社員であれば、平日の昼間は定例会議が入っていたり、業務から抜けられなかったりすることが普通です。
その結果、せっかく興味を持っていた授業が取れず、代わりに「空いているから仕方なく取る」授業を選ぶしかなくなる事も多いのです。
「なんのためにこの授業を取っているんだろう…」
そんなジレンマを多くの社会人大学院生が抱えています。

授業の「曜日」と「時間」が最大の関門
私自身も、平日の昼間に研修講師の仕事が入っているため、大学院の授業を組むのが至難の業です。
仮に取ったとしても、物理的に何度か欠席せざるを得ないことが予想されます。
大学院では一般的に「3分の2以上の出席」が単位取得の条件とされています。
前期・後期の授業はそれぞれ15回行われますので、「6回以上欠席するとアウト」という計算になります。
しかも、これは「5回までは休んでいい」という意味ではありません。
出席点もバッチリ設定されているので、欠席は成績ダウンに直結します。
なので私も、なるべく全部の授業に出席したいのですが、いかんせん出張で出席できないことも当初から考えておく必要があるのです。

なお、仕事で出席できない回がある際は履修の最初から教員に相談しておくのがオススメです。
「欠席時、代替課題を提出させてもらえませんか」と相談しておくと認められるケースがあります。
そもそも大学から直で大学院に進学した大学院生も就職活動で授業の欠席を余儀なくされるケースがありますので、最初から相談しておくと欠席対応をしてもらえることもあります。
小樽商科大学大学院の「切なさ」。3日休んだらアウト!
ちなみに、この欠席のツラさで言いますと、小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(通称OBS。MBAが取れます)はけっこうツラいです。

(ちなみにOBSはうちの塾が合格実績No.1です)
OBSはそれぞれの授業が2週間に1回2コマ連続で行われます。
1日休むことは2回分の授業を欠席したことになります。
ということは3日授業を休んだ時点で単位習得が不可能になってしまうのです。
しかも必修科目が多いので、下手をすると3日授業を休んだことが理由で「留年」の可能性も出てきます…。
なのでこの場合 なんとしても「3日以上欠席しない」努力が必要不可欠だと言えるのです。
土曜日の授業が社会人にとっての「命綱」
そんな中、土曜日開講の授業は社会人にとって非常にありがたい存在です。
平日昼間のように業務との重なりが少なく、比較的時間が確保しやすいのが理由です。
私の場合も、受講生との授業調整などがあるものの、土曜日は基本的に空けやすいため、土曜開講の授業を毎年履修してきました(今年も履修します)。
逆に言えば、土曜以外の授業は履修を断念せざるを得ないケースもそれなりにあります。
結果、「取りたい」よりも「取れる」が優先される現実があります。
これ、なんとかならないかな・・・といつも思っているところです。
Zoom授業がもたらした希望と現実
実は私が入学した2023年当初はいまよりも履修がしやすかったのです。
当時はコロナ禍が開け始めた時期でした。
そのため、Zoomによるオンライン授業もそれなりにありました。
出張中や移動先でも参加できる環境が整っていたので、「取りたい授業」を取りやすい現実がありました。
(出張の際、ホテルからZoom授業に出席できてたいへん助かりました)

ですが、2024年度・2025年度になるにつれ、Zoom授業は減っていっています。
Zoomベースの授業がもう少し定着してくれると、社会人にとっての大学院は格段に通いやすくなるのではないかと感じているところです。
授業の曜日・時間は「早く知りたい!」
で、このへんは私の「愚痴」というか「要望」なのですが、大学院の時間割ってできれば早く公開してほしいなあ、と思っているところです。
たとえば私が通っている北大公共政策大学院は次年度の時間割が出るのは毎年3月半ばです。
たいていの授業は毎年同じような時間帯で開講されるとはいえ、このタイミングにならなければ授業時間帯がわからないのはけっこう困ります…。
それは研修講師の仕事って半年以上前から予定が入ることも多いためです。
そのため、時間割表が発表されたときには「ああ、この曜日は研修出張だから100%ダメだ…」と絶望することがあります。
もちろん、大学教員との調整があるのはよくわかりますが、できれば1〜2月頃から情報が出るとありがたいなあ、と思っています。
「元を取る」ためにも、取った以上は授業に全力を!
今回は愚痴も交えてですが「社会人大学院生のリアル」として「取りたい授業よりも取れる授業が優先される理由」についてを見てきました。
せっかく履修する以上、イヤイヤ取るのは考えものです。
せっかく学費を出している以上、「元を取る」つもりで全力で取り組むことが大切だといえます。
自分にとってベストな授業ではないかもしれませんが、そこでの学びが新たな興味や視点につながることもあるからです。
なお、志望する大学院にすでに通っている社会人の方がいれば、どの曜日にどんな授業が開講されているのか、どのようにスケジュール調整しているのかを聞いてみるのもおすすめです!
事前情報があれば大学院に入ってからもスムーズに履修計画が立てられるはずです。
まとめますと、社会人が大学院で学ぶということはスケジュールとの戦いでもあります。
スケジュールの都合で本当に取りたい授業が取れないこともありますが、それでも「取れる授業」の中で最大限の学びを得る姿勢が重要です。
こうした制約の中でも学び続けることそのものが、社会人大学院生としての価値なのではないでしょうか。
ぜひあなたも、自分のスケジュールと相談しながら、悔いのない大学院生活を送ってくださいね!
こちらのシリーズで「大学院のリアル」を知りませんか?
「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!














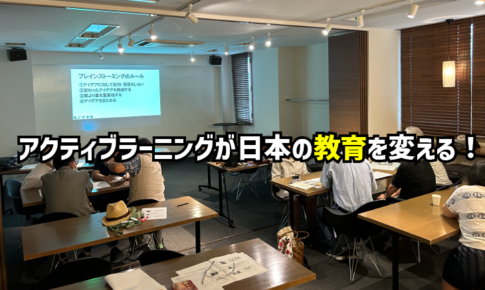

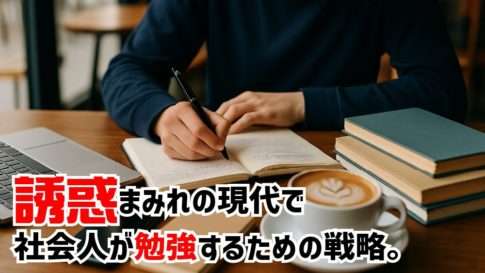


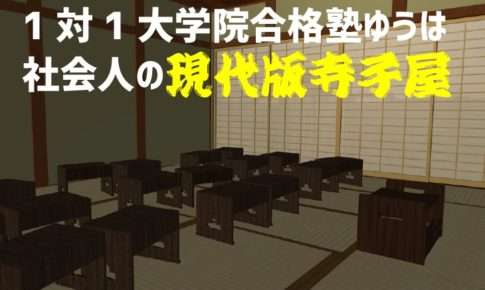
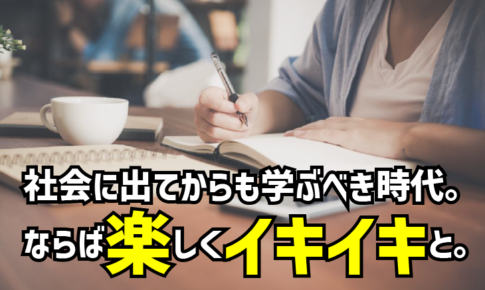
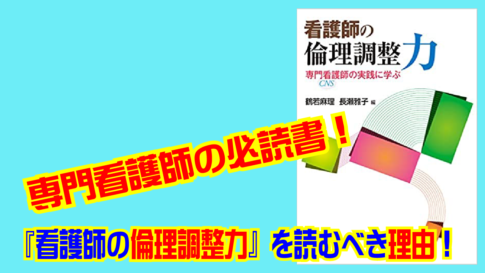






社会人が大学院で学ぶ際、スケジュールとの戦いが現実です。取りたい授業が仕事や家事と重なるため、「取りたい授業」より「取れる授業」を選ばざるを得ないことも…。ただ、そういう場合でも履修した授業の学習に全力を出すことが重要ですよ!