目次
研究を趣味にする!在野研究者になろう!
突然ですが、あなたは「在野研究(ざいやけんきゅう)」という言葉をご存知でしょうか?
在野研究とは、大学や研究機関などに所属せず、自らの関心に基づいて研究を行い、その成果を学術論文や書籍として発表することをいいます。
いわば研究を“趣味”として続けている生き方。

大学教員などの研究者は「生活の糧」として研究をしているわけですが、そうではなく在野研究をしている人は純粋に「知的好奇心」に基づいて研究をしています。
在野研究者のなかにはプロの研究者以上の知見や実績を持つ方も少なくありません。
今回は社会人こそ目指したい「在野研究者」の生き方をご紹介します!
在野研究の先人たちに学ぶ!
大学・大学院などの研究機関に所属せずに研究を進める…。
在野研究者の代表例としてよく挙げられるのが、歴史学者のフィリップ・アリエスです。
アリエスは「日曜歴史家」として知られています。
本業が休みの日曜日や仕事の合間で研究を進め、学術的に高く評価される成果を残しました。
アリエスの著書『子供の誕生』などは、歴史学の常識を塗り替えるほどのインパクトを持っています。
私自身も教育学部在籍中に読み、「中世には子どもという存在は認識されていなかった」という事実を解き明かすアリエスの知見に感銘を受けたのを覚えています。

(アリエスの著書『子供の誕生』は教育学を学ぶうえでの必読書でもあります。
詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/4mlooud)
同様に、エリック・ホッファーもほぼ独学で社会哲学について学び、本業とは別で研究を進め多大な業績を残しています。

(写真はWikipedia)
ほかにも、「在野の研究者」という意味では思想家・吉本隆明(よしもと・たかあき)も在野研究者としてカウントできるかもしれません(吉本隆明は作家として考えることもできますが)。

(吉本隆明の本で一番感銘を受けたのがこの『共同幻想論』です。
詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/3H1m8Ze)
このように、在野研究という営みは古くから行われてきました。
在野研究は学問の発展に大いに貢献してきたともいえるのです。
研究機関に在籍していなくても研究は実施可能!
「大学院での学びをもっと深めていきたい!」
「自分のテーマを、もっと研究したい!」
大学や大学院に学ぶ社会人の中にはこういった思いを持つ人も多くいらっしゃいます。
「でも、大学や大学院など研究機関にポストを見つけるのはメチャクチャ大変…」
そういう思いから研究を続ける道を断念する人も残念ながらいらっしゃいます。
ですけど、研究は研究機関に在籍していなくても続けることができます。
実験設備が必要な理系分野ならたしかに大変かもしれませんが、本とパソコンさえあれば研究できる文系分野なら意外と実現可能性が大きいのです。
私が思うのは、研究したいなら研究機関でポストを見つけられるか関係なくガンガン研究を続けていったら良いのではないか、ということです。
「研究をしたいからひたすら研究する」
「研究が面白いから続ける」
こういう生き方を目指すのもアリだといえるのです。
プロの研究者でなくても「在野」の立場で研究を続けている人は昔からたくさんいます。
『在野研究ビギナーズ 勝手にはじめる研究生活』という本もあるように、勝手に研究生活を始めても何ら問題ないのです。

むしろ「食うために研究する」わけでない以上、より純粋な知的好奇心から研究を深めていくことも十分可能なのです。
☆『在野研究ビギナーズ』の詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/43lguIE
なお、荒木優太さんの著書『在野研究ビギナーズ 勝手にはじめる研究生活』の前著は『これからのエリック・ホッファーのために: 在野研究者の生と心得』となっています。
この記事で言及した「エリック・ホッファー」が在野研究者の「お手本」として描かれていることに注目していただければ、と思います。
☆詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/3Zo9F7X
動画でも紹介しています!
教員も在野研究の担い手!
日本でも在野研究者は多数存在しています。
なかでも教員が在野研究を担う例も多くあります。
日々の授業や業務の傍ら、自らの専門に関心を持ち、調査や執筆を続け、学会発表や論文投稿を行う。
こういう人が意外とたくさんいました。
実際、英語科教員が英文学研究を在野で行っていたり、歴史科教員が歴史研究を同じく在野で続けていたりするなど、教員には在野研究者が昔から多く存在していたのです。

教員の在野研究者が意外といるのは、「大学院で研究していたけれど仕事がなくて教員になった」というケースが多いからです。
教員になってからも、以前からやっていた研究を継続しているという熱意を持つ人が在野研究を支えています。
他にも、「大学院で研究していたけれど仕事がなくて企業就職した」「公務員になった」という方が在野研究を続けているケースも多いです。
私もいちおう在野研究者。
実は私自身も、一瞬「在野研究者」だった時期があります。
高校教員として4年間勤務していましたが、その中で日本通信教育学会で発表を行い、論文投稿もしています。
(可能であればいま一度「在野研究者」に戻って研究しようとも思っています)
日本通信教育学会で研究したことは自分自身の成長にもつながりましたし、専門性を向上させることにもつながりました。
それが高校教員としての日々の授業にも活かされていたのを覚えています。
在野研究が本業にも活かされることを実感したしだいです。
「大学院」という選択肢
「自分も思い切って研究をしていきたい!」
そういうとき、大学院で身につける研究スキルが大いに役立ちます。
大学院修士課程って言ってしまえば「自力で研究する力を身につける」「自力で論文を書き上げる力を身につける」ためだけの場所でもあります。
なので大学院で学んだ基礎的素養さえあれば、あとは仕事をしながらいくらでも「在野研究者」として活躍することは十分可能です。
逆に、いくら研究しようと思っていても大学院にいかずに完全に独学で研究するのはかなり「キツい」ことであると言えます。
なので「研究をしたい!」という思いがある方はまずは大学院に進学することをオススメします。
社会人として働きながらでも、通信制や夜間・土日開講の大学院を活用することで、研究の道を切り拓くことが可能な時代となっています。
すでに大学院在学・修了なさっている方は、大学院での学びをもとにどんどん「在野研究」を進め、学会発表・論文投稿に邁進していくのがいいですね!
実際、私のまわりにも働きながら大学院に通い、大学院修了後も研究を継続している方が多数いらっしゃいます。
こういう方のもつ見識の深さにいつも学ばせていただいています。

研究は、誰にでも開かれている
研究は、決して大学の教員や研究所に勤める人だけの「特権」ではありません。
興味を持ち、調べ、まとめ、そして発表する意志があれば、誰でも始めることができます。
もちろん簡単な道ではありませんし、時間の確保や知識の整理は大きな課題です。
ですが、だからこそ大学院で「研究の仕方」を学ぶことが、大きな武器になるのです。
学びたいことがある。深めたいテーマがある。
その情熱こそが、研究の出発点です。
研究したいテーマがあるのであれば、ぜひ「在野研究」という生き方も考えてみてはいかがでしょうか?
こういう人が増えていくことで学問の世界はより一層豊かになっていきます。
それになにより、研究するのは「知的好奇心」をくすぐる非常に面白いことでもあるのです。
在野研究というスタイルで自らの知的世界を切り拓くことはあなた自身の仕事や人生にも深い充実をもたらしてくれるはずですよ!

「社会人大学院のリアル」はこちら!













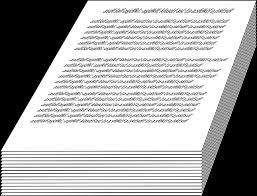
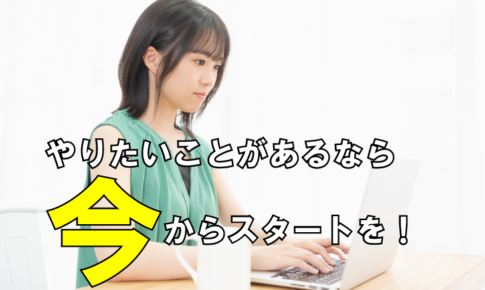



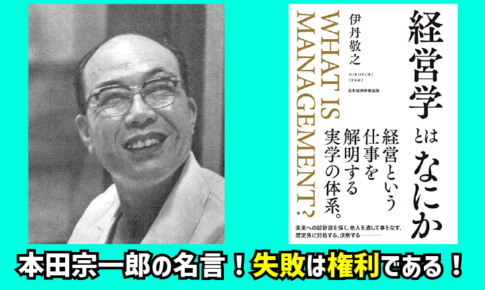

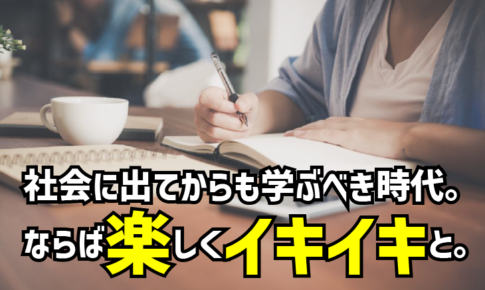






在野研究とは大学などに所属せず自らの関心で研究を行い、論文や書籍として発表する生き方です。知的好奇心を原動力に誰でも始められる研究スタイルであり、社会人の中にも実践する人が多くいます。あなたも在野研究者を目指してみませんか?