目次
「今後のためにMBAを取りたい」という発想の問題点。
「周りから認められたいから、大学院でMBAの資格を取りたい!」
「外資系企業への転職を成功したいから大学院でMBAの資格を取る!」
こういう思いを持って勉強している方って多いかもしれません。

いまよりも自分をより良くしたいという向上心が溢れていてとてもいいですね!
この考えの背景には「目的-手段関係」が存在しています。
つまり、「周りから認められたい」「転職に成功したい」という「目的」を達成するために大学院でMBA(経営管理修士)の資格を取るという「手段」を目指すという考えが隠れているのです。
このこと自体には一見なんら問題はなさそうですが、下手をするとこの考えではつまづいてしまうこともあります。

今回は「目的-手段関係」でキャリアアップを考える問題点を解説介します!
國分功一郎さん『手段からの解放』読書会を開催しました!
私の塾では毎月 読書会を開催しています。
先日は國分功一郎(こくぶん・こういちろう)さんの『手段からの解放』をテーマにした読書会を開催しました。

☆『手段からの解放』の詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/4ca6zJW
本書では現代においてあらゆるものが「手段」としてしか捉えられなくなっているという問題提起がなされています。
私たちはついつい「何の役に立つのか」「将来のためになるのか」といった視点から、すべての行動や選択を評価しがちです。
その結果、何かを純粋に楽しむという体験が、どんどん失われつつあるのではないかと指摘しているのです。
なぜ私たちは「楽しむ」ことが難しくなったのか?
著者の國分さんは、現代人が「目的のための手段」にとらわれすぎて何も楽しめなくなっていると指摘します。
たとえば、チェスをやるにしても「戦略的思考を身につけるため」、資格を取るのも「キャリアアップのため」、将棋をするのも「論理的思考の訓練のため」など、何かしら自己向上に結びつけようとする傾向があります。

この発想がひどくなると、例えば「絵を習いたい」という社会人がいた場合「どうせ今更プロになんてなれないんだから学んでもムダ」とアドバイスしてしまうようになります。
あるいは「韓国語を習いたい」という社会人がいた場合も「通訳にでもならないならやっても無意味」と言ってしまうことになります。
これは、新たに何かを学ぶ場合、そのことが何らかの「役に立つ」「お金になる」ことがなければムダという発想が前提にあります。
今後なにか役に立ったりお金になったりする可能性が低いなら、そういうムダなことはしないほうがいい。
こういう考え方があるのです。
ここには「楽しむために絵を習う」「楽しいから韓国語を習う」という発想が欠如しているのです。
「目的-手段関係」の落とし穴。
「目的-手段関係」で物事を考えることには「楽しむ」という発想がなくなっているという問題点があります。
本来なら楽しむためにチェスや将棋をしたり、資格勉強をしたりする発想があってもしかるべきなのですが、「楽しむ」ことがどこか低級な感覚なように思われてしまっているのです。

「目的-手段関係」は常に向上を目指します。
なのでどこかで満足したり、充足したりしてしまったらもう上にいけなくなってしまいます。
一方、「楽しむ」ことはいまに満足し、いまを充足することを意味します。
「楽しむ」時点である意味 向上が終わってしまうのです。
そのため、「目的-手段関係」で考えると、いつまで経っても満足することができず、「努力しても努力し尽くしても楽しめない」「努力してるのになぜか虚しい」という思いになってしまいます。

キャリアアップと目的・手段の関係
「手段としてしか物事を見られなくなる」という傾向は、キャリアアップにも深く関係しています。
例えば、大学院に進学する場合でも、「転職に有利だから」「独立して経営に役立つから」「昇進の条件になるから」といった「目的」が前提となることがほとんどです。
MBA取得や看護系大学院への進学なども、多くの人が「キャリアのための手段」として考えがちです。
もちろん、それ自体は悪いことではありません。
むしろ現実的な判断としては正しいでしょう。
しかし、大学院生活は通常2年間、長期履修なら3〜4年もあります。
大学院での学習が「手段」に過ぎない状態の場合、これだけの長時間 勉強し続けることは可能でしょうか?
人によっては途中で学ぶ意欲が途切れてしまう、あるいは日々苦しくて仕方なくなることも起きうるのです。
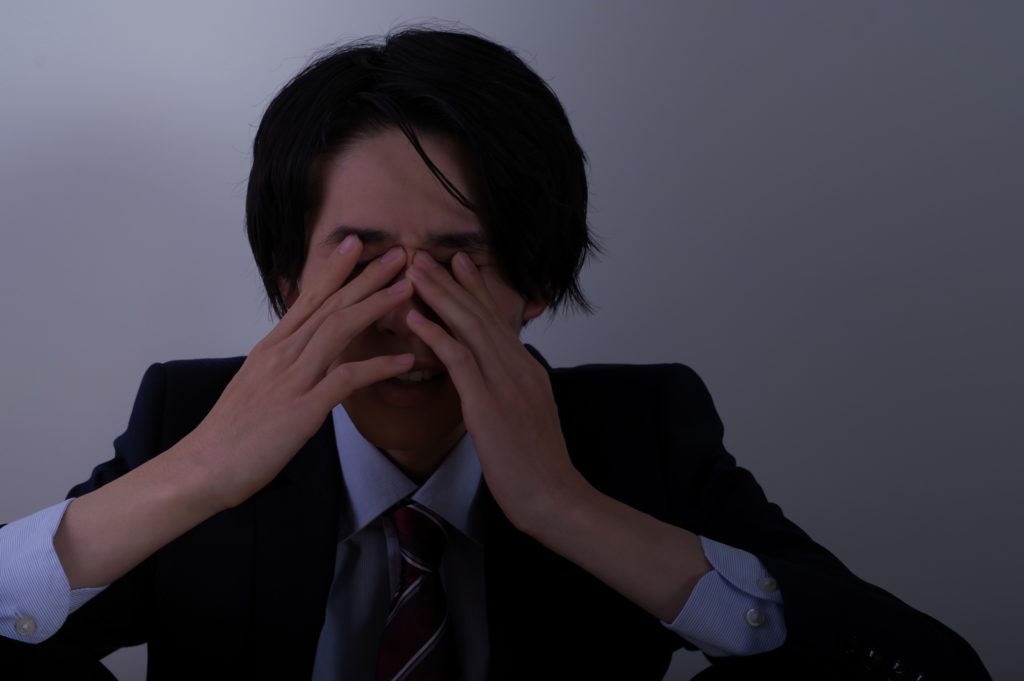
行動自体を楽しもう!
ではどうしたらいいのでしょうか?
その答えは「楽しむ」ということです。

勉強すること自体・努力すること自体を「楽しむ」のがポイントなのです。
いい例となるのがコーヒーやお酒などの嗜好品です。

嗜好品をたしなんでも別にお腹は膨れませんし栄養が取れるわけでもありません。
でも、嗜好品を口にすると「楽しい」「幸福」な気持ちが広がります。

私はカフェオレが好きですが、カフェオレは健康のために飲んでいるわけでも、水分補給のために飲んでいるわけでもありません(コーヒーには利尿作用がありますので)。
カフェオレが飲むのに理由はいりません。
ただ美味しいから飲む。それで十分なはずです。
にもかかわらず、私たちは「健康に良いから」「集中力が高まるから」といった“合理的な目的”を求めずにはいられないという「病んだ」社会に生きているのですね。
逆に言えば嗜好品に注目することは現在のように「目的-手段関係」がいちじるしい「病んだ」社会に対してその処方箋を出すことにもつながるのです。
(國分さんはこういう視点から「手段からの解放」を目指すべき、と主張しているわけです)
勉強自体を楽しもう!
「目的-手段関係」も確かに重要ですが、それだけで考えると勉強するのも努力するのも辛くなります。
だからこそ、「学ぶことそのものを楽しむ」姿勢が重要なのですね。

「新しいことを知ることが嬉しい」「学んでいる時間が充実している」と思えたとき、学びは単なるキャリアアップのための“手段”ではなく、自分の人生を豊かにする“目的”にもなります。
モチベーションが続かないのは「手段」だけにしてしまうから
目的と手段だけで物事を考えてしまうと、思い通りにいかなかったときの失望も大きくなります。
例えば、「この資格を取れば転職がうまくいく」と思って勉強していたのにうまくいかなかったとき。
そんなとき、「努力は無駄だった」と感じてしまうかもしれません。
でも、学ぶこと自体が楽しいと思えていたら、結果が出なくても意味があると感じられるのです。
勉強することが楽しくなると、受験に受かるジンクス
大学受験のジンクスでも、「勉強すること自体が好きになると受かる」という話があります。
最初は浪人してイヤイヤ日々勉強していた(目的のためだけに動いていた)状態から、「仮に受からなくても、勉強自体が楽しいから不合格でもまあいいかな」と思えるようになる。
そうやってプロセスそのものを楽しめるようになったとき、結果としてうまくいく。
そんな話が実際にあるのです。

キャリアアップこそ「楽しむ力」が求められる時代へ
キャリアアップは今後のための「手段」でしょうか?
それとも楽しむ対象としての「目的」でしょうか?
私の答えは、「その両方であっていい」ということです。
ですが、忘れてはならないのは学びそのものの楽しさを感じられるかどうかがポイントになる、ということです。
キャリアアップを目指す取り組みはどうしても長期戦になります。
うまくいかないことも多いです。

だからこそ、「キャリアアップ」を「手段」としてしか考えていない場合、「こんなにやっても結果が出ないなら辞めてしまおう…」と思いがちなのです。
そうではなく、キャリアアップに向けての勉強自体を楽しむことが必要なのです。
これが、長期的な成長や継続的なモチベーションの鍵になります。
國分功一郎さんの『手段からの解放』は、私たちに目的手段関係から自由になることの大切さを教えてくれます。
キャリアアップという目標に向かう過程でこそ、学ぶこと自体を楽しめているか問うてみるのもオススメですよ!
ではまた!
「キャリアアップを科学する」シリーズはこちら!




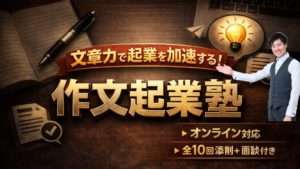












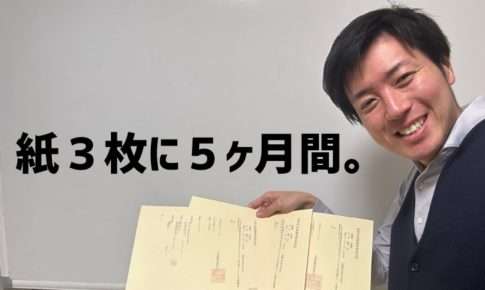










私達はついつい「今後のキャリアアップのために勉強する」と、勉強を「手段」扱いします。この発想、向上心があっていい反面、うまくいかないことがあると途端に挫折しやすいという問題点があります。大事なのはキャリアアップのため関係なく勉強それ自体を楽しむ、つまり、勉強すること自体を目的としても考えることです。そうするとうまくいかないことがあっても勉強を継続し、結果的にキャリアアップができるのです。