(インタビュー実施日:2025年2月18日@Zoom)

1987年大阪生まれ。私立大学教育学部、同大学大学院臨床心理学専修修了。
現在、東京都の中学校・高校のスクールカウンセラーをしながら2024年11月に「水野心理教育相談室」を開室。
☆動画はこちら↓
目次
スクールカウンセラーとして活躍。昨年は相談室を開室!
―― 今回は、カウンセラーとして独立し活躍されている水野正幸(みずの・まさゆき)さんにお話を伺います。
まずは、水野さんの現在の活動について教えていただけますか?
水野: 私は現在、主に学校関係でスクールカウンセラーをしています。
中学校や高校での勤務経験があり、小学校でのスクールカウンセラーもしていました。
それ以外にも、電話カウンセリングや、心理職を目指す大学生のサポート、さらには都内の高校で職場環境の改善アドバイザーも務めています。
―― すごく幅広い活動をされているのですね。最近では相談室も開業されたとか?
水野: そうなんです。
昨年11月から、東京で「水野心理教育相談室」という相談室を開室しました。
ありがたいことに、ご縁がつながって今の形になりました。
カウンセラーを目指すきっかけ
―― もともとカウンセラーを目指したきっかけは何だったのでしょうか?
水野: 実は、小学5年生の時に不登校の特集を読んだことがきっかけです。
その特集の中で、スクールカウンセラーの存在を知り、「これはすごくいい仕事だな」と思いました。
また中学生の頃に心理テストにすごくハマっていました。
面白かったので、図書室の心理テストの本をすべて読破したことを覚えています。
読み終えたあと、その延長でとなりにあった臨床心理学の本を手に取り、そこからどんどん興味が深まっていきました。
―― それほど早い段階から心理学に興味を持たれていたのですね!
水野: そうなんです。ただ、大学は心理学部ではなく、教育学部でした。
併設の大学院に心理学のコースがあったので、「大学院で心理学を学ぼう」と考えていました。当時、教員免許も取得したいと考えていたので、中学校の社会科の免許を取りました。
―― 教育実習も経験されたのですね?
水野: はい、中学校で教育実習をしました。
そのとき先生方の仕事を間近で見て、教育の大変さを実感しました。
みなさん情熱を持って取り組んでいらっしゃいますけど、1クラス30-40人いる児童・生徒の責任がすべて先生の肩に背負わされているのは本当に大変だなと。
それだけに先生自身が精神的に追い込まれてしまうことも多く、「支えが必要だ」と強く感じました。
それで、「スクールカウンセラーになろう」と決めたんです。
―― なるほど。教育実習の経験がスクールカウンセラーを目指すきっかけになったのですね。
心理大学院での学び
―― 大学院ではどのようなことを学ばれましたか?
水野: 大学院では、臨床心理学、面接技法、心理査定、統計法など、幅広い心理学の知識を学びました。
学部時代とは違い、「自分で深めていく」ことが求められましたね。同じ大学院生同士で勉強会を開いたり、研究を深める環境が整っていたりして、とても刺激的でした。
臨床心理士って教育・医療・福祉・司法・産業と多くの分野についての学習が必要なんです。

―― やはり大学院の学びは大変でしたか?
水野: かなりハードでしたね。
2年間、休みなく勉強を続ける日々で、学びの密度が非常に濃かったです。
授業を受け、面接練習もやり、論文も書くので大変でした。
でも、それだけに得るものも多かったです。
補足 心理職に関する2つの資格(臨床心理士・公認心理師)に関して
インタビューの中で水野さんより心理職に関する2つの資格について伺いました。
| 臨床心理士 | 公認心理師 | |
| 資格の種類 | 民間資格(公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会) | 国家資格 |
| 取得方法 | 臨床心理士を養成する大学院修了後、試験に合格する | 公認心理師を養成する大学・大学院修了時の試験に合格する |
| 資格の更新 | 5年ごと | 不要 |
以前は心理職の有名な資格としては臨床心理士しかありませんでしたが、現在は国家資格である公認心理師制度も成立しました。
なお、水野さんは両方の資格をお持ちです。
やりがいと大変さは表裏一体
―― カウンセラーの仕事のやりがいと大変な点についてお聞かせください。
水野: これはよく聞かれる質問ですが、正直、やりがいと大変さは表裏一体ですね。
すごく大変な仕事ですし、特に深刻な悩みを抱えた方との面談が続く日は、精神的にも体力的にも消耗します。
―― 具体的にはどのような点で大変さを感じますか?
水野: 相談者の悩みの深さや複雑さに直面すると、やはり揺さぶられますね。
一日中面談が続くと、帰宅するときにはヘトヘトになっていることも多いです。
ただ、そんな中で、相談者が「話して楽になった」「整理がついた」と感じてくれると、それが大きなやりがいになります。
―― 相談者の気持ちが軽くなることで、ご自身も充実感を感じられるということですね。
水野: カウンセリングの役割は、あくまで悩みを整理し、少しでも前向きになれるようサポートすることです。
全ての問題を解決できるわけではありませんが、相談者の負担を少しでも軽減できたと実感できると、「やっていてよかった」と思います。

メタ認知を鍛えるカウンセリングの訓練
―― カウンセラーとしての訓練についても教えていただけますか?
水野: 実はカウンセラーって、なってからも常に勉強が必要なんです。
―― へ〜、そうなのですね!
水野: たとえば大学院ではカウンセリングの面接練習のために、自分のカウンセリングの様子をビデオに録画することもあります。
その後、動画を見ながら逐語録を作成し、他のカウンセラーからスーパービジョン(指導)を受けるんです。
―― それはかなり自分自身を振り返る機会になりそうですね。
水野: そうなんです。
例えば、スーパーバイザーから「この時、君は何を考えていた?」と問われたり、「なぜこの言葉を選んだの?」と聞かれたりします。
最初は「特に考えていなかった」と答えたくなりますが、それでは通用しません(笑)。
自分が何を思い、なぜその言葉を選んだのかを深く掘り下げることで、より良いカウンセリングができるようになっていきます。
―― 自分の言動を客観視することが求められるのですね。
水野: まさにメタ認知の訓練ですね。
自分自身を深めることが、心理職の大きな特徴の一つだと思います。

(後編に続きます)




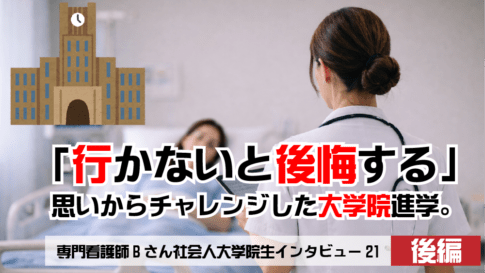
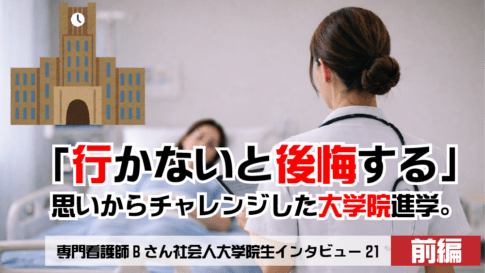





















現在、スクールカウンセラーや自身の相談室運営に取り組んでいらっしゃる水野正幸さんにインタビューを実施しました!心理の仕事は常に勉強が必要という水野さんから心理職の醍醐味と心理の大学院の魅力について伺いました。そんなインタビューの前編です!