(インタビュー実施日:2025年2月18日@Zoom)

1987年大阪生まれ。私立大学教育学部、同大学大学院臨床心理学専修修了。
現在、東京都の中学校・高校のスクールカウンセラーをしながら2024年11月に「水野心理教育相談室」を開室。
☆前編はこちら↓
☆動画はこちら↓
目次
聞き上手なカウンセラーたち
―― カウンセラーの方々は、やはり「聞き上手」な人が多いのでしょうか?
水野: カウンセラーは「聞く」という訓練を受けているので、自然とそうなります。
ただ、カウンセラーって単に黙って聞くだけではなく、けっこう「どうしてそう考えたのですか」とけっこう質問を投げかけてくるんです。
―― なるほど。ただ聞くだけでなく、会話をリードしながら相手の考えを整理する役割があるのですね。
水野: カウンセリングは、相談者が自分自身の気持ちに気づき、整理していくプロセスをサポートするものです。
そのためには、カウンセラー自身も深い洞察力を持ち、的確な質問をすることが求められます。

ところで藤本さんは聞き上手ってどういうイメージをもちますか?
逆質問みたいになりますけど。
―― え、聞き上手ですか…。そうですね、相手が話しやすいように興味のある話題を広げていくイメージがあります。
水野: それも大事ですね。聞き上手って、ただ話を聞くだけでなく、相手に関心を持ち、適切な質問を投げかけることが求められます。
よく「傾聴」という言葉が使われますが、「傾聴」という言葉ってもともと英語の「アクティブリスニング(Active Listening)」の訳語なんです。
―― 「アクティブリスニング」ですか?
水野: そうです。アクティブリスニングは、単に聞くだけではなく、積極的に質問をして相手の考えを深掘りするスキルです。
カウンセラーは黙って話を聞いているだけではなく、「それはどうして?」「その後どうなったの?」と質問を投げかけながら、相談者の思考を整理する役割を果たしています。
―― なるほど。一般的に思われている「聞き上手」とは少し違う印象ですね。
水野: そうかもしれませんね。
カウンセラーは、相手の話をただ受け止めるだけでなく、会話の中で適切に関心を示しながら、より深い部分にアプローチしていく必要があるんです。

心理職を目指す人へのアドバイス
―― 心理職やカウンセラーを目指す人に向けて、何かアドバイスをいただけますか?
水野: 心理職を目指す方の中には、「人を助けたい」「救いたい」という強い思いを持っている方が多いと思います。
その気持ちはとても大切ですが、同時に「なぜ自分は助けたいのか?」という点にも目を向けることが大事です。
―― といいますと?
水野: 例えば、「人を助けることで感謝されたい」「自分がアドバイスをして優越感を持ちたい」という気持ちがあるかもしれません。
それ自体は決して悪いことではありませんが、自分の内面をしっかり理解しておくことが、良いカウンセラーになるためには不可欠です。
つまり「なぜ自分は人を助けたいのか」ということを突き詰めていく必要があるわけです。
―― 確かに、自分の動機をしっかり見つめることは重要ですね。
水野: そうなんです。実際にカウンセラーが、自分自身についてカウンセリングを受けることもめずらしくありません。
自分自身の悩みを整理することで、より冷静に相談者の話を聞くことができるからです。

―― それは意外ですね。カウンセラー自身がカウンセリングを受けることって、なんだか「恥ずかしい」ことのように思うんですけど…。
水野: カウンセラーも人間ですから、悩みを抱えることは当然あります。
だからそういう悩みの相談をするのって「ふつう」のこと。
むしろ「恥ずかしい」と思っているということは、きつい言い方になるんですけど、相談に来た人を恥ずかしい人だと思ってしまうことになります。
だからこそ、悩みを相談するのは「ふつう」のことだと考えて相談し、自分の内面を整理することで相談者により良いサポートを提供できるようになるんです。
私もカウンセリングを受けにいくとき、車の中で「今日は何を話そうかな」と想像することでクライアントさんの気持ちを追体験できているように思います。
カウンセラーは常に勉強あるのみ!
―― カウンセラーなど心理職として成長し続けるためには、どのようなことが求められますか?
水野: 心理職は一生学び続ける仕事です。
臨床心理士の資格は5年ごとの更新制で、研修会や勉強会に参加してポイントを取得しないと資格を維持できません。
それに心理学の分野は常に進化しているため、新しい知識を取り入れ続けることが求められます。
例えば、最近ではHSPや発達障害、インナーチャイルドなどの概念が注目されていますし、新しい心理療法も次々に登場しています。
そういった最新の知見を学び続けないと、現場で適切な対応ができなくなってしまいます。

―― なるほど〜。心理職は、ただ資格を取得するだけではなく、常に自己研鑽が必要な仕事なのですね。
水野: そうなんです。勉強し続けることが求められる仕事ですが、その分、やりがいも大きいです。
大学院に進学して良かったこと・大変だったこと
―― 大学院に進学して良かったこと何ですか?
水野: 最初にも少し触れましたが、大学院では自分自身の興味を深めることができました。どの方向に関心があるのかをじっくり掘り下げることができ、同じ興味を持つ仲間と一緒に勉強したり、先生に質問しに行ったり、勉強会に参加したりと、知識を深める環境が整っていたことは大きなメリットでした。
あとは映画を学割で観れたこと、でしょうか(笑)
―― 逆に大変だったことはありますか?
水野: 正直、悪かったことはあまり思い浮かばないですね(笑)。勉強が大変だったことくらいでしょうか。
授業はかなり集中しなければいけませんし、2年間ほぼ休みなく勉強と面接の練習、論文作成に取り組むことになりました。

大学院を目指す方へのメッセージ
―― 最後に、大学院進学を考えている方へのメッセージをお願いします。
水野: 自分の興味関心を深く考え、それを突き詰めることが大切です。
大学院での学びは決して楽ではありませんが、自分のキャリアや人生に直結するものです。
しっかりと目的意識を持って、納得できる選択をしてほしいですね。
是非、勉強もそうなんですけれども、自分がどうしていきたいのかとか、なんでこういう風になっていきたいのかっていうところをガンガン深めていっていただきたいと思います。
それこそ色々な人に聞きながら、「自分はどうしていきたいのか」っていうのを考えていっていただけるとあなたの力になって行くんじゃないかと思います。
―― 水野さん、本日のインタビュー、ありがとうございます!
インタビューを終えて
心理カウンセラーとして活躍する水野さんの言葉には、現場で働くからこそ得られた深い洞察が詰まっていました。心理職を目指す方にとって、大きなヒントになるのではないでしょうか。
ちなみに、水野さんは私の高校の同級生。
高校時代から「母校でスクールカウンセラーになる!」という目標を話していたのが懐かしいです。
実際、水野さんは現在母校の高校でもスクールカウンセラーとして勤務なさっています。
まさに初心貫徹なさっている姿がすごいなと思います。
(昨年、札幌で一緒に飲んだのも懐かしいです)
今後も色々教えて下さい!
「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!





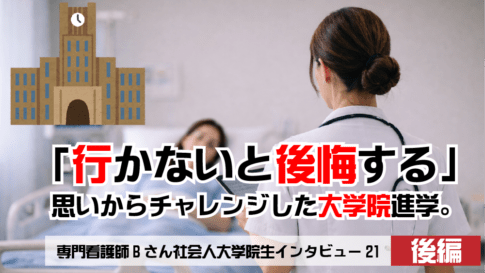
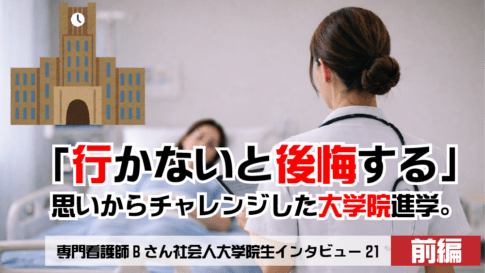




















現在、スクールカウンセラーや自身の相談室運営に取り組んでいらっしゃる水野正幸さんにインタビューを実施しました!心理の仕事は常に勉強が必要という水野さんから心理職の醍醐味と心理の大学院の魅力について伺いました。そんなインタビューの後編です!