目次
公務員が公共政策大学院を受験する際の研究計画書の書き方
「公務員としてキャリアアップをしたい!」
「自分のスキルを高めたい!」
そんな思いを持つ公務員の方にとって人気なのが公共政策大学院です。
東京大学・北海道大学・早稲田大学など全国に6箇所存在しているのが公共政策大学院です。
公共政策大学院は、政策の企画・立案能力を高めるための実践的な教育を提供する場です。
公務員として地域課題に取り組むために大学院進学を目指す方も増えてきています。

ただ、受験の際に必要となる「研究計画書」づくりで苦労している人も多いかもしれません。
今回は私自身が公共政策大学院(北海道大学の公共政策大学院)に通っている経験ももとに公共政策大学院受験の研究計画書作りについて見ていきます。
公共政策大学院受験用 研究計画書の書き方のポイント!
公共政策大学院受験用の研究計画書づくりの概要を一緒に見ていきましょう!

1. はじめに(研究テーマの設定)
研究計画書では「はじめに」において現在 行政分野で課題となっている内容や自身の職業経験から考えた問題点を指摘します。
その上で、そのテーマが重要である理由を自身の業務経験や地域の現状を基に説明していきましょう。
テーマ設定においては自身の行政経験や地域課題を基に具体的なテーマを設定するといいでしょう。
例えば過疎化・交通サービスの減少など現状の地域課題に根差したテーマを選ぶほか、公共政策の現場で活用できるテーマを定めると今後に役立てられるでしょう。
今回の記事では「今後の地域交通のあり方」について自治体の現状の課題と今後の展望についてを展望する研究計画を見ていきます。
2. 先行研究の検討
次に記載すべきは先行研究の検討です。
これまでに行われた研究や政策事例を検討し、これまでの研究で明らかになっている点と明らかになっていない点を指摘します。
その上で、明らかになっていないことでどのような問題が発生しているか、その内容を明らかにすべき理由はどこかを説明していきます。
地域交通の例ですと、過疎地域において現状取り組まれている地域交通政策にはどのようなものがあるか、どんんあ研究がなされてきたきたかを資料・論文などの文献をもとに説明していきましょう。
3. 研究方法
ここでは具体的な調査方法や研究方法を提示します。
例えば住民や行政職員に対するアンケート調査や他の自治体へのフィールドワークなどが考えられます。
これまでの政策事例を比較検討する文献調査も研究方法として役立ちます。
4. 倫理的配慮
ここでは研究協力者が不利益を被らないような配慮事項をまとめていきます。
(ここの記述が不要なケースもあります。
また、「倫理的配慮」については先行研究に書かれているような内容を書いておけば問題ございません)
5. 予想される結果
ここでは研究によってどのような結果が得られそうかを述べていきます。
調査によってどんな結果が出そうか、その結果を何に活かせるかをまとめていきましょう。
6. スケジュール
ここでは修士課程2年間のあいだで研究をどのように進めていくか展望をまとめていきます。
7. 参考文献
ここでは研究計画書作成のために参考にした資料や引用した先行研究を挙げます。
可能であれば、自分が学びたい指導教員の論文を引用するのもオススメです。
参考文献の書き方は学問ジャンルによってすべて異なります。
そういう場合、自分が学びたい指導教員が執筆した論文を1つ選び、その先生がどのように参考文献を記載しているかを「真似する」のがオススメです!

研究計画書の例「◯◯市における、今後の地域交通のあり方」
それではここから実際の研究計画書の例を見ていきましょう。
なお、本文に出てくる「◯◯」というのは研究者名が当てはまります。
引用している文献はすべて架空のものですので念の為…。

(1)はじめに
現在、わが国の地方都市では、人口減少や高齢化に伴い公共交通機関の維持が困難な状況に直面している。例えば国交省が実施した調査では公共交通機関の維持に困難を抱える自治体が全体の◯割に達したことを指摘している(国土交通省2024)。過疎地域において高齢者など交通弱者が移動するための手段を確保することは極めて重要な課題となっている。
本研究では北海道◯◯市における地域交通の現状と課題を調査し、地域住民の生活の質向上に寄与する持続可能な交通政策のモデル提案を目的とする。
(2)先行研究の検討
◯◯(2018)は地域交通におけるデマンド型交通(オンデマンド交通)の導入が高齢者や通学者の移動手段の確保に有効であると指摘する。
また、自治体と交通事業者が連携した事例として、過疎地域でのコミュニティバスの運営が地域住民の生活改善に寄与した例も報告されている(◯◯ 2020)。しかしながら、筆者が勤務する◯◯市においての調査や住民へのインタビューをもとにした研究は皆無に近い現状がある。
そのため本研究では、◯◯市の地域交通に関する現状分析を行った上で、◯◯市において今後求められる持続可能な地域交通のあり方を検討する。
(3)研究方法
次の研究を行う。
(1)調査対象:
北海道◯◯市の過疎地域に住む高齢者・通学者および自治体職員・交通事業者
(2)調査方法:
- アンケート: 地域住民を対象に、移動手段・交通利用の満足度や改善を希望する内容を調査する。
- インタビュー: 自治体職員や交通事業者への半構造化インタビュー調査を行う。
(3)データ分析:
- アンケート結果を用いた定量分析(クロス集計、相関分析など)を実施する。
- インタビューデータをカードにまとめた上でKJ法で分析を行う。
(4)倫理的配慮
す べての調査対象者に研究目的を説明し、書面による同意を得るものとし、同意はいつでも撤回できることを説明する。
得られたデータは匿名化し、個人が特定されることがないよう十分に配慮する。
(5)予想される結論・仮説
本研究により、◯◯市の地域交通の課題とその改善方法としてデマンド型交通やコミュニティバスの導入の是非を明らかにする事ができる。
これは高齢者や通学者の移動手段の確保という社会課題解決に役立てられるであろう。
現状において仮説として次のよう内容を考えている。
- 地域住民の移動手段確保が、社会的孤立の解消や地域活性化に寄与する可能性が高いのではないか。
- 自治体と交通事業者の協働による柔軟な運行モデルが、コスト効率と住民満足度の両立を実現するのではないか。
(6)研究スケジュール
次の計画で研究を行う。
- 修士1年前期: 文献調査と研究計画の立案
- 修士1年8-9月: アンケート設計および事前調査の実施
- 修士1年後期: 本調査(アンケートおよびインタビュー)の実施
- 修士2年前期: データ分析および仮説の検証
- 修士2年8-9月: 論文執筆と中間発表
- 修士2年後期: 論文仕上げと最終発表準備
(7)参考文献
- ○○, 2018, 『地域交通におけるデマンド型交通の有効性』, △△出版.
- ◯◯, 2020, 『地方自治体と交通事業者の協働モデル』, ××研究所.
- 国土交通省, 2024, 『 (白書名) 』.
まとめ! 事例を参考に研究計画書作成を!
さあ、いかがでしたでしょうか?
この記事を参考に、公共政策大学院の研究計画書作成に役立ててくださいね!
具体例をもとに自身の経験や地域課題を取り入れた計画書を作成することで、志望理由に説得力を持たせることができますよ!!
…とはいうものの研究計画書を書くのは正直一人では難しいところがあります。
そういう場合、一人で悶々と悩むよりも1対1大学院合格塾のような専門機関の助けを借りるのも有益です。
ぜひ、今回の内容をあなたの進学対策に役立ててくださいね!

☆研究計画の書き方例はこちら↓
「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!


















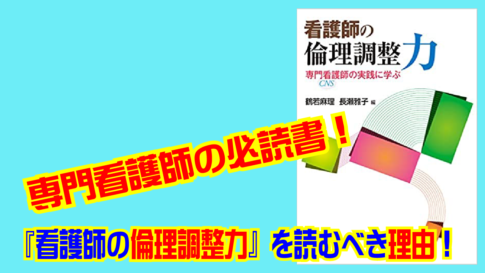


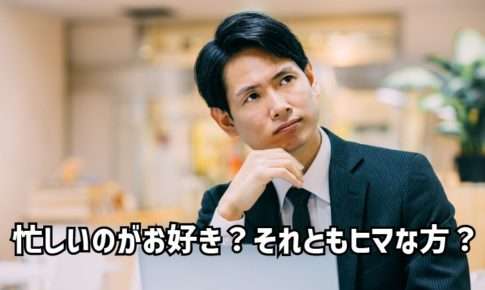






公務員キャリアアップに有効な公共政策大学院受験。
その出願時に必要な研究計画書作成法を徹底解説します!
地域課題や行政経験を活かしたテーマ設定、先行研究の検討、具体的な研究方法まで詳しく紹介!
進学対策にぜひ役立ててください!