目次
現職教員が教職大学院を目指す際の研究計画書の書き方!
「現職教員としてキャリアアップしたい!」
小学校・中学校・高校などの学校教員の方がキャリアアップを目指す場合役立つのが大学院進学です。

通常、大学の学部4年を出た時に取得できるのは「教育職員一種免許状」です。
ですが、教職大学院で所定の単位を取ると卒業時に「教育職員専修免許状」を取得することができます。
教育職員専修免許状はその教科や指導力についての専門性を示す資格となっています。
教員として自身の専門性を高めたり、管理職を目指したりする際に有益です。
さらには教職大学院で学び直すことで自分の自信を高めることもできるのです。
補足1
教職大学院でなくても、大学院で所定の単位を履修することで専修免許状を取得することは可能です。
補足2
教職大学院への進学を目指す現職教員にとって見逃せないのは職場から派遣の形で進学できるケースもあります。
どうやって研究計画書を書けばいいの?
教職大学院を目指そうと思っていても、研究計画書が書けなければ出願する事ができません。
この場合、どうやって出願したらいいか困ってしまう人も多いかもしれません。

研究計画書は自身の教育実践を基にした研究テーマを深めていくことがもとめられます。
そのため、本記事では、現職教員が研究計画書を書く際の具体的なポイントと、研究計画書の例を紹介します!
研究計画書の書き方のポイント!
1. はじめに(研究テーマの設定)
自身の教育現場での課題や経験を基にテーマを選びます。
テーマは具体的でありながら、現場に還元可能なものであることが望まれます。
例えば、「中学生の学習意欲向上を目指したICT活用の実践とその効果」など、実践に根差したテーマを選ぶといいでしょう。
ご自分のこれまでの教職経験を元にするだけでなく、いま教育現場で課題とされている内容に取り組むことがポイントとなります。
テーマを設定した理由を、自身の経験やデータ、教育現場の現状を基に説明します。
具体的な課題や問題意識を明確に示すことで、研究の重要性を伝えます。
2. 先行研究の検討
これまで行われてきた研究を検討し、その研究テーマをご自分が行うべき必然性を示します。
3. 研究方法
どのように研究を進めるかを詳しく記述します。
例えば、以下のような要素を盛り込みます。
- 対象: 調査する学年やクラスの生徒、指導教員など
- 方法: 授業実践、アンケート、インタビュー、授業観察
- 分析: 定性的分析(KJ法やグラウンデッド・セオリーなど)、定量的分析(統計分析など)
4. 倫理的配慮
研究において配慮すべき事項をまとめます。
例えば「◯◯大学大学院の倫理委員会の承認を得る」ことや「調査同意を書面で取る」ことなどを記載するといいでしょう。
5. 期待される成果と意義
研究によって得られる成果が教育現場や学校にどのように貢献するかを示します。
6. スケジュール
研究を進める2年間の計画を具体的に示します。
7. 参考文献
研究計画書作成において参考にした資料や引用した資料を掲載します。

研究計画書の例「中学生の学習意欲を向上させるためのICT機器活用授業の効果に関する研究」
それではここから実際の研究計画書の例を見ていきましょう。
なお、本文に出てくる「◯◯」というのは研究者名が当てはまります。
引用している文献はすべて架空のものですので念の為…。
1. はじめに
現代の中学生は、スマートフォンやタブレットなどICTに慣れ親しんでいる。実際、◯◯(2023)は10年前に比べデジタル端末を使いこなす中学生が増えたことを報告している。しかしながら、学校の授業に対して興味を持てていない中学生も多く存在している。たとえば◯◯(2023)は従来型の授業方法を行う場合、生徒の学習意欲が低下しやすい傾向を指摘している。
そのため本研究ではICT機器を活用した授業が学習意欲にどのような影響を与えるのかを検証し、実践的な教育手法を探ることを目的とする。
2. 先行研究の検討
現状においてICT機器を活用した授業が学習意欲に与える影響についていくつかの研究が出ている。例えば◯◯(2022)はICT機器を用いることで学習意欲が高まったこと、また学習意欲の向上度合いは教科によって異なることを指摘している。
しかしながら、ICT機器を通年にわたって使用することで学習意欲にどのような変化が見られたかについての研究は皆無に近い現状がある。
3. 研究の方法
本研究では授業においてICT機器を活用することが中学生の学習意欲に与える影響を明らかにし、効果的な指導方法を提案することを目的とする。
次のような研究を実施する。
- 調査対象: 中学2年生の1クラス(30名)
- 研究内容: タブレットを用いたICT活用型授業を年間を通じて実施
- 方法: 通年での授業前後で学習意欲や授業満足度についてアンケートを元に調査するほか、授業中の生徒の反応や発言内容を記録したものをカードにまとめKJ法の手法で分析する。
4. 倫理的配慮
本研究を進める際は勤務校の承認を取るほか◯◯大学大学院の倫理委員会の承認を得て行うものとする。
調査で得られたデータは匿名にしたうえで個人情報保護に配慮し厳重に管理をする。
5. 期待される成果
本研究により、中学生の学習意欲向上に寄与する具体的なICT機器活用の方法を明らかにすることができる。これにより、ICT機器を活用した授業方法について、他校でも実践可能な指導モデルを構築することが可能となる。
6. スケジュール
次のような見通しで研究を実施する。
- 修士1年前期: 文献調査および授業計画の立案
- 修士1年8-9月: 授業実践の開始とデータ収集準備
- 修士1年後期: 授業実践の継続とデータ収集
- 修士2年前期: データ分析と結果の整理
- 修士2年8-9月: 論文執筆と結果の発表準備
- 修士2年後期: 論文完成および最終発表
(7)参考文献
◯◯(2022)「 (論文名) 」, 『雑誌名』◯号pp.◯◯-◯◯.
まとめ!型を活かしながら研究計画を書き上げる!
さあ、ここまで研究計画書の例を見てきました。
実際には各大学院によって求められる項目や分量は様々です。
ぜひ今回の内容を参考に、あなたらしい研究計画書を書き上げてくださいね!

「でも一人では難そう…」
そんな方はお気軽に1対大学院合格塾までお問い合わせください。
☆研究計画の書き方例はこちら↓
「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!














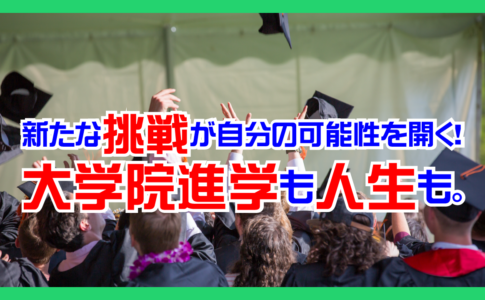
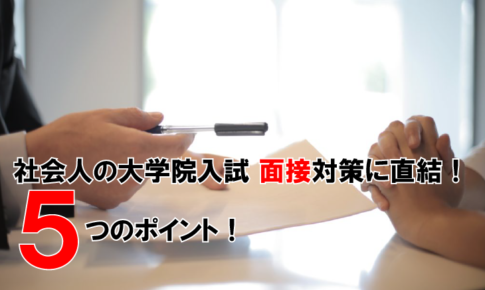



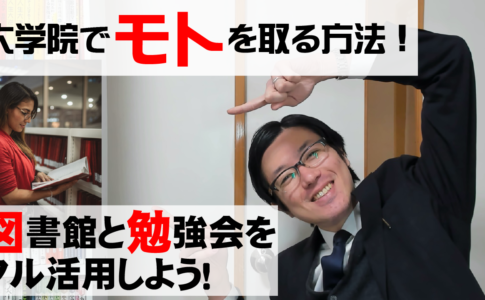








現職教員が教職大学院を目指すための研究計画書の書き方を徹底解説!
テーマ設定や研究方法、先行研究の分析、ICT活用授業の具体例も詳しく紹介します。
教育現場での課題を深掘りし、キャリアアップに役立つ計画書を作成しましょう!