目次
「研究計画書、どう書けばいいの?」と悩んでいませんか?
社会人の大学院入試の「壁」となるのが「研究計画書」。
これをどう書けばいいか、悩ましいところです。
前回はそんな研究計画の書き方を解説しています。
今回からは実際の研究計画書の例を学んでみましょう!
具体例をもとに解説!
ここからは実際にはどのように書いたらいいのか具体例をもとに見てみましょう。
まずはビジネスパーソンの方がMBA(経営管理修士)を目指す際の研究計画の例を見てみます。

MBA(経営管理修士)はビジネスパーソンのキャリアアップにおいて非常に役立つ資格となっています。
ぜひ今回をあなたの進学に役立ててくださいね!!!
なお、今回の研究計画書はあくまで「例」です。
大学院によっては書式の項目が固定されているケースもありますので参考として捉えてください。
ビジネスパーソンがMBAを目指す場合の研究計画の例
ここからは研究計画書を具体的に見ていきましょう。
1. はじめに
ここでは研究テーマの選定と定義を行います。
ビジネスパーソンがMBAに進学する際は、通常、経営戦略、マーケティング、ファイナンス、人材管理など、自身の職業経験に関連する分野をテーマに選ぶことが多いです。
テーマは具体的で解決を目指す価値が明確なものが望ましいといえます。
たとえば、「中小企業における事業承継の支援方法」や「デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進戦略」などが考えられます。
2. 先行研究の分析
ここではテーマで選んだ内容に関する先行研究にどのようなものがあるかを見ていきます。
その先行研究でどこまで分かり、どこまでが分かっていないかを述べたうえで「だからこそ◯◯の研究が必要!」と自身の研究を行う必然性を説明していきましょう。
3. 研究方法
どのような研究手法を用いるかを詳細に記述します。例えば、ケーススタディ、アンケート調査、インタビュー、理論分析など、目的に応じた方法を選びます。データの収集方法や分析手法も具体的に記載します。
4. 倫理的配慮
研究をするうえでの研究対象者への保護を記載します。
研究することが不利益につながらないよう、個人情報をどのように保護するか・調査同意をどのように取るかを書いておきましょう。
(学問によっては倫理的配慮が不要なケースもありますが、医療系ですと必要不可欠です)
5. 期待される成果(予想される結論) or 仮説
研究からどのような成果を期待できるかを記述します。
6. 研究計画
研究活動の開始から終了までのスケジュールをプランニングします。
修士課程2年間の計画を大ざっぱでいいのでまとめておくといいでしょう。
7. 参考文献
既存の研究や文献をどのように参照し、自分の研究にどう活かすかを示します。
研究テーマに関連する重要な文献を選び、その理論をどのように拡張または適用するかを述べます。
可能であれば、自分が学びたい指導教員の論文を引用するのもオススメです。
参考文献の書き方は学問ジャンルによってすべて異なります。
そういう場合、自分が学びたい指導教員が執筆した論文を1つ選び、その先生がどのように参考文献を記載しているかを「真似する」のがオススメです!
研究計画の具体例「中小企業におけるデジタルトランスフォーメーションの推進戦略」
ここからは実際の具体例を考えてみましょう。
なお、本文に出てくる「◯◯」というのは研究者名が当てはまります。
引用している文献はすべて架空のものですので念の為…。

テーマ: 中小企業におけるデジタルトランスフォーメーションの推進戦略
(1)はじめに
近年、デジタル化が企業競争力の源泉となっている。特に中小企業では資源の限られる中で、デジタル技術を如何に活用するかが課題となっている。
その中で近年はデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により資源不足と人材不足を補足する動きが広まっている。◯◯(2024)は中小企業経営者にアンケートを行い、DXを企業の資源不足対策のために用いる企業が7割を超えることを指摘している。
しかしながら、◯◯(2022)は中小企業においてDXの導入が著しく遅れていることを企業の参与観察から明らかにしている。中小企業は日本国内の企業数の大半を占める上、雇用数では7割を占めているため(経産省2024)、中小企業に対するDX導入は極めて重要であるといえる。
(2)先行研究の分析
DX導入については◯◯(2022)や◯◯(2023)が主として大企業に対する調査を行っている。また、◯◯(2022)は企業経営者10人にインタビューをし、DX導入の理由として生産性拡大や人件費高騰への対応が考えられていることを指摘している。
しかしながら、これらは大企業に対する調査であり、現状において中小企業のDX導入についての研究はほとんど存在していない。これは今後の生産性拡大を考えるうえで極めて重要な問題となっている。
したがって本研究ではいままで顧みられていなかった中小企業のDX導入、特に中小企業のDX導入による離職率低下に関し調査を行う。
(3)研究方法
複数の中小企業経営者に対し半構造化インタビュー調査を行い、DX導入に関する考えを調査する。また、すでにDX導入を行っている企業にはその効果をインタビューにより調査し、DX導入が離職率低下につながっているかを検討する。
(4)倫理的配慮
調査に際し、研究協力者には事前に書面で同意を取り、この同意はいつでも撤回できるものとする。
得られたデータは匿名にしたうえで厳重に管理をする。
(5)予想される結論・仮説
本研究により、これまであまり顧みられていなかった中小企業のDX導入に関しての現状把握が可能となる。また、DXの導入が離職率低下につながっているかどうかを実証的に検証することができる。
これはわが国の生産性拡大に於いて極めて重要な示唆であるといえる。
(6)研究計画
以下の計画で行う。
- 修士1年前期: 先行文献の調査および研究計画の具体化
- 修士1年8-9月: アンケート調査およびデータ収集の準備
- 修士1年後期: ケーススタディおよび従業員・経営者へのインタビュー調査
- 修士2年前期: データ分析および研究結果の考察
- 修士2年8-9月: 研究成果の統合と論文執筆開始
- 修士2年後期: 論文執筆の仕上げおよび最終発表準備
(7)参考文献
◯◯(2022)「 (論文名) 」, 『雑誌名』◯号pp.◯◯-◯◯.
まとめ!型を活かしながら研究計画を書き上げる!
さあ、ここまで研究計画書の例を見てきました。
実際には各大学院によって求められる項目や分量は様々です。
ぜひ今回の内容を参考に、あなたらしい研究計画書を書き上げてくださいね!
「でも一人では難そう…」
そんな方はお気軽に1対大学院合格塾までお問い合わせください。
☆研究計画の書き方例はこちら↓
「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!


















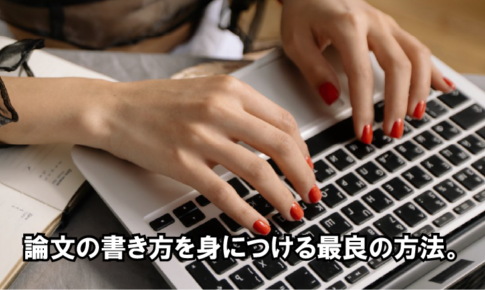
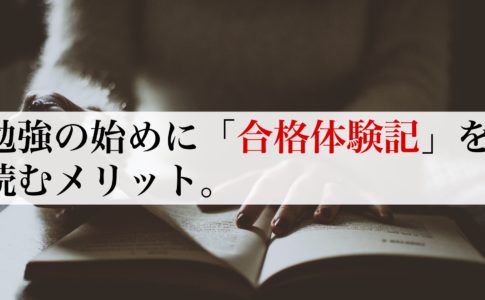




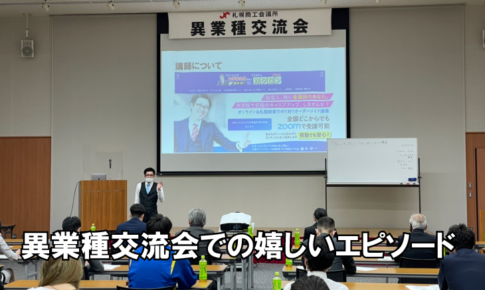






「研究計画書、どう書けばいい?」と悩むあなたへ、MBA進学者向けの具体例と書き方のポイントを解説します!研究テーマの選び方や計画の立て方、参考文献の活用術まで網羅。あなたの大学院進学を全力でサポートします!