イベントを企画するなら
【誰が】【誰に】【何を】【どのように】
【狙いは?】を明確に書き出そう!
「イベントを企画しているんだけど、
なんかうまくまとまらないんだ・・・」
最近、「文章のアドバイスをして欲しい」
というご依頼を多く頂いています。
先日も友人から
「地域の集まりでパネルディスカッションを
行うんだけど、
どうも方向性が決まらなくて困ってるんだ〜」
という相談をもらいました。
中身を聞いてみました。
どうも
「仕事✕やりがい✕夢」
というテーマになる、とのことです。
ただ。
どうも伝えたい事が
「あいまい」なようでした。
企画書を見せてもらいましたが、
企画書にも「悩み」のあとが透けてみえます。

どうも
「どのようにパネルディスカッションをするか」
ばかりを考えるあまり、
「どのようなパネルディスカッションにしたいか」
「何を参加者に伝えたいか」
がハッキリ決まっていないようでした。
つまり、
企画の「目的」が不明確だったのです。
こんなこと、あなたもありませんか?
会社から
「〜〜について企画してよ」
と言われて進めているんだけど、
どうも方向性がハッキリしない。
結果、いくら話し合っても決まらない。
こんなことって、ありますよね。
でも、安心してください。
イベントを企画する際に
「よくある」話なのです。
イベントを通して何を伝えたいかという
「目的」があいまいだと、
結局準備がうまくいかないのです。
そんなわけですので
依頼をしてくれた友人に
次の表を書いて送りました。
①【誰が?】
②【誰に?】
③【何を?】
④【どのように?】
⑤【狙いは?】
5つの質問を送りました。
実はこの5つを埋めていくことが
イベントの「目的」を明確にする
ヒントになるのです。
質問を細かく見ていきましょう。
①【誰が?】:
これはイベント主催者や
イベントのパネリストがどんな人かというところです。
イベントの参加者は
「どんな人が話をするのか」
わからないと行く/行かないを決めることができません。
専門性を示す形で書く方がいいです。
いくつも肩書がある人は
「関係するもの1つ」に絞るといいでしょう。
たとえば私は
「文章アドバイザー」という肩書も
「塾経営者」という肩書もあります。
どちらを出すかは
イベントの種類によって決まってきます。
「作文講座」なら「文章アドバイザー」、
「起業入門講座」なら「塾経営者」が
【誰が?】に示す肩書になります。
友人の依頼の件では、
「いま会社で順調に売上を伸ばしている経営者が」
「かつては仕事がツラかったけど、いまは楽しくなった人が」
などになるでしょう。
②【誰に?】:
これはイベントに来て欲しい人です。
できるだけ明確にすべきなのです。
たとえば友人の依頼の件では
「仕事が楽しくなく、月曜を迎えるのがツラい20代〜30代の若者に」
としてみました。
ダメなのは
「みんな」
「沢山の人」
という書き方です。
「みんなに来て欲しい」
「仕事に興味のある人みんなに来て欲しい」
というのは【誰に?】としては不適切です。
誰を対象にするかが
絞れないからです。
逆に、【誰に?】が明確なら
イベントの文章やイベントのやり方は明確です。
「仕事が楽しくなく、月曜を迎えるのがツラい20代〜30代の若者」が
対象なら、
難しい話や「経営者側の視点」は
全く響かないでしょう。
むしろ
「仕事をちょっと楽しくするためのコツ」
「仕事がちょっと楽しくなる考え方のヒント」を
話してもらえるなら参加しやすくなるはずです。
このように【誰に?】をできるだけ具体的にすると、
③【何を?】と④【どのように?】も明確になるのです。
☆このあたりの流れは
「ペルソナづくり」にも近いです。
こちらもご覧ください。
③【何を?】
④【どのように?】
この2つ、
先程も言ったように
②の【誰に?】が明確なら
勝手に見えてくるのです。
ちなみに③は
「仕事がちょっと楽しくなる考え方のヒントを」
が対象となります。
④が
「仕事が楽しくなったキッカケを語ってもらい、
参加者からの質問にも答えることで」
になります。
ところが、大部分のイベント企画者は
②の【誰に?】を考えず
いきなり③と④を考えてしまいます。
だから何をしたらいいか
わからなくなるのですね。
②さえ明確なら
何をしたら②であげた人に響く企画になるか
勝手に決まってくるのです。
先の友人は初めから
「パネルディスカッションをする」という
④から考え始めていました。

これはあまりよくないことです。
②を明確にする!
そうすると、パネルディスカッションがいいのか、
講演会がいいのか、
それともファシリテーションがいいのか
見えてくるのです。
【誰に?】が明確なら
あとはうまくいくのです!
⑤【狙いは?】
これはイベント全体を通して
参加者に「どうなってほしいか?」考えたものです。
要はイベントを終え、
会場を出る時、
お客さんに「どうなってほしいか?」を
イメージすることです。
友人の依頼の件では
私はこう考えました。
「こうすれば次の月曜日、仕事がもっと楽しくなる!」と実感してもらう
こういう風に明確にすると、
これがそのままキャッチコピーになることも
あります。
このポイントは
「要はこのイベントって、どんなイベントなの?」
というのを一言で答えることです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
イベントを考える際の
5つの質問項目①〜⑤をお伝えしました。
ちなみに。
①〜⑤を続けて読むと
【1つの文章】になるのです!!!
気づかれましたでしょうか?
友人の依頼へ書いた文章
①〜⑤を続けて書いてみましょう。
②「仕事が楽しくなく、月曜を迎えるのがツラい20代〜30代の若者に」
③「仕事がちょっと楽しくなる考え方のヒントを」
④「仕事が楽しくなったキッカケを語ってもらい、
参加者からの質問にも答えることで」
⑤「こうすれば次の月曜日、仕事がもっと楽しくなる!」と実感してもらう
どうでしょう?
①〜⑤、
続けて読むと
「どんなイベントか」がわかるようになりますね!!!
この1つの文章を元にイベントを
組み立てていくとすごくイベントの準備が
やりやすくなるのです。
何かイベントや企画を立てる際は、
②【誰に】
③【何を】
④【どのように】
⑤【狙いは?】
という5つを明確にするようにしてみてください!
ではまた!
☆私の「文章アドバイス」は、
「文章のみ」のアドバイスではありません。
エッセイにしても企画書にしても、
単なる文言を直すのではなく
「そもそも、どういう企画にすればいいか」
というレベルからアドバイスが可能です。
それは私自身が
数限りなくイベントを量産して実施してきたから
可能なのだ、と言えるでしょう。
ある企業さんから「国に提出する提案書」の
赤入れをして欲しい、という依頼があったこともありました。
その時も文言をチェックするだけでなく、
「そもそも先方はどんな提案を欲しがっているか」
などと明確にしています。
こういう「どのように行なうか」「狙いは何か」という
点にも踏み込んだアドバイスを差し上げています〜



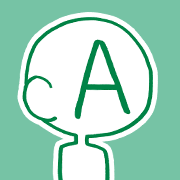

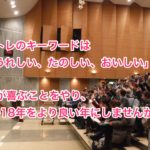
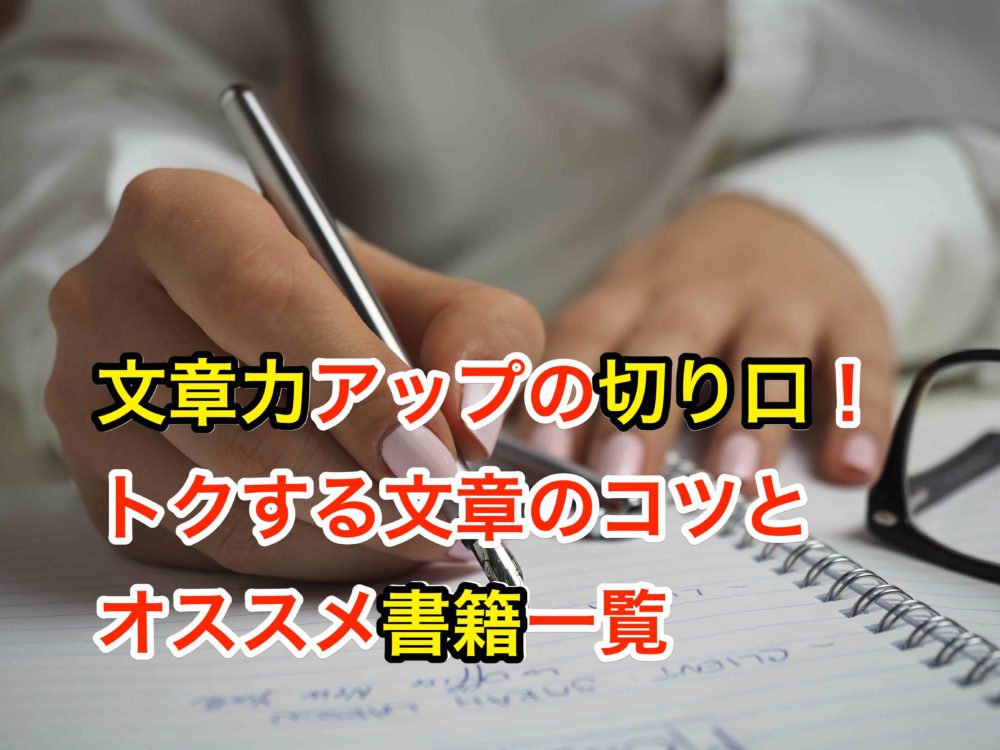


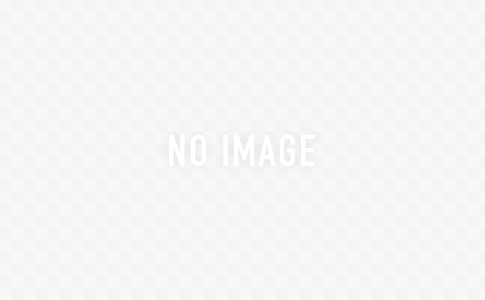
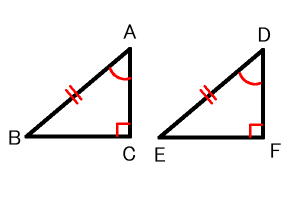
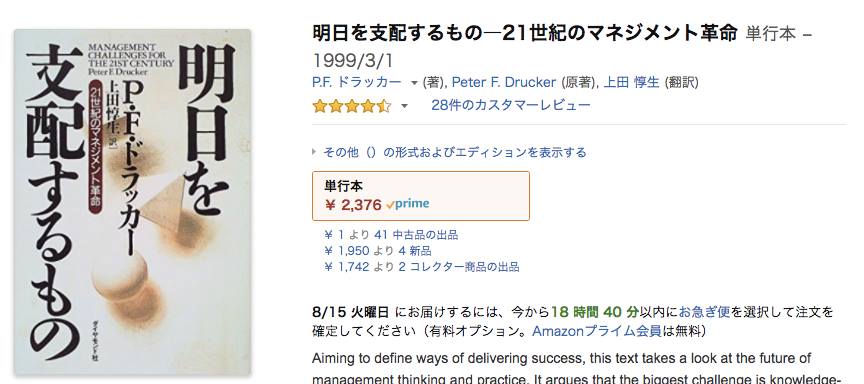






コメントを残す