こんにちは、
文章アドバイザーの
藤本研一です。
作文教室ゆうでは
経営学者・ドラッカーの読書会を
毎月定期的に開催しています。
現在読んでいるのは、
『明日を支配するもの』という、
ドラッカーが21世紀の経済について
予言をしている書です。
これまでに、
2回開催しました。
おかげさまで、
毎回参加人数が増えています。

次回は11/9(木)13:00-15:00に開催します。
希望する方、
ぜひお気軽にご参加ください。
ドラッカー『明日を支配するもの』読書会vol.3
【日時】平成29年11月9日(木)13:00-15
【場所】作文教室ゆう札幌駅前校
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西5丁目6-1
ストーク札幌201
JR札幌駅北口徒歩1分。
☆ヨドバシカメラ様 道向かい。
ミアボッカ札幌駅北口店様 上。
【内容】
ドラッカー『明日を支配するもの』第3章を元にした読書会
・内容の解説
・意見・感想・ディスカッション
お申込み・お問い合わせはこちら、
またはFacebookイベントからどうぞ!
目次
…さて、いよいよ
『明日を支配するもの』読書会も
第3章に入ります。
以下はこの3章のレジュメとなります。
1章のレジュメはこちら。
2章のレジュメはこちら。
本文中の「☆」マーク部分は
私・藤本のコメントです。
第3章 明日を変えるのは誰か(83-107)
☆第3章のメインは
「チェンジ・リーダー」という概念の説明です。
チェンジ・リーダーとは、
「変化を機会としてとらえる者のことである」(82)
つまり、
時代の変化を「チャンス」と捉えられる人のことである。
1 チェンジ・リーダーの条件ーー仕組みと手法(83-)
「チェンジ・リーダーとなるために
必要とされる条件の第一が、
変化を可能にするための
仕組みとしての廃棄である」(83)
「第一の条件は、すでに行っていることの
体系的廃棄である」(83)
→「もはや成果を上げられなくなったものや、
貢献できなくなったものに投入している資源を
引き上げることである」(83)
→「昨日を棄てることなくして、
明日をつくることはできない」(83)
(名言!)
→「この体系的廃棄の第一の段階は、
あらゆることについて、
すでに行っていなかったとして、
今これを始めるかを問うことである。
答えがノーであれば、次に言うべきセリフは、
それでは詳しく検討しようではない。
直ちに行動しようである」(84)
☆ゼロベースで考える。
そして、「選択と集中」を行い、
資源を投下する先を検討する。
☆まずは事業全体から
「無駄」「賞味期限切れ」のものを
削っていくことである。
■ 今までのやり方を変える(86-)
「体系的廃棄の方法は、
行っていること自体の廃棄ではなく、
行ない方の廃棄であることも少なくない」(86)
「体系的廃棄の第二の段階は、
すでに行っている方法の廃棄である」
→別のやり方・方法でやってみる。
■流通チャネルは第一の顧客(88-)
「変化の時代には、流通チャネルほど
早く変わるものはない」(88)。
だからこそ流通チャネルについて
検討していくのが必要である。
「今日の情報革命が
最も大きな影響をもたらす領域が
流通チャネルである」(88)ためだ。
アメリカの大学の例:
入学志望者の流通チャネルは高校の進学担当教師。
でも最近では
雑誌や本で大学についての情報を得るようになっている
(☆いまならネットも)
☆ネットによって、個人がスマホで
発注ができるようになった。
これも流通チャネルである。
☆なぜタイトルに「第一の顧客」と付けているのだろう?
■体系的な作業が必要(90-)
廃棄の手続きは
「体系的な作業として行なう必要がある。
さもなければ、先送りしてしまう」(90)からだ。
そのため「毎月」など
期間を決めて行なう必要がある。
☆個人事業でも、
「やらないこと」を決めたり、
「もう受けないタイプの仕事」を明確化
しておくことも大事であると思う。
そうでないと忙しくて仕方なくなるからだ。
■継続的改善(91-)
「チェンジ・リーダーたるための第二の条件が、
組織的改善、日本語で言うところのカイゼンである。
あらゆる組織が、自らの製品、サービス、
プロセス、マーケティング、アフターサービス、
技術、教育訓練、情報すべてについて、
体系的かつ継続的な改善をはかっていかなればならない」(91)
あらかじめ「年率三パーセント」などと
目標を立てることが必要である。
「成果を改善しようとするのであるならば、
その目的たる成果が
具体的に何を意味するかを
前もって明らかにしておかなければならない」(91)
「継続的改善は、
積み重ねによって、
活動のすべてを根本的に変える。
製品のイノベーションをもたらし、
サービスのイノベーションをもたらす。
プロセスの刷新をもたらし、
事業の刷新をもたらす。
やがて、すべてを根本的に変える」(92)
☆先に「カイゼン」ではないところが重要。
すでにあるものを「廃棄」したあと、
本当にいるものだけを「カイゼン」するのだ。
■成功の追求(92-)
「チェンジ・リーダーたるための
第三の条件が成功の追求である」(92)
「チェンジリーダーたるには、
機会に焦点を合わせなければならない。
問題を餓死させ、
機会を太らせなければならない。
そのためには、ちょっとした工夫でよい。
問題を列挙したこれまでの月例報告の第一ページの前に、
新しい第一ページを加える。
売上にせよ利益にせよ、
予想以上に上がった成果を列挙すれば良い。
そして、問題の検討に投じていたのと
同じだけの時間を、
それらの新しい機会の検討に割くのである」(93)
☆「問題の検討」だけではなく、
「うまくいったことの検討」に時間をかける。
それが「成功の追求」である。
「成功の追求は、継続的改善と同じように、
やがて積み重なって大きなイノベーションとなる」(94)
■イノベーションーー変化の機会を知る
「チェンジ・リーダーたるための
第四の条件がイノベーションである」(95)
「体系的なイノベーションの手法が不可欠である」(95)
「体系的なイノベーションの仕組みを必要とするのは、
イノベーションそのものよりも、
チェンジ・リーダーたらんとする姿勢を
組織中に浸透させるためである」(95)
そのために、
「機会の源泉」とドラッカーが呼ぶ
7つの領域を「体系的に精査していくことが必要」(95)
(1)自らおよび競争相手の予期せぬ成功と失敗
(2)生産、流通におけるプロセス・ギャップ、価値観ギャップ
(3)プロセス・ニーズ
(4)産業構造と市場構造の変化
(5)人工構造の変化
(6)認識の変化
(7)新しい知識の獲得
「イノベーションを追求することに伴うリスクは、
イノベーションを追求しないことによるリスクよりも
はるか小さい」(96)
イノベーションを「日常の仕事」とする。
2 チェンジ・リーダーにとっての三つのタブー(96-)
▼第一のタブー:
「現実と平仄(ひょうそく)の合わないイノベーションを手がけること」
(2章参照)
☆平仄が合わない:つじつまがあわないこと。
「成功するイノベーションは、
先進国における少子化、
支出配分の変化、
コーポレート・ガバナンスの変容、
経済のグローバル競争の激化、
政治の論理との乖離などの
新しい現実と平足の一致するものだけである」(97)
☆社会の「与件」の変化を受け、
新しい状況に対応する方法を出すのがイノベーションである。
▼第二のタブー:
「真のイノベーションと単なる新奇さを混同すること」(97)
→「イノベーションであるか否かは」
「客がそれを欲し、買うことによって決まる」
▼第三のタブー:
「行動と動作を混同することである」(97)
▼この3つのタブーを逃れるには?
「変化の初期段階を階層化すること、
すなわちパイロットすることである」(97)
3 チェンジ・リーダーのための手順と予算(98-)
■小規模にテストする(98-)
「新しいもの、改善したものは、
すべて小規模にテストする必要がある。
つまり、パイロットする必要がある」(99)
→いきなり大きな市場でテストするのでなく、
小さい市場でテストしてみる。
■チェンジ・リーダーのための二つの予算(100)
チェンジ・リーダーに必要な2つの予算
(1)現在の事業のための予算
「事業を継続して行なっていくうえで
最小限必要なものである」
(2)未来のための予算
「全予算の一〇パーセントから二〇パーセント」
「このことは、新しい製品、
サービス、技術への取り組みだけでなく、
市場や顧客や流通チャネルへの働きかけ、
さらには人材教育についてもいえる」(101)
☆グーグルの20%ルールである。
☆「未来のための予算」はこちらも参考にしてください↓
4 継続性との調和(102-)
■変化を目的にする(102-)
「チェンジ・リーダーとして変化を受け入れ、
自ら変化していく」ためには格別の努力が必要。
「チェンジ・リーダーたろうとすることは、
変化を目的とするということである」(102)
そのためには、
・自らの位置を知ること
・共に働く人たちについて知ること
・何を期待してよいかを知ること
・組織が価値とするもの・組織が定めるルールを知ること
が必要。
「何びとといえども、
自らの働く環境を知らず、
理解することができなければ、
いかなる役割りも果たしえない」(102)
組織の継続には「外部との関係においても必要である」(102)
→外部組織について知ることが必要。
「変化と継続は対立するものではない。
二つの極とみるべきものである。
組織は、チェンジ・リーダーになればなるほど、
内外いずれにおいても、
継続性の確立を必要とし、
変化と継続との調和を必要とする」(103)
☆アウトソーシング、クラウドサービスの活用など、
組織の「外部」との関わり方も検討していくべきだ、ということ。
■情報を共有する(104)
「変化と継続の調和のためには、
情報への不断の取り組みが不可欠である。
したがってあらゆる組織が、
いかなる変化についても、
誰に知らせるべきかを考えることを
当然としなければならない」(104)
「不意打ち」をせず、継続的に伝えていく。
☆周りに「伝えていく」のが必要。
「最後に、チェンジ・リーダーたるためには、
変化と継続の調和を、
報酬、認知、評価のシステムによって補完し、
確実にしておかなければならない。
正当に評価されないかぎり、
誰もイノベーションを行なわないことは、
かなり前から明らかである」(105)
5 未来をつくる(105-)
先進国はもちろん、世界全体でも
「根本的な変化が続く時代に入っている」ことは
確実である。
経済・技術だけでなく、
人口・政治・社会・哲学も変化する。
そんな時代だからこそ
「変化を無視し、明日も昨日と同じであるかの
ようなふりをしても無駄」(106)。
「成功への道は、自らの手で
未来をつくることによってのみ開ける」(106)
「自ら未来をつくることにはリスクが伴う。
しかしながら、自ら未来をつくろうとしないほうが、
リスクは大きい」(107)

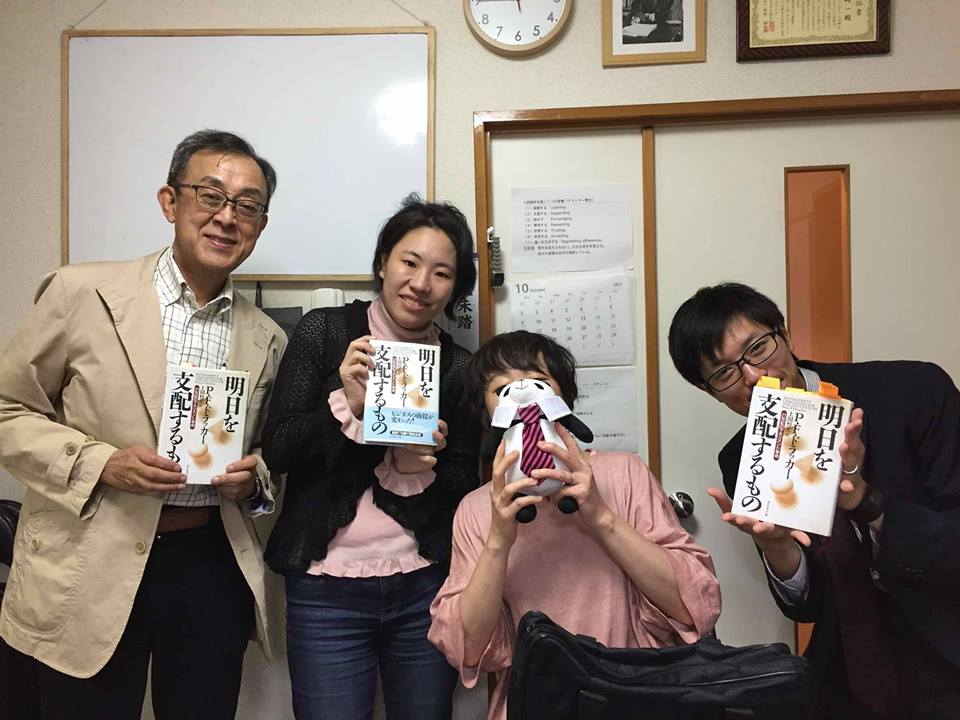



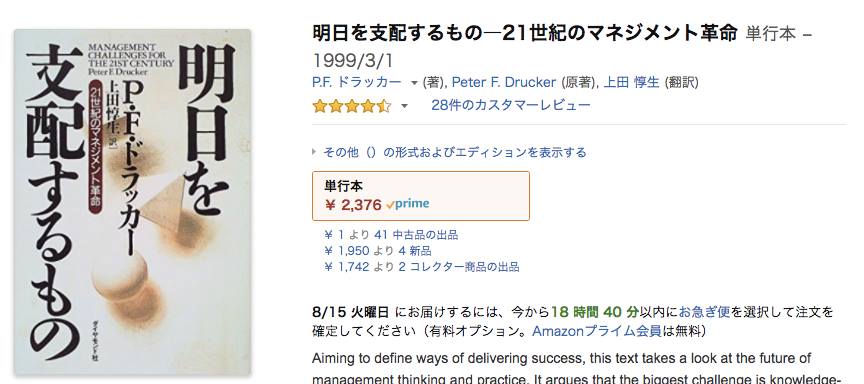
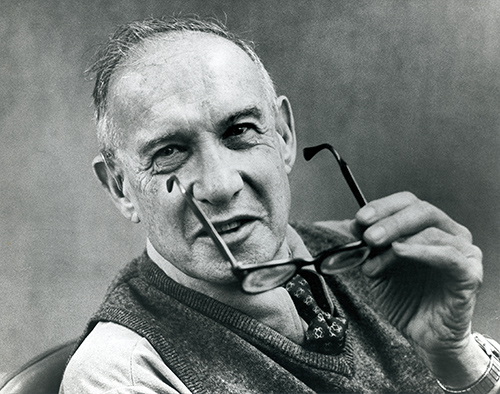
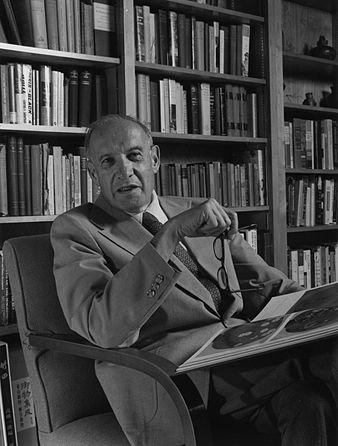





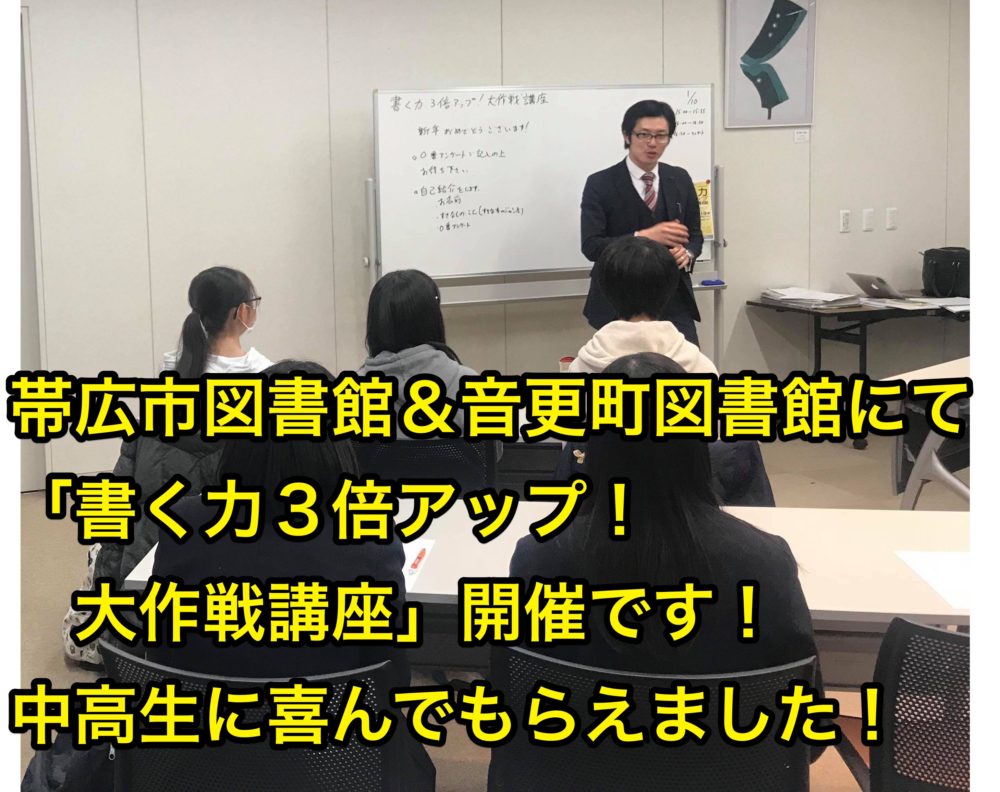
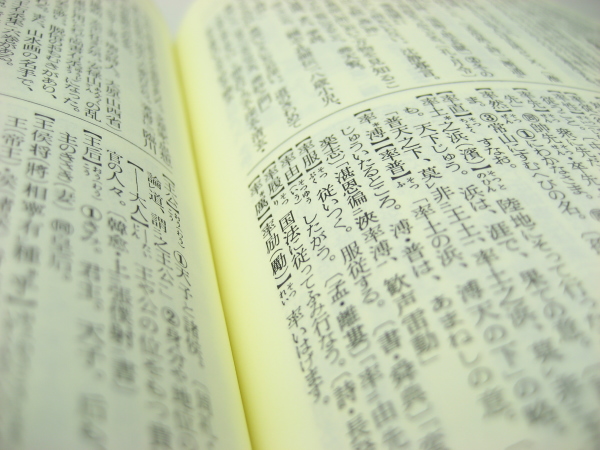
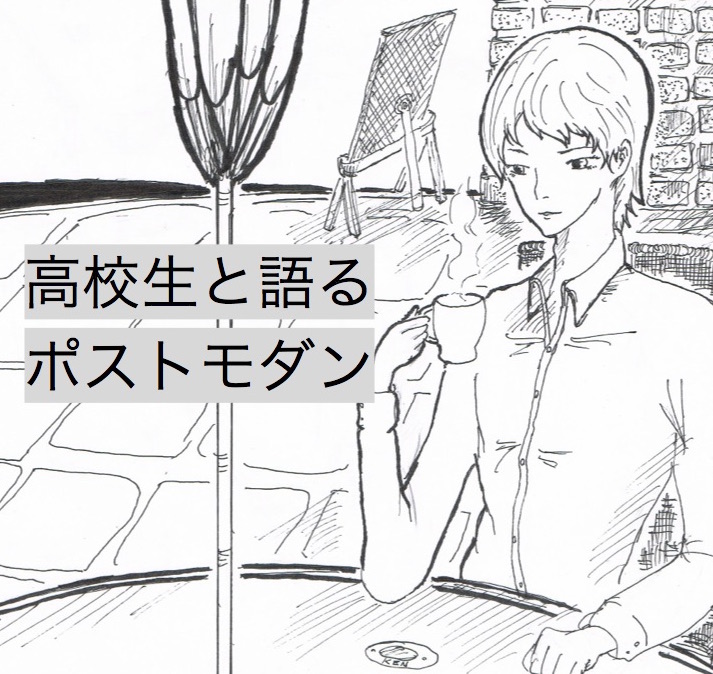
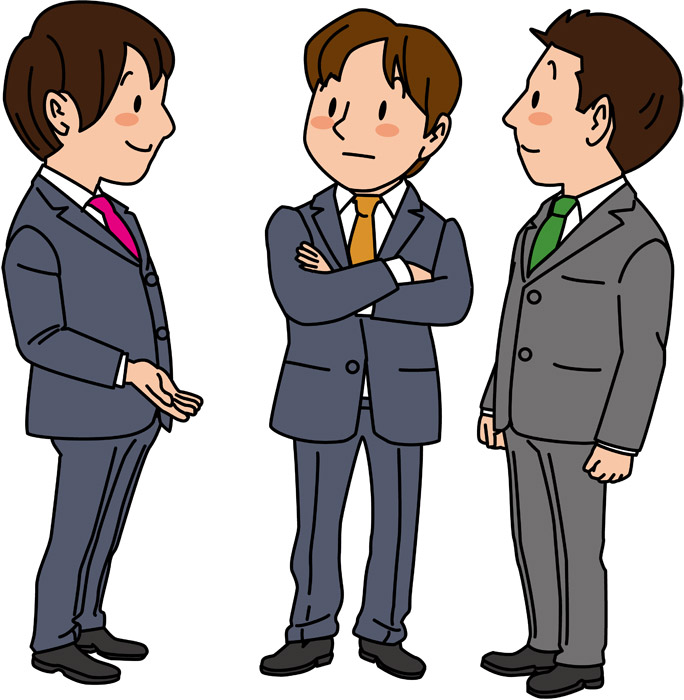
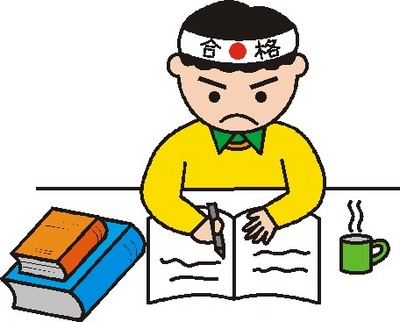

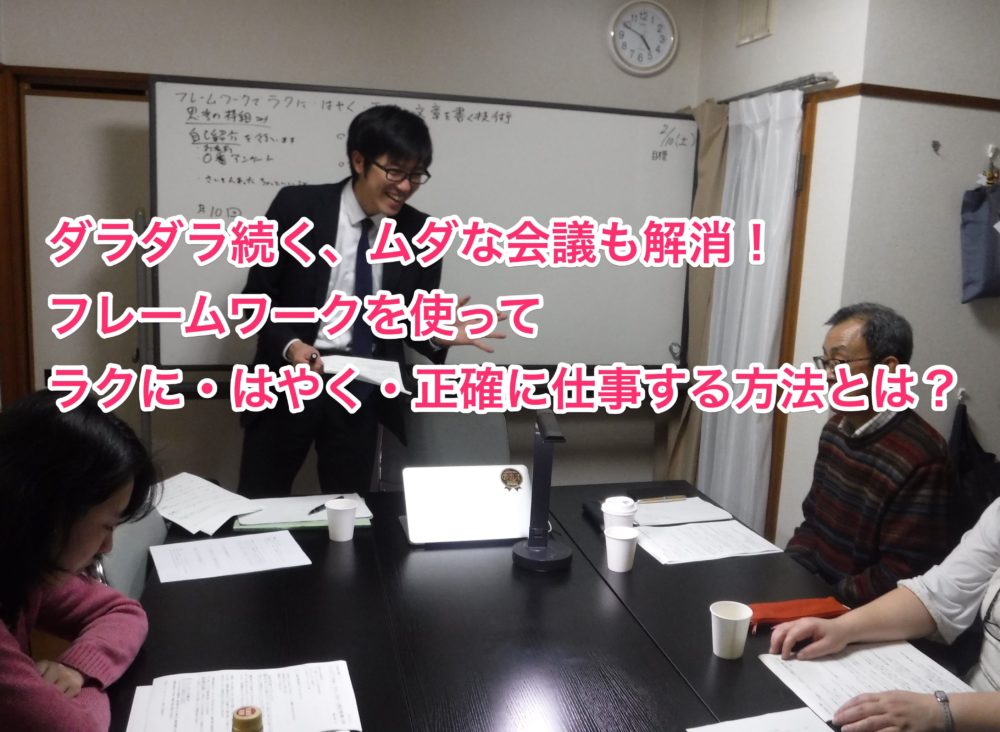







コメントを残す