目次
やる気をどうやって引き出すか?
「どうしてもやる気が出ない…。
どうやったらやる気を引き出せるのだろう…?」
やる気をいかに引き出すか。
これは、キャリアアップを目指す上でとても重要なテーマです。
というのも、キャリアを磨くには、自分の自由時間をどう使うかが大きなカギを握るからです。
たとえば、同じ1時間の自由時間があったとしても、YouTubeをなんとなく見て過ごすのか、あるいは自分の目標に向けてテキストを開き勉強するのかによってその後の成果に大きな差が生まれます。

とはいうものの、空き時間ができたときに勉強したほうが良いとわかってはいても、実際に取り組む気力が湧くかどうかは別問題。
やる気をうまく引き出せるようになりたいと思っている方も多いと思います。
ではどうやったら適切にやる気を引き出せるのでしょうか?
前回の記事では、「モチベーションには内発的なものと外発的なものがある」というお話をしました。
そして、自分の中で勉強に取り組む理由をたくさん増やしていくことがやる気を高める一つの方法になるとご紹介しました。
今回はその発展として、「やる気には5つの種類がある」という視点をご紹介します。
あなた自身の勉強や仕事へのモチベーションを分類・分析することで、自分のやる気の源泉がどこにあるのかを発見できるかもしれません。
ぜひ紙とペンを用意して、実際に取り組んでみてくださいね!
「やる気が出ない…」それ、実は“分類”できるんです!
教育心理学者・外山美樹さんの著書『勉強する気はなぜ起こらないのか』(ちくまプリマー新書)。
この本では、心理学の観点から「やる気」(モチベーション)を内発的動機づけと外発的な動機づけに分けて説明しています。
この分類をさらに分けていくと次のようになります。

(外山美樹,2021, 『勉強する気はなぜ起こらないのか』筑摩書房, 40頁)
やる気は「5つのタイプ」に分けられる!
先ほど示した分類図では、やる気を「内からのやる気」(内発的動機づけ)と「外からのやる気」(外発的動機づけ)に分けています。
外発的動機づけに対しては自律性(自己決定性)の高さに応じて4つに分類しています。
上にいくほど“自分の内面から生まれたやる気”であり、下にいくほど“他者や環境から与えられたやる気”の色合いが増えていきます。

それぞれを見ていきましょう。
① 内からのやる気(内発的動機づけ)
- 面白くて楽しいから
- 新しいことを知りたいから
これは「やりたいからやる」という純粋なやる気。
ゲームに夢中になっている子どもや、興味のある本を読みふける大人などがこの状態です。
やらされているのではなく、「自分からやりたくてやっている」状態です。
集中力も高く、学びが深まります。

大学院進学などのキャリアアップだと、例えば法律の勉強が面白くて仕方ない状態や三国志の時代の研究所を読みふけっている状態などが当てはまります。
② 自己実現のためのやる気(外発的動機づけ)
- 自分の能力を高めたいから
- 知識を得ることで幸せになりたいから
これは「理想の自分に近づくためのやる気」です。
たとえば「将来こんな仕事をしたい」「もっと自信を持てるようになりたい」と思って勉強する人が当てはまります。
内発的な要素も含まれますが、内発的動機づけよりも明確な“目的”があるのが特徴です。

③ 目標によるやる気(外発的動機づけ)
- 自分の夢や目標のために必要だから
- 良い学校に入りたいから
- 資格を取って独立したいから
これは目標や将来の計画に基づくやる気です。
「受験に受かるために今頑張る」といった場合などが該当します。
内面からの動機というよりも、“やらないと達成できない”という認識が力になります。
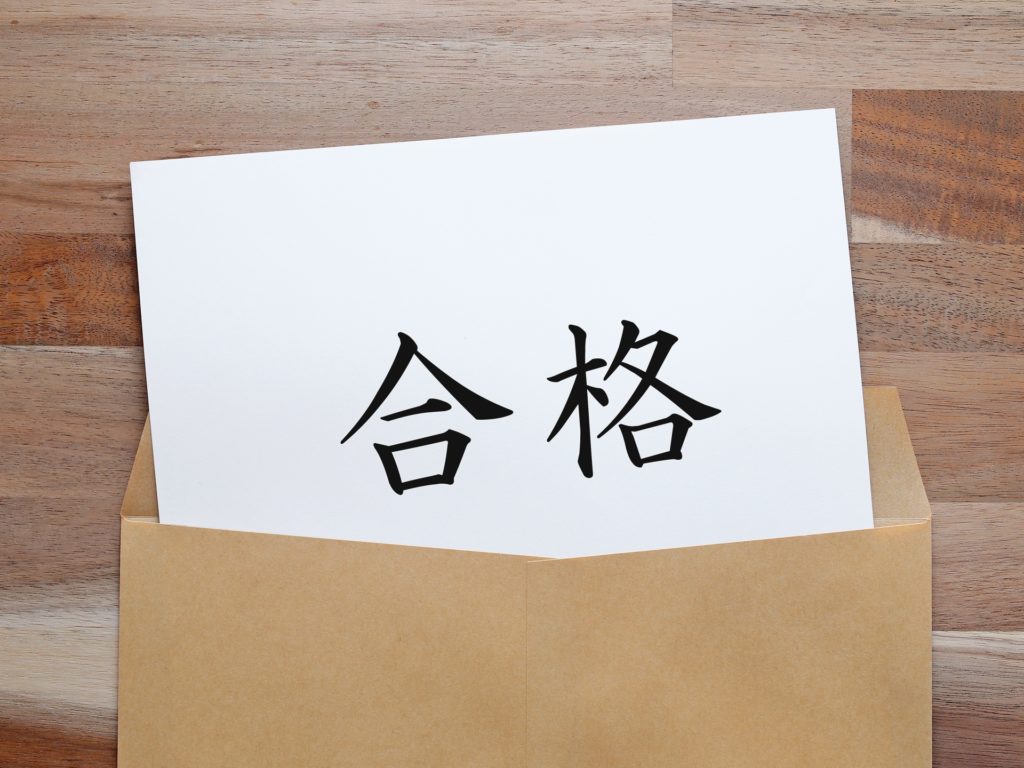
④ プライドによるやる気(外発的動機づけ)
- 勉強できないと恥ずかしいから
- 良い成績をとりたいから
- 最終学歴を大学院卒にしたいから
これは「見られ方」や「プライド」がモチベーションになっている状態です。

周囲と比較して「自分が劣って見られるのが嫌だ」と思うとき、ここからのやる気が出てきます。
一見するとネガティブに思えるところもありますが、他者との「競争」がやる気を引き出す場面も多くあります。
少し視点が異なりますが、「自宅では勉強できないけど、図書館やカフェなら勉強できる」という場合は「他者からの見られ方」を気にする点でこの「④プライドによるやる気」を活用している状態だと言えるでしょう。
⑤ 典型的な外からのやる気(外発的動機づけ)
- 上司や家族に叱られるから
- 上司や家族に褒められるから
- やらないとクビになるから
これはもっとも自律性の低い、外的な圧力や報酬によるやる気です。
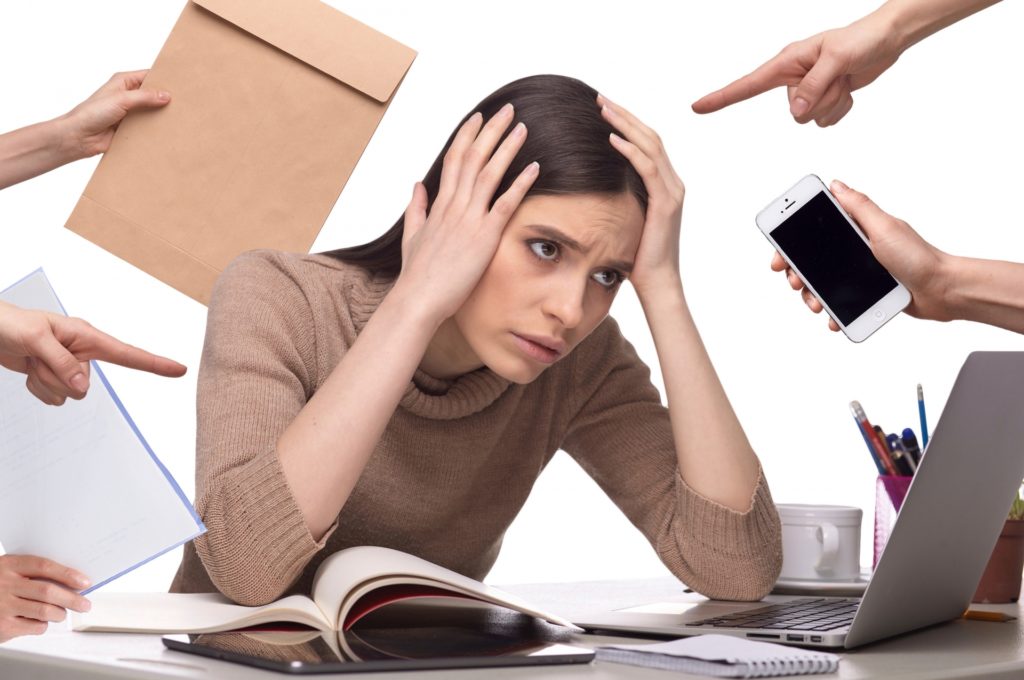
「怒られるのがイヤ」「ご褒美が欲しい」など、条件付きのやる気であると言えます。
「今月中に◯◯を終わらせないとめちゃくちゃ怒られる…!」
こういう思いで勉強・仕事に取り組むことは時折あるかも知れません。
これ、一時的には有効ですが、持続性が低いのが課題とされています。
長期的なやる気にはつながりにくいのです。
どのタイプの「やる気」も使い方次第
こうして見ると、「内からのやる気」や「自己実現のためのやる気」が一番良さそうに思えます。
ですが、実際の話、どのタイプのやる気も悪いわけではありません。
たとえば、最初は「上司・家族に褒められたい」(外発的動機づけ)ことからだったとしても、取り組むうちに「面白い」「もっと知りたい」(内発的動機づけ)に変わることもあります。
私が時折話す内容に「勉強するのが楽しくなったら受かる」「仮に合格できなくてもこれだけ勉強できたのだから悔いはない、と思えたら受かる」というものがあります。
最初は外発的動機づけで始めた勉強が、次第に内発的動機づけに変化していく。
そうなると放っておいても学習が進みますし、自分から進んでやりたい内容に進化していくのです。
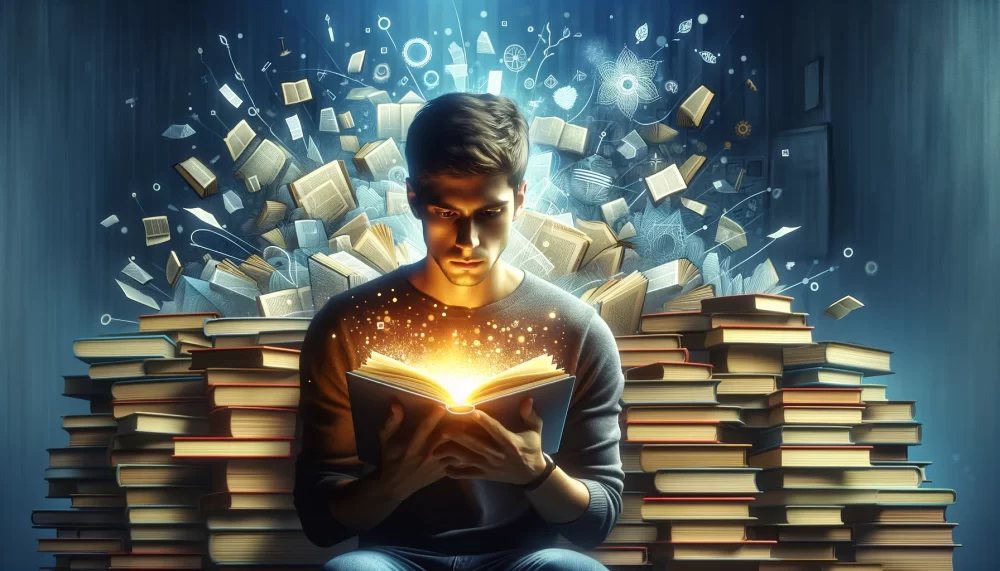
また、「目標によるやる気」や「プライドによるやる気」も、目標達成のためには重要なエンジンです。
ポイントは、自分のやる気の“種類”を理解しておくこと。
「自分が今、どこからのやる気で動いているのか?」「そのやる気が長く続くためには、どうすればいいか?」を意識することで、やる気を上手に育てていくことができるのです。
あなたのやる気、「見える化」しませんか?
おすすめなのは次のようなワークをやってみることです。
【自分のやる気分類ワーク】
- いま取り組んでいることを1つ書く(例:資格の勉強)
- それをやっている理由を3つ以上書き出す
- それぞれがどの「やる気のタイプ」に当てはまるか分類する
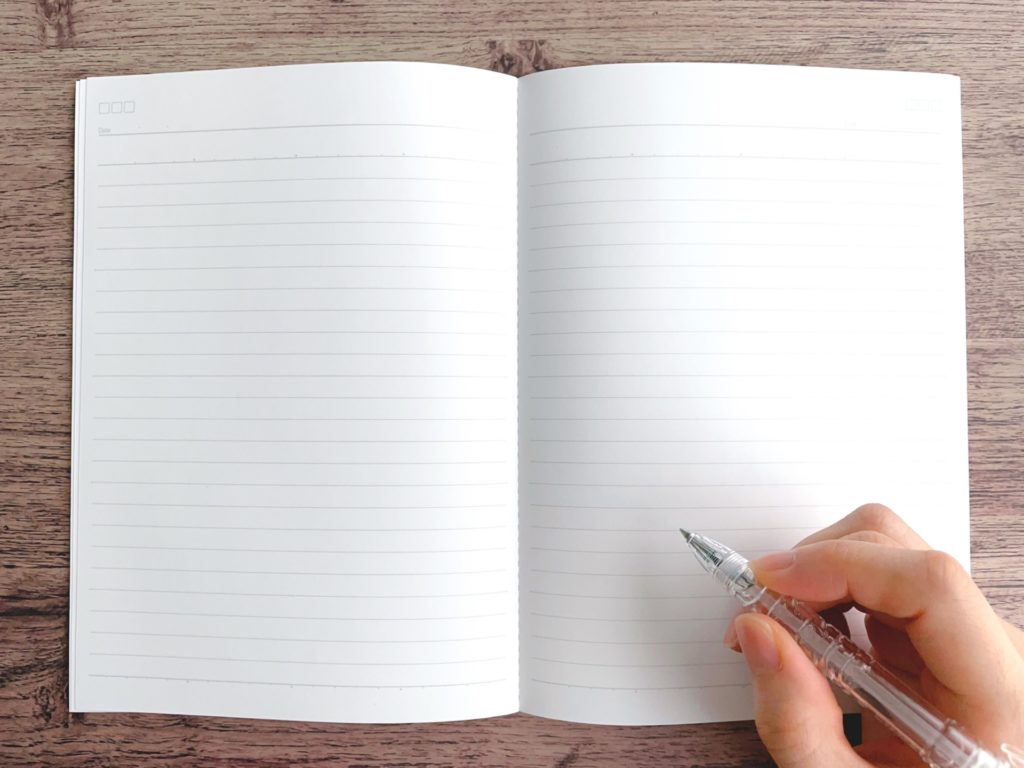
例えば、次のように書いてみると良いかも知れません。
- 「合格したら昇給するから」→ 目標によるやる気
- 「資格の内容が面白いから」→ 内からのやる気(内発的動機づけ)
- 「同僚に負けたくないから」→ プライドによるやる気
こうやって可視化してみると、「自分はこんなにもいろんなやる気で動いてるんだな」と気づけるはずです。
自分のやる気の背景をこうやって書き出していくと、自分のやる気をどう引き出すか方向性が見えてくるはずです。
まとめ!やる気は“自分で組み立てられるもの”
やる気が出ない日もあれば、やる気に満ちる日もある。
それは当たり前のことです。
大事なのは自分のやる気の“出どころ”がどこかを知っておくこと。
そうすれば、いざというときにもやる気を引き出しやすくなるのです。
ぜひ、内からも、外からも、たくさんの「やる気」を引き出せるよう、一度自分のやる気の出どころを書き出してみましょう!
やる気は“急に湧いてくるもの”ではなく、“自分で引き出していくもの”でもあります。
自分のやる気を正しくコントロールしていきましょう!

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!
























やる気が出ない…そんなときは、自分の「やる気のタイプ」を見える化してみましょう。『勉強する気はなぜ起こらないのか』ではやる気を「内からのやる気・自己実現のためのやる気・目標によるやる気・プライドによるやる気・典型的な外からのやる気」の5つに分類しています。自分が勉強・仕事する理由はこの項目のどこに当てはまるか考えてみるとやる気を引き出しやすくなりますよ!