目次
ノートの取り方で結果は180度変わる!
「ノートを取る」。
講義や研修の際にノートをまとめることって多いです。

他にも専門職の方ですと「技術ノート」などの形で自身の専門性をノートにまとめることもあります。
ノートを取る機会は、学生時代に限らず、社会人になってからも多くあるのです。
では、あなたはどんな意識でノートを取っていますか?
中には「自分がわかればそれでいい」と思って取っている人もいるかも知れません。
ですがこれって、あまり効果が上がりません。
実は、「人に見せる前提でノートを取る」ことが、学びの質をぐっと高めてくれる方法なのです。
今回は、大学院での学びや日々の業務メモにも使える、「人に伝えるつもりでノートを取る」ことの重要性をお伝えします!

なぜ「人に見せる前提」でノートを取るのが良いのか?
ノートを取るとき、ついつい「自分にだけわかれば良い」と考えてしまいがちです。
中には自分が知っていることはノートに取らず、いまの自分に必要なことだけしかノートに取らないケースもあります。
これ、合理的なようでいてちょっと「もったいない」ことだと言えます。
それは「いま必要なことだけノートに書こう」と思っていると、話をきちんと聞けなくなってしまうからです。
大事なのは「講師は何を言おうとしているのか」「研修はどのように行われたのか」を正しく記録するつもりでまとめてみること。
いうならば「人に見せる前提でノートを取る」ことが良いノートをまとめるポイントなのです。
この意識になると、「聞き漏らさずノートにまとめよう」と主体的になります。
人に見せるつもりでノートを取ることで、自然と「わかりやすくまとめよう」と意識するようになるのです。
結果、講義の理解度も上がりますし、付随的な話ですが「研修報告」などを会社に出すのもスムーズになります。
大学院の授業ですと授業の課題レポートをまとめるのも楽にできるようになるのです。

わかりやすくまとめるには?
人に見せる前提でノートを取る場合、必然的にノートに情報を自分で追加していくことも求められます。
単に講師が話している内容ではなく、講義内容の全体や背景にあることも自分で書き添えていくことが必要なのです。
他にも、講義に出てきた用語の意味を簡単に追加したり、因果関係や背景を図解で示したり、
話の要点・構造を整理して記録したりする工夫を自然に行うようになります。
他の人が読んでもわかるノートにしようと工夫することで、自分自身の理解も深まるのです。

逆に、自分だけがわかればいいと思っていると、
「知ってるからメモしなくていいや」
「この部分は省略しておこう」
といった意識が働き、重要なポイントを見落としてしまうこともあります。
他人に伝えようとする視点を持つことで、内容の整理、前提の確認、論理的な構成を意識することになります。
結果的には、「人に見せる前提」でノートを取ることが学びの質を高めてくれるのです。
(なお、ここでお話しているのはあくまで「人に見せる前提」を考えるということであり、実際に誰かに見せなければならないというわけではありませんので念の為)
かつての「ノート」は教材だった
この「人に見せる前提でノートを取る」という姿勢、実は歴史的にも大切にされてきました。
たとえば、明治時代の大学教育では教科書や参考書が非常に貴重でした。
特に海外の最先端の知識をまとめたテキスト自体が貴重だったため、講義の中で話される内容をまとめたノートがそのまま貴重な参考書となったのです。
そのため、講義の内容を記録し、それを「他人が読んでも理解できるようにまとめる」ことが、学習の一環だったのです。
講義をまとめたノート(講義録)はそのまま教科書になりえていたのです。
(戦前の早稲田大学では、授業の内容を話した「講義録」が実際に大学教材として販売されていました)
中世ヨーロッパでも、修道院や大学では教員の話をノートに記録して後で読み返し学ぶというスタイルは中心的なものでした。
つまり、ノートとはもともと他の人が読んでもわかるように講義の内容をまとめるために会ったのです。
自分だけでなく「他の人が読んでもわかるようにまとめる」のが本来の役割だったのです。
「自分だけがわかるノート」の落とし穴
私自身も大学生の頃、あとから講義内容を再現できるよう、教員の話を「書き漏らさない」ことに必死でした。
字は綺麗とは言えませんでしたが、「後で読んだとき講義内容を思い出せる」内容となっていました。
すでに自分が知っていることも、「他の人が読んでもわかる」ようにまとめていたのが懐かしいです。
こうやって書き漏らさずまとめたノートが、自分にとって最高の復習教材になったのです。
逆に、「自分の知っている部分だけをメモする」「新しい情報だけを書き留める」というやり方では、ノートの内容が断片的になりがちだったと思います。
結果、後から見返しても理解が難しくなってしまうのです。
東大合格者のノートに学ぶ「美しさ」の意味
かつて、『東大合格者のノートはかならず美しい』という本が流行りました。

☆太田あや『東大合格生のノートはかならず美しい』の詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/450AT8B
この本では、東大合格者のノートが「見やすい」「整理されている」「論理が明確」といった点で優れていることが紹介されました。
それは彼らが特別に字が上手いというよりも、他の人が読んでもわかるように書くことを意識しているからこそ生まれる美しさなのです。
他の人が読んでも理解できるいノートは、わかりやすいノートです。
わかりやすいノートは、論理的に整理されたノートです。
つまり、他者を意識することで論理力が磨かれていくのです。
手書きとパソコン、どちらでも応用できる考え方
さて、現代の大学・大学院では、パソコンでノートを取る人も増えています。
私も、いま北大大学院に通っていますが、基本的にはノートPC上でノートを取っています。
学生時代は手書きでしたが、いまのノートPCにおいても「他の人が読んでも理解できるように書く」という意識を大事にしています。

(私の手書き文字はけっこう読みづらいので、ノートPCで取るほうが他に人にも読んでもらいやすいように感じています)
手書きでもPC入力でも、自分だけにわかるノートではなく、他人にわかるノートを目指すと、学びが定着しやすくなるのでおおすすめです!
ノートの最後に「一言まとめ」を!
なお、ノートの取り方には1点ポイントがあります。
それはノートを取ったあと「一言まとめ」をノートの上部または下部に書いておくことです。
「今日の講義で、私が一番大事だと思ったことは何か?」
「この授業から得られた教訓は何だったか?」
こうした問いを立てて、一文でまとめる習慣をつけるのがおすすめです!
そうすると、自分の理解を言語化するトレーニングになります。
後で復習する際も「どういう授業だったのか」が一度で思い出せるのでとても有益です。
これを日常的に行っていると、大学院のレポートや発表の準備、さらには仕事での報告書作成にも役立つはずですよ!

(ロジカルシンキングの手法でもあります)
まとめ!ノートは「学びの鏡」
ノートはただの記録ではなく、学びを支える重要なアイテムです。
自分の理解度、論理力、思考の整理力、他者への伝達力…。
ノートには、それらがすべて表れてしまいます。
だからこそ、ノートを「人に見せる前提で」取る習慣をつけてみませんか?
・内容を整理しながら
・背景や前提を踏まえながら
・誰かに教えるつもりで
そうすることで、きっとあなたのノートは「伝わるノート」に変わります。
学びを深めたい、アウトプット力を高めたい、そう思ったときには、まずノートの取り方から見直してみるのも一つの手です。
ノートを変えれば、学びも変わります。
ぜひ、「人に見せたくなるノート」を目指してみませんか?
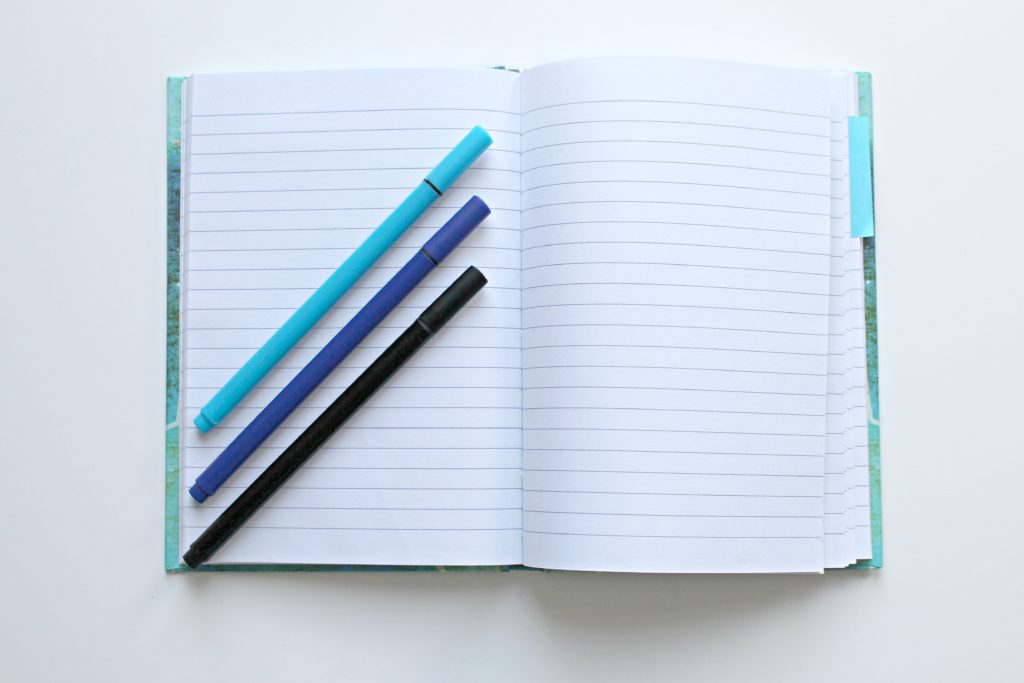
「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!










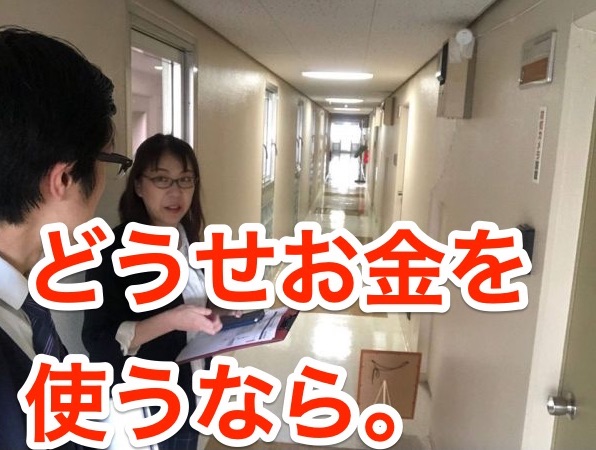
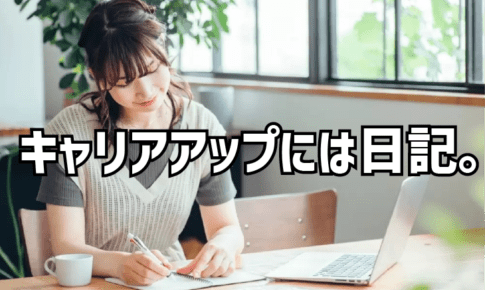
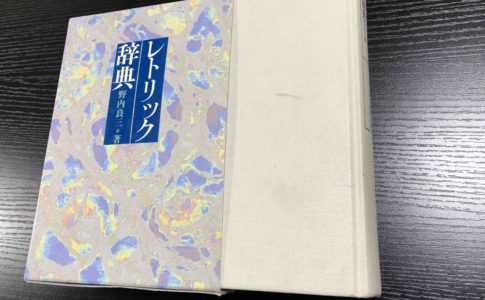
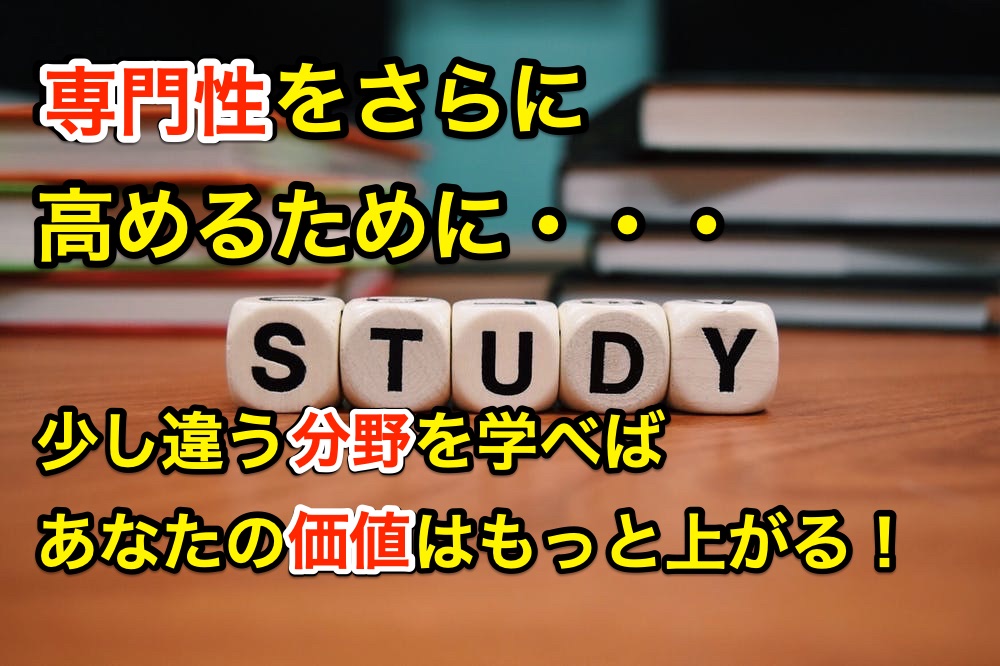
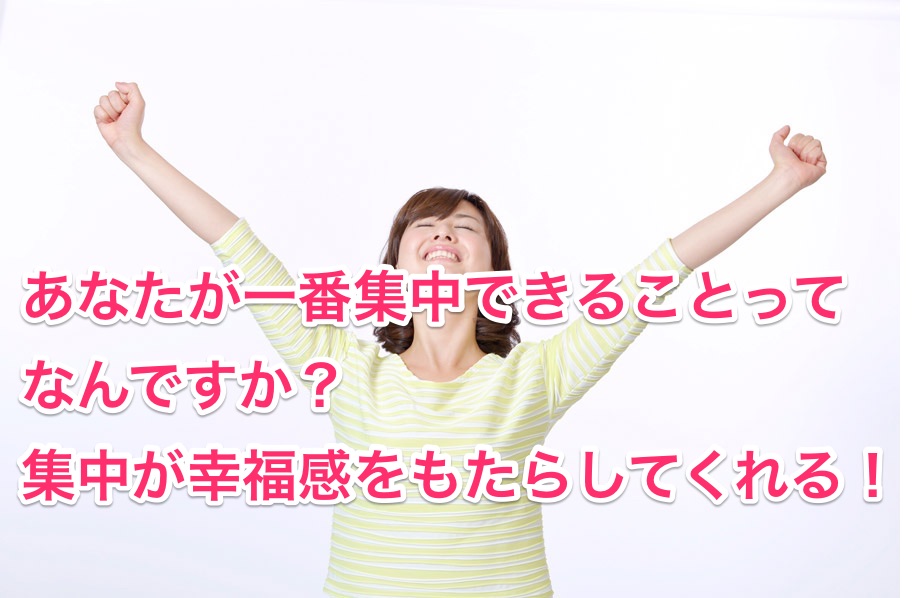









ノートってついつい自分にだけわかるように書いてしまいがち。ですが「人に見せる前提」で取ると、理解が深まり論理的に整理されます。聞き漏らしもなくなるので効果的。ぜひ大学院の授業ノート、人に見せる前提で書いていきましょう!学びの質もぐっと高まりますよ!