目次
仕事と勉強の両立をどう実現するか?
大学院への進学を考える社会人の方にとって、「仕事と勉強の両立」は大きな課題です。
社会人が大学院に進学するとキャリアアップに直結しますが、いかんせん通学と仕事の両立がけっこう大変なのです。
修士課程で学習をする場合、毎週8〜10コマ(1コマ90分)の授業を取る必要があります。
8コマ×90分なので週12時間の授業を受けるだけでなく、それ以外に課題レポートなどがけっこうあります。

これだけの時間を捻出するのって、人によっては相当大変かもしれません。
私自身も現在、北海道大学の公共政策大学院に在学中ですが、日々の仕事と授業、研究とのバランスに悩むことは少なくありません。
そんな中、大きな力になるのが「長期履修制度」です。
これは通常2年間の修士課程を、同じ学費で3〜4年に学習期間を延長できる制度となっています。
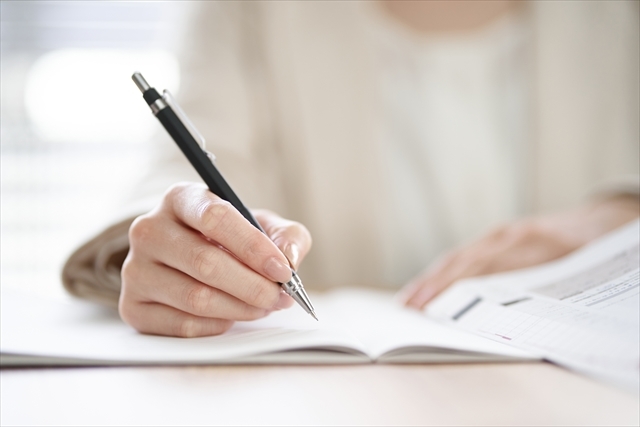
この記事では、社会人にとって非常に便利な「長期履修制度」の仕組みと活用のポイント、注意点などをお伝えします。
「大学院に通いたいけど、時間が取れない…」という方は、ぜひ参考にしてみてください!
長期履修制度とは?社会人にとってのメリット
「長期履修制度」とは、標準修業年限(通常2年)を超えて3年〜4年かけて履修することが認められる制度です。
最大のポイントは、学費が2年分で済むこと。
時間はかけても費用面での負担が増えないのが特徴です。
私もこの制度を利用して、北大の公共政策大学院に通っています。
通常、週に8〜10コマの授業を履修しなければいけないところを、長期履修制度のおかげで週3〜4コマに抑えることができ、無理なく学びを継続できています。
特に仕事をしながら大学院に通う社会人にとってはかなりの恩恵がある制度だと感じています。

すべての大学院で使えるわけではない!?要注意ポイント
便利な長期履修制度ですが、すべての大学院で利用できるとは限らないという点には注意が必要です。
実際、私自身も進学前には「どの大学院でも当然使える制度」と思っていたのですが、調べていく中で、制度が整っていない大学院も意外と多いということがわかりました。
特に、社会人学生が多いにもかかわらず、長期履修制度が使えない大学院も存在しています。
これは非常にもったいないですよね。
(なんとか改訂してほしいなあ、と思います)
入学してから「長期履修制度が使えないんだ…」と気づくと損してしまいますので、入学前に確認してみるのをおすすめします!
まずは興味のある大学院の事務局に電話などで直接問い合わせて見てください。

「長期履修制度」と「在籍可能年数」は別物です!
ここで混同しやすいのが、「長期履修制度」と「在籍可能年数」という2つの概念です。
長期履修制度を使わなくても修士課程に3〜4年在籍することはできます(在籍可能年数)。
ですが、この場合は単に「留年」のような扱いになるため学費が発生します。
大学院によっては長期履修制度の説明なく在籍可能年数のみが書かれているケースが有り、時折誤解してしまうケースがあるのです。
両者をまとめると次のようになります。
- 長期履修制度:申請を行うことで、2年分の学費で3〜4年かけて履修できる制度。
授業の履修計画を調整しながら、無理なく卒業を目指せる。 - 在籍可能年数:制度の申請とは関係なく、大学院に在籍できる最大年数。
多くの大学院では4年程度が上限。
つまり、長期履修制度を使わないまま3年目、4年目に在籍を続けると、追加で学費が発生します。
「在籍できる=お得に通える」わけではないので要注意です。

通えない時は「休学制度」も検討を!
長期履修制度が使えないケース以外にも、途中で仕事や家族の都合で通学が厳しくなるケースも考えられます。
そういう場合、安易に退学するのはもったいないです。
せっかく入学金や学費を支払っている以上、安易に辞めてしまうのはもったいないのです。

そうではなく、まずは休学制度を活用するのがおすすめです!
大学院によっては、半年単位や1年単位での休学が可能です。
やむを得ない事情で通えない時期がある場合、無理に在籍を続けても学費をムダにするだけです。
であれば休学制度を使って時間をあけるほうが有益であると言えます。
休学から復学という再スタートを切ることで学びの質もモチベーションも高く保つことができます。
途中から長期履修に切り替えることはできる?
なお、大学院によっては、入学後に長期履修制度へ切り替えることが可能な場合もあります。
私の通う公共政策大学院でも、社会人であれば通常の2年履修を途中から3年・4年へ切り替えられるようです。
(3年の長期履修制度を4年に変更することも可能なようです)

ですが、その逆、つまり「長期履修で入学したけど、やっぱり2年で卒業したい」と途中から短縮するのは難しい場合が多いようです。
なので入学時に慎重に計画を立てておきましょう!
長期履修制度の活用がキャリアにもつながる!
長期履修制度を活用すれば、仕事を続けながら、無理なく、そしてしっかりとした内容の学びを得ることができます。
研究テーマにじっくり取り組める時間も増え、学びの質が向上するだけでなく、将来的なキャリアアップにもつながる力を身につけることができます。
「どうせ通えないから大学院は無理だ」とあきらめる前に、このような制度を調べ、自分にとって最適な学び方を見つける工夫をしてみましょう!
お金の捻出も楽になる!
長期履修制度は学費捻出の点でも有益です。
それは一気に学費を払うのが大変でも、長期履修制度を使うことで結果的に「2年分の学費を4年かかけて払う」ことになるからです。
1年の学費は国立大学の大学院では通常約53万円です。
通常であれば半期に1度ずつ半分の納付になるので4月・9月あたりにそれぞれ約26.5万円ずつ支払うことになります。
(入学時は入学金約30万円も同時に支払いが必要になります)
一方、長期履修制度で4年かけて通う場合、半期に一度の納付分がさらに半額になり約13.3万円ずつの支払いとなります。
一気に年53万円支払うのは大変でも、長期履修であれば年26.5万円支払うだけで済むので経済的にもラクになるといえるでしょう。
(ただし、長期履修制度を使う場合は「教育訓練給付制度」が使用できない点にはご注意ください)
☆こちらもご覧ください→「働きながら大学院進学を実現する5つの方法。使える制度を知り、仕事を辞めずに進学しませんか?」https://school-edu.net/archives/36381
まとめ!
まとめますと、長期履修制度は社会人の強い味方となり得る制度だと言えます。
大学院によっては使えないこともあるので事前のチェックは必要ですが、使えるのであればどんどん使っていくといいですね!
(長期履修制度だと学割が使える期間も長くなりますし)
最後に、もう一度ポイントをまとめておきます↓
- 長期履修制度は、学費を2年分に抑えつつ3〜4年かけて通える制度。
社会人が無理なく大学院で学ぶための強い味方となる - すべての大学院で使えるわけではないので、制度の有無は事前に要確認。
在籍可能年数との違いにも注意が必要。 - 通学が難しい場合は休学制度の活用も視野に入れる。
- 制度の活用が研究やキャリア形成にも良い影響を与える。
長期履修制度を使うことで「大学院で学びたい」という気持ちを実現しやすくなります。
社会人にとっては、時間もお金も限られているからこそ、こうした制度を知っているかどうかが大きな分かれ道になることでしょう。
ぜひ、あなた自身にとってベストな学び方を見つけ、大学院での学びを実りあるものにしてくださいね!

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!
























社会人が仕事と勉強を両立させるための強い味方が「長期履修制度」です。この制度は2年の学費で3〜4年かけて修了できる制度です。ただし制度が使えない大学院もあるので事前に制度の有無を確認し、無理なくキャリアアップを目指しましょう。