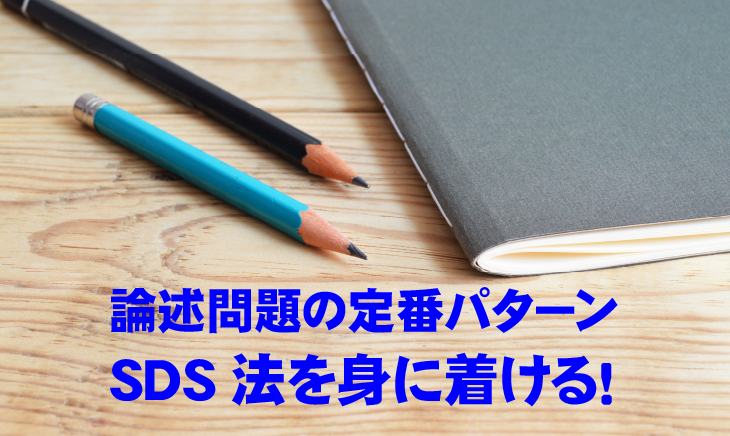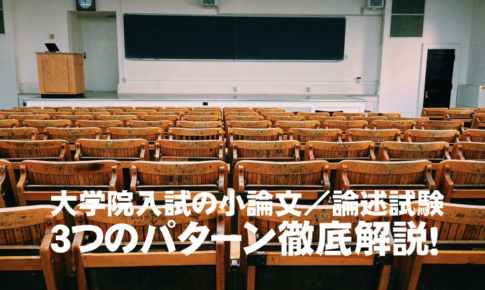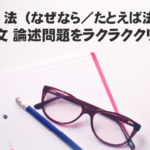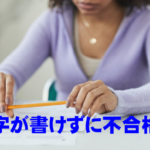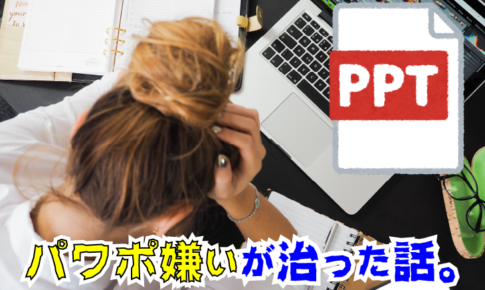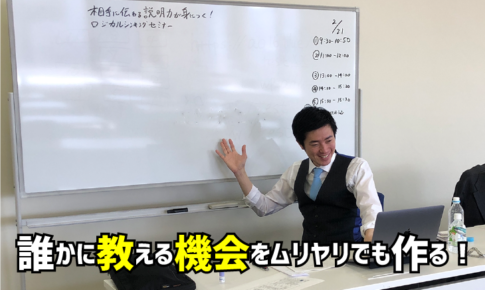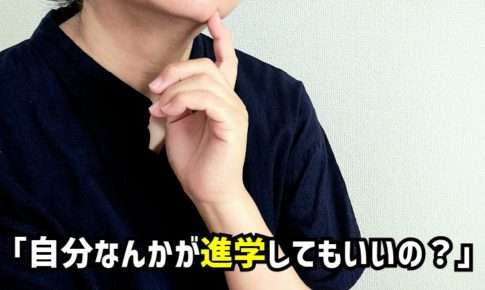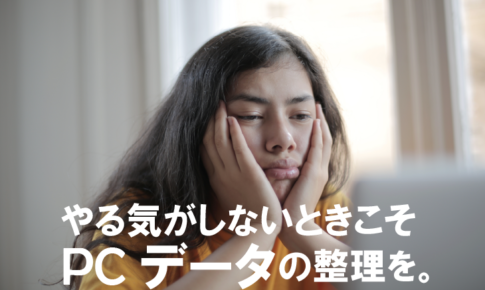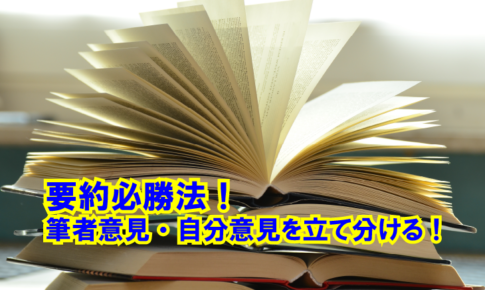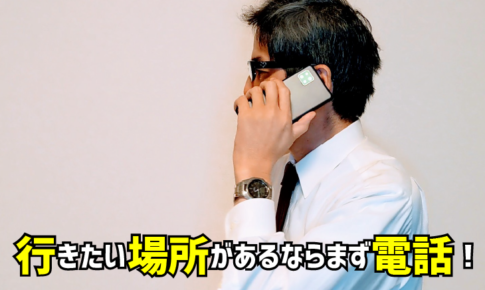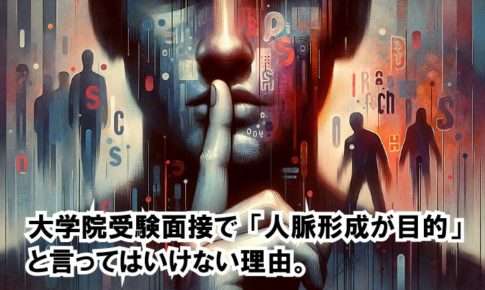短い字数での論述試験に効力を発揮する!
SDS法を身に着けよう!
「大学院進学って、
どうやって進めればいいの…?」
そんなお悩みにお応えするシリーズ
第11弾(小論文/論述問題対策 編vol.4)。
今回もお届けします!
適当に書くとグダグダに…。
今回は小論文/論述試験問題の
具体的な解き方です。

小論文や論述試験において、
原稿用紙を前に考え込む人は多いです。
「どうしよう、
どの順番で原稿を書いたらいいか、
よくわからない…」
こういうふうに、
どのように論述をしたらいいか悩む人が多いです。
小論文試験では
【800~1,200文字】で
回答が求められることもあります。
この字数、
「適当」に書いてしまうと
ぐちゃぐちゃになります。
その上、
いきあたりばったり式で書くと
字数を埋めることもできません。
空白が目立つ「書けなすぎ」な原稿だと、
そもそも採点されないことすらありえます。
(注 小論文/論述試験の場合、
指定された字数の【9割】程度で書ければベスト、
と言われています。
たとえば【1,000文字以内】で答える問題には
【900文字以上1,000文字以内】で答える必要があります。
なお、文字数の上限が決まっている場合は
1文字でもオーバーすると不合格となるケースもあります。
「書けなすぎ」同様に「書きすぎ」にも注意しましょう)
「回答の基本のパターン」を知るのが合格のカギ。
さて、こういう小論文/論述試験で
規程の文字数でピタッと回答するには
どうしたらいいのでしょうか?
それには次に示す
【回答基本のパターン】を身につけるのが
一番の近道です。
基本のパターン1)SDS法(結論サンドイッチ法)
最初に紹介するのは
SDS(エスディーエス)法です。
SDSとは
Summary(サマリー:まとめ・結論)
Detail (ディティール:詳細・具体的説明)
Summary(サマリー:まとめ・結論)
の頭文字を示したものです。
文章のはじめに
一言で「結論」を示し、
その後その詳細説明を追加し、
最後に再び「結論」で締める、
という方法です。
詳細(具体的説明)を
「結論」と「結論」でサンドイッチする。
その点から
私はSDS法を「結論サンドイッチ法」と呼んでもいます。
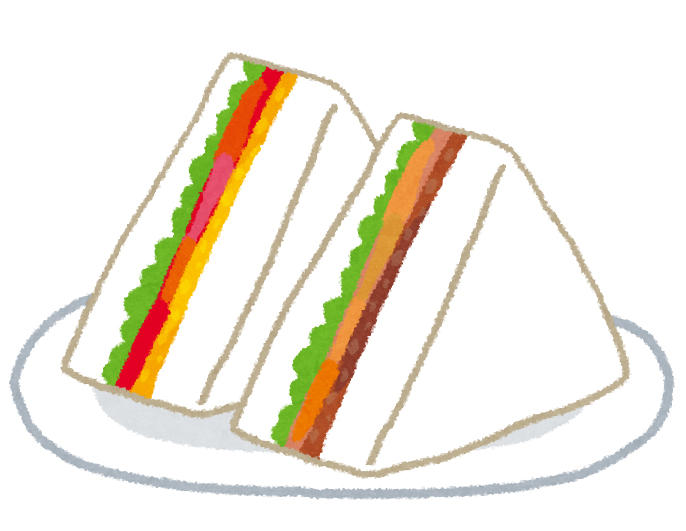
シンプルながら活用範囲の多い書き方ですので
ぜひ覚えて使えるようになっていただければ、と思います。
なお、論述試験で文字数が少ない場合は
最後のSummaryを削ることも可能ですので
参考にしてみてください。
SDS法での論述例
では、実際にSDS法で
答案を作ってみましょう。
前々回の記事で書いた
「北海道大学 大学院教育学院」の過去問の例で
見てみましょう。
「銀行型教育」という言葉を説明する、
という過去問をSDS法で答えてみます。
(専門外の人にはイマイチ何のことか
分かりづらいかも知れませんが、
「まあ、そんなもんだな」と考えてみてください)
「銀行型教育」の論述例(SDS法)
S: ブラジルの教育学者パウロ・フレイレが
現代教育に対して行った批判を意味する。
D: フレイレは『被抑圧者の教育』において
従来からの詰め込み主義の教育を
「銀行型教育」と言って批判をした。
これは社会的に抑圧された立場にある人々に対し、
役に立たない概念をただ詰め込み、
暗記させる発想を批判的に見た考え方である。
この「銀行型教育」に対し、
被抑圧者自身が自ら知識を獲得し
抵抗していく「対話型教育」の重要性を提唱している。
この「対話型教育」により
被抑圧者を支援・援助していく発想が重視された。
S: このように「銀行型教育」とは「対話型教育」の対極にある概念であり、
詰め込み主義に基づく教育を批判するための概念であると言える。
(注 この回答例はフジモトが書いたものですので
「例」としてお考えください)
結論→詳細→結論の順で。
最初に本文の結論を
一言で示しています。
(「銀行型教育とは」という書き出しでもいいのですが、
設問が「銀行型教育という言葉を説明しなさい」なので
カットするのも可能です。
ムダな字数を削るために今回の回答例ではカットをしています)
その後その詳細を述べた後、
最後に再び結論を示しています。
適当に書くとグダグダになってしまいやすいのが
今回のような論述問題です。
SDS法という基本の答え方を身に着けた上で
回答する練習をしてみてくださいね!
今回のポイント
短い字数での論述試験に効力を発揮する!
SDS法を身に着けよう!
論述練習に「添削」が必要な理由。
なお、書き方をどんなに学んだとしても、
「この回答で本当にいいのかどうか」は
誰かに添削してもらわなければ
よくわからないものです。
体験授業の中などでも
こういった添削を行っておりますので
お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

次回は2つ目の
「回答基本のパターン」をご紹介しますね!
ではまた!