目次
コアラのマーチってどう作られている?
ロッテから長年販売されているお菓子・コアラのマーチ。
1984年の発売以来ベストセラーです。

1984年当時はオーストラリアからコアラが贈られたことでコアラブームが起きていました。
それを受けて販売されて依頼、現在41年を超えて販売され続けています。
おそらく子ども時代に美味しく食べた記憶をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

(写真はwikipedia)
コアラのマーチのユニークな絵柄!
コアラのマーチといえば、1つひとつにユニークな絵柄が描かれているのが印象的です。

お菓子の名前に「マーチ」とあるように、もともとはマーチングバンドをやっている絵柄が12種類あるだけだったのようです。
ですが、いまは本当に多くの絵柄が出ています(SDGs関連やテレワークなど、時事ネタを取り入れた物も多いです)。
なんと現在500種類以上を超える絵柄が存在しているというから驚きです、
コアラのマーチの絵はどう描いている?
ところで、あなたは「コアラのマーチ」の絵柄がどうやって描かれているか、ご存知ですか?
私自身、妻と話していたとき、「きっとあれって、焼き上がった後にレーザーか何かで絵を描いているんじゃない?」と考えました。
ところが、実際はまったく逆だったのです。
なんと、生地に最初にカラメルで絵を描いてから、焼き工程に入るとのこと。
この情報はロッテの公式サイトに掲載されていました。

https://www.lotte.co.jp/entertainment/factory/tour/koala.html
(個人的にはコアラのマーチの模様ってレーザーの焦げ目だと思っていたので、カラメルで味付けをしている事自体に驚きを感じました)
印刷後、コアラの形に切り抜き焼きあげたあとチョコを充填して作っているのです。
絵を描いたあと、焼いて膨らませ、チョコレートを中に詰めるという手順――。
公式サイトでは映像付きでこの模様が描かれています。
だんだんコアラのマーチが完成する形も楽しいですし、「ああ、こうやって作られているんだな…」と知るとそれだけで感慨深くなります。
工場見学の面白さと、見えない作業への驚き
こういった普段見えない製造過程を知るのって面白いですよね。
ロッテのサイトにはコアラのマーチ以外にもいろんなお菓子の製造工程が描かれています。
見ていて感動したのがチョコパイの製造工程。

☆チョコパイの製造工程はこちら→https://www.lotte.co.jp/entertainment/factory/tour/chocopie.html
実は私、子どものころからチョコパイが大好きでして、今も9個パックが安売りになっていたら思わず買ってしまいます(笑)
あのチョコパイがベルトコンベアを流れていく様子などを見ると、それだけで食べたくなってきます。
意外と作り方は知られていない
コアラのマーチの製造工程って、イメージと違うことがあります。
ですが、こういう作り方を知ると、いつも食べているお菓子も違う見方で見れるようになりますね。
これ、実は大学院受験の世界にも似ています。
論文は「前から順に書かれている」と思っていませんか?
論文って「はじめに」から始まり、「先行研究の検討」「研究方法」「倫理規定」「研究結果」「考察」「結論」などという順番で続いていきます。
多くの人は、研究論文や研究計画書を読むとき、その整然とした構成から「きっと最初から順に書いているんだろう」と思いがちです。

でも、実際はそうではありません。
論文は、「はじめに」「先行研究の検討」「研究方法」「倫理規定」「研究結果」「考察」「結論」と順に並んでいますが、多くの研究者は“後ろから”書きます。
つまり、まず実際に研究をして、結果を出して、それをどう解釈するか(考察)を考える。
そして最後に「この研究にはこういう意義がある」とまとめてから、「はじめに」や「先行研究との関係」を逆算して書いていくわけです。
つまり「はじめに」と言いつつも、一番最後に書かれているケースも多い、というわけです。
作り方がイメージと違うという点では「描いてから焼く」コアラのマーチの製造工程に似ているようにも思います。

研究計画書を書くのが難しいのは「順序」を誤解しているから
大学院受験の相談を受ける中で、「研究計画書の書き方がわからない」「研究ってどうやって始めればいいのか見当もつかない」という声をよく耳にします。
その原因として「一番最初の部分から順番に書かないといけない」と考えているケースが多くあります。
また、研究とはどういうものか分からず書き始めているケースも多くあります。
本来、研究というのは「仮説」を立て、それを検証していくプロセスです。
この仮説は「もし〇〇ならば、△△になるのではないか」と、因果関係を意識した論理的な構造を持つ必要があります。
そのため、仮説が立っていない状態でいきなり「はじめに」から書き始めようとすると、手が止まってしまうのです。
だからこそ、正しいやり方・書き方を知らずに始めると壁にぶつかってしまうのですね。
「やり方を知る」ことの価値
私の運営する1対1大学院合格塾では、大学院受験に必要な研究計画書の書き方や論文の書き方について実践的にご指導差し上げています。
ありがたいことに、体験授業に参加された方からは、
「研究計画書って、こうやって書くものだったんですね」
「この方法なら自分でも書けそうな気がします」
といった前向きな声を多くいただきます。
やり方がわからないまま、がむしゃらに取り組むのではなく正しいやり方や順序を知ってから書く。
それだけで、取り組みの質もスピードも大きく変わるのです。
「研究って難しそう…」「計画書が書ける気がしない…」と感じている方は、ぜひ一度うちの塾の体験授業で“やり方を知る体験”をしてみてください。
そして、あなた自身の研究計画をバッチリ作り上げ、大学院受験本番につなげていきましょう!
うちの塾があなたをアシストしていきます!

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!















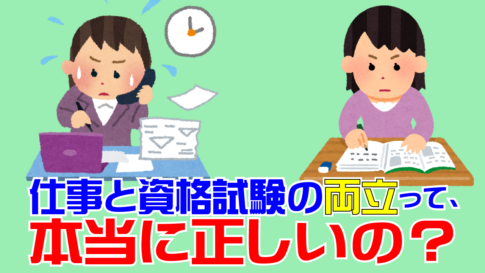








コアラのマーチの絵柄って、焼いてから描いているのでしょうか?描いてから焼いているのでしょうか?実は描いてから焼いているのが正解です。作り方を知ると意外な発見があるものですね!大学院で書く論文も通常の順番とは逆に書かれている事が多いです。作り方を正しく知ると発見があるのはコアラのマーチも論文も同じですね!