目次
問題集を選ぶときのコツは「50%の難易度」!
資格試験やTOEIC、大学院受験など、さまざまな学習に取り組むときに欠かせないのが「問題集」。
これまで、学生時代から多くの問題集と向き合ってきた方も多いのではないでしょうか?
問題集ってたくさんの種類があります。
書店に行けば膨大な数の問題集が並んでおり、「どれを選べばいいの?」と迷ってしまうことも多いのではないでしょうか?

今回は「問題集選び」で失敗しないポイントをご紹介します!
「難しすぎる」問題集も「簡単すぎる」問題集もNG!
問題集を選ぶ際、多くの方が「評判がいいから」「合格者が使っていたから」という理由で選ぶことが多いかもしれません。
実際、書店で「人気NO.1!」というポップがついている問題集をついつい選んでしまうこともあるかも知れません。
ですが、そうやって買ってきた問題集を解いてみると「難しすぎて全然解けない…」こともあります。
逆に「簡単すぎて退屈…」と感じることもありますよね。
実際、難しすぎる問題集を使うと、挫折感が強くなり、「自分には無理かも…」とモチベーションが下がってしまうことがあります。
一方で、簡単すぎる問題集では、学習効果が感じられずだらけてしまうこともあります。
つまり、問題集選びは難しすぎても簡単すぎても良くないのです。
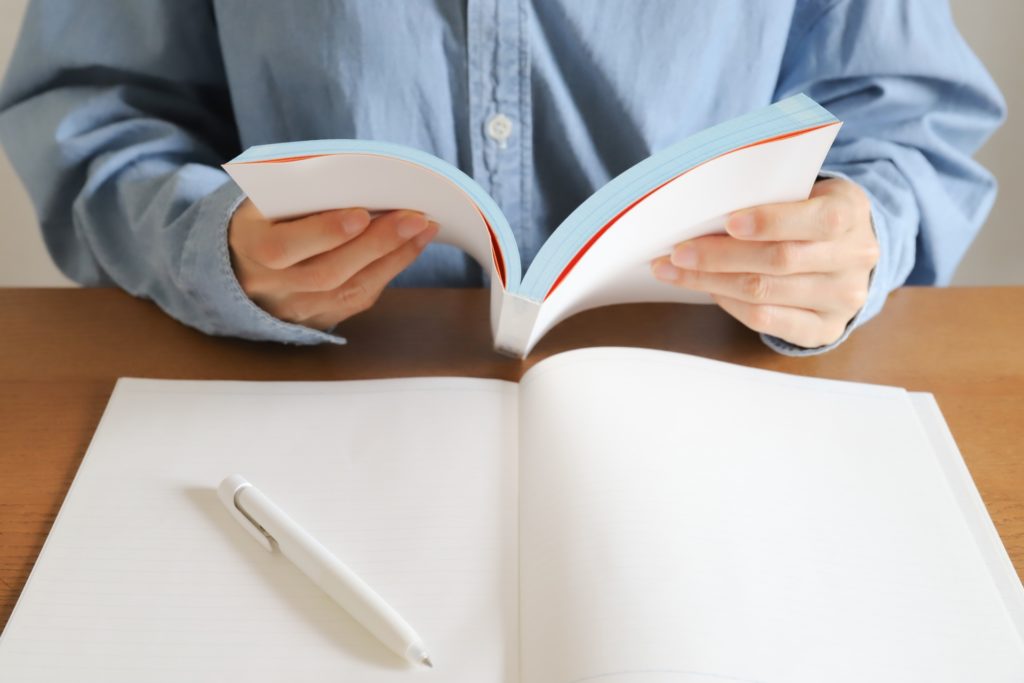
さらには他人の評価ではなく、自分にとって最適かどうかで考えるべきと言えます。どちらに振れても長続きしづらく、結果として勉強が定着しないリスクがあるのです。
理想は「50%解ける問題集」がベスト!
では、どういった問題集が理想的なのでしょうか?
その目安は「自力で問題の50%が解ける難易度のもの」です。
つまり、ページに出ている問題のうち半分くらいの問題が解けるくらいの難易度の問題集がベストなのです。
この考え方には、ある実験がヒントになっています。
ある研究で、子どもたちが輪投げをするとき、どのくらいの距離から輪を投げるかを調査したそうです。

輪投げって、的に近いとカンタンに入ります。
反対に、的から遠いとなかなか入りません。
ではどれくらいの距離から輪投げをすることが多いのかを調べてみると、輪が入る確率がちょうど50%くらいになる距離で挑戦する子どもが最も多かったという結果が出たのです。
「子どもたちが一番多く輪投げをしたのは、成功の確率が50%と感じている距離からでした。
この実験からわかったことは、輪投げが難しすぎるとやる気を失い、一方簡単すぎてもやる気を失うということです。
その丁度中間ぐらいがやる気が高まるようです」
外山美樹. 2021. 勉強する気はなぜ起こらないのか. 筑摩書房. 90頁

これはどういうことかというと、「簡単すぎると面白くない」「難しすぎても楽しめない」という人間の心理を表しています。
入るか入らないか、成功と失敗が半々くらいの状態が、最も集中力とやる気が高まる、ということですね。
この「50%の原則」は、勉強にもそのまま当てはまります。
つまり、50%の問題を自力で解ける問題集が良いわけです。

☆『勉強する気はなぜ起こらないのか』の詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/3YT2NiX
問題集選びに迷ったら「真ん中のページ」を開いてみよう
実際に書店で問題集を手に取ったときに試してみてほしい方法があります。
それは、問題集の「真ん中あたりのページ」を開いて、実際に問題をいくつか解いてみることです。
そして、そのうち半分くらいが自力で解けるかどうかをチェックします。
- 解ける問題が多すぎる(7〜8割以上)
その問題集は「復習用」として使うならアリですが、新たな知識を得るには向いていないかもしれません。 - 解けない問題が多すぎる(3割以下)
挫折の原因になりやすく、継続が難しくなる可能性があります。 - 半分くらいできる(4〜6割) →
理想的な難易度。手応えも感じつつ、新しい学びも得られる状態です。
この「半分できるかどうか」のチェックこそが、問題集選びの一番のコツなのです。
思い余って中学生用の教材を用意していませんか?
学習をする際、時折「もう一度基礎からやり直そう…」と思い、ものすごく簡単な教材を買ってくる方がいらっしゃいます。
例えば英語や数学なら中学生用の教材を買ってくる方です。
もちろん、本当に基礎がわかっていないならこういうのを使うのもアリだと思います。
ですが、こういうテキストっておそらく9割以上わかってしまっていることも多いものです。
その場合、該当箇所だけ学習し、その後は潔くよりレベルが高い教材(高校生用など)に進んだほうが良いのです。
すでに観てきたように、簡単に解ける問題ばかりだとやる気が下がってしまうことも多いのです。
英語学習でも応用可能!知らない単語が半分くらいの教材がベスト
特に英語学習の場合、「知らない単語が50%くらいあるテキスト」を選ぶのが効果的です。
全部わからないとただの暗号に感じてしまいますし、すでに知っている単語ばかりだと学習効果が得られません。
「知っている単語もあるけど、ちょっと難しい」くらいのレベル感が、無理なく学習を継続できる秘訣です。
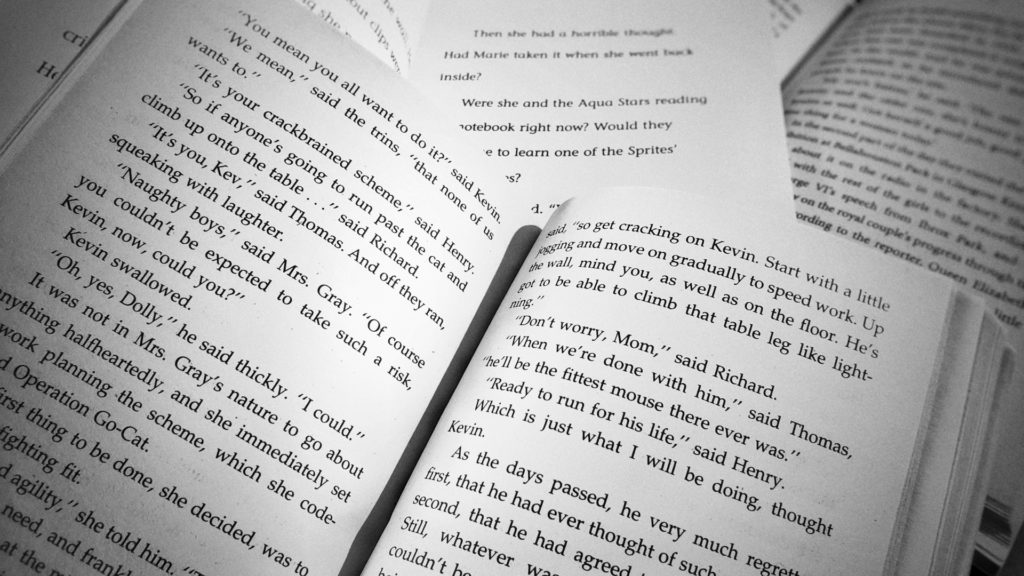
とはいえ…大学院受験にはちょうど良い教材が少ないのも現実
この「50%の原則」は、TOEICや資格試験などでは比較的適用しやすい考え方です。
ですが、「1対1大学院合格塾」を運営している側から見ますと、大学院受験に関してはそもそも問題集が少ないという課題があります。
そのため、「ちょうどよい難易度の問題集が少ない」のが毎年の悩みのタネです。
特に専門知識の分野では、そもそも市販の問題集が少なく、過去問だけに頼らざるを得ないケースも多いです。
そうした場合は、過去問をベースに自分で解説を書き込んだり、わからない部分を辞書やネットで重点的に調べる工夫も必要になります。
学習継続のカギは「ちょっと背伸び」
学習を続ける上で大切なのは、「ちょっとだけ背伸びした状態」を保つこと。
つまり、自分の今のレベルからほんの少し高いレベルの課題に挑戦し続けることです。
その「ちょっとだけ」が、まさに50%解ける問題だと言えるでしょう。
これこそが、モチベーションを保ちつつ、着実にレベルアップできるラインとなるのです。
まとめ!問題集は「半分くらいわかるもの」がベスト!
問題集選びに迷ったら、「だいたい半分くらい解けるかどうか」を基準にしてみましょう。
50%の難易度は、やる気を保ちつつ、効果的に学習を進めるうえで非常に重要なポイントです。
資格試験、英語、大学院受験など、どんなジャンルの学びにおいても「ちょっとだけ難しい」問題に取り組み続けることが、最終的には大きな成果に結びつきます。
ぜひあなたのキャリアアップに役立ててくださいね!

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!












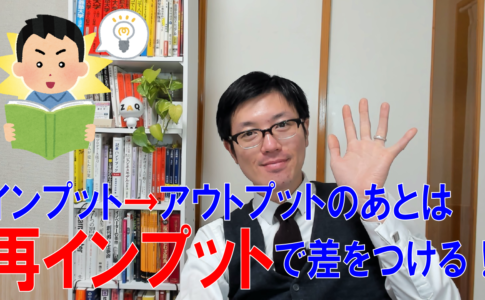

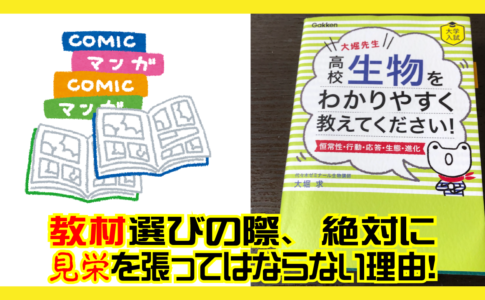









問題集選びで大切なのは「50%の難易度」のものを選ぶこと。自力で半分くらい解ける問題集を選ぶことが、やる気と成長の両立に役立ちます。難しすぎず簡単すぎない教材が、継続学習のカギになりますよ!