目次
修士論文を出す達成感。それだけで終わっているのはもったいない…!
「なんとか修士論文を書き終えた……!」
大学院の修士課程2年間。
ざっくり言えば「2年かけて修士論文を書き上げる」ことこそが大学院の目的である、といえます。
2年間(人によってはそれ以上)の時間をかけて修士論文を書き上げる。
これ、大きな達成感を伴う瞬間です。
大学院での集大成として、多くの時間と労力をかけて仕上げた修士論文。
ですが、実はそのまま“出して終わり”にしてしまうのは、少しもったいないかもしれません。
せっかくまとめた研究を、そのまま埋もれさせてしまうのではなく、学会発表や論文投稿として再活用することが、あなた自身のキャリアにとっても、学問への貢献にとっても非常に有効です。

本記事では、「修士論文の“その後”の活用法」として、
- なぜ分割して発表・投稿するべきなのか
- どのように分割・再構成すればよいか
- 学会発表・論文投稿のメリット
- 実際にどう動くかのステップ
をお伝えしていきます!
修士論文は“情報の宝庫”
修士論文というのは、たとえるなら「研究のフルコース」です。
序論から文献レビュー、方法論、データ分析、考察、結論まですべての要素が詰め込まれています。
場合によってはあれこれの詰め込み、盛り沢山な内容となっています。
ですが、学会発表や学術論文は、1つのテーマに焦点を絞って簡潔に提示するのが一般的です。
つまり、修士論文をうまく“切り分け”て編集し直すことで、複数のアウトプットに変換できるのです。
学会発表・論文投稿の3つのメリット
修士論文を書き上げるのは大きな達成感が得られますが、修士論文ってあくまで「修士号」を取るために形式的に提出するものです。
修士論文として提出したところで、修士課程修了の審査をする教員しか読みません。
せっかく苦労して書いても、修士論文の形だけであればほとんど日の目を見ないのです。
修士論文を研究業績にするには修士論文の一部を切り出して再構成する(あるいは章ごとにどこの学会に提出するかを考える)ことが必要不可欠なのです。
ここでは修士論文を学会発表や論文投稿するメリットを3点に分けて説明します。

① 自分の研究を世に出せる!
せっかくの研究も、読むのが指導教員と審査委員だけでは寂しいものです。
学会や論文という形で外部に発信することで、あなたの研究は“社会的に存在する知”になります。
他大学の研究者や実務家と出会うきっかけにもなり、「こんな視点があったのか」と新たな学びにもつながります。
② キャリア形成に役立つ!
将来的に大学教員や研究職、あるいは専門性を活かした実務職を目指す方にとって、発表歴・投稿歴は「研究能力の証明」になります。
履歴書や(登録していれば)reserchmapなどの研究業績欄に記載をできるようになります。
いくら修士論文で良い研究をしていても、学会発表や論文投稿の実績がなければなんにもなりません。
特に大学講師の募集では「研究実績」がなければ評価されない側面があります。
修士論文の一部を切り出して学会発表や論文投稿していくことがあなたのキャリアにもつながるのです。
③ 研究を“アップデート”できる!
修士論文を書いたときには気づけなかった点も、学会発表や論文投稿をする際、他の研究者と意見を交わすことで見えてきます。
たとえば、「別の視点でデータを読み解けるのでは?」という示唆を得たり、「この資料が参考になる」と教えてもらえたりと、次の研究ステップに向けたヒントが得られます。

どうやって分割する?3つのパターン
では実際にどうやって修士論文を切り出していけばいいのでしょうか?
いろんなパターンが考えられます。
パターン1:一部の章をピックアップして短い論文に
たとえば、方法論と結果に絞って「ある地域の調査分析」として論文にする、あるいは「先行研究レビュー+問題提起」だけで理論的論文とすることも可能です。
この場合、もとの修士論文を骨格にして“削る”ことで、投稿論文として仕上げられます。
なお、修士論文自体が短い場合は全体の骨組みを残したまま、不要な要素を削っていって1つの論文にすることも可能かもしれません。
一般的に、研究学会への論文投稿は「1〜2万字」などと字数が設定されています。
あなたが所属したい学会の学会誌の投稿規定をサイトで字数設定を確認しましょう!
パターン2:複数のサブテーマに分けてシリーズ化
修士論文の中に、「メイン分析」と「補足分析」がある場合、それぞれを別の学会で発表するのもおすすめです。
例:
- 第1発表:A地域の教育政策の変遷
- 第2発表:A地域における保護者の意識調査の結果
など、1つの論文から複数のアウトプットを作れることもあります。
パターン3:実務応用バージョンとして書き直す
実践現場での活用や政策提言に向けて、文章のスタイルを調整するのも一つの方法です。
たとえば、学術論文風ではなく「事例レポート」や「調査報告書」としてNPOや自治体の研究誌に投稿することで、社会的インパクトをもった発表にもつながります。
学会発表・論文投稿の流れ
ここからは具体的に修士論文を学会発表や論文投稿する際のステップを見ていきます。

(1)学会発表の流れ
まずは学会発表の流れから。
一般的に学会発表は次のようなステップで準備を進めていくことになります。
- 自分の研究に合った学会を探す(大学の先輩や指導教員に聞くのも◎)。そしてその学会に加入しましょう(年会費1万円程度かかります)。
- 発表申込の募集時期を確認(多くは数カ月〜半年くらい前に募集が締め切られます)
- 発表要旨を提出(400〜1,000文字程度)
- スライドや原稿を準備(事務局側に事前に送付が必要なケースが多いです)
- 当日発表&質疑応答
発表後には「研究会報告」として記録が残ることもあります。
学会発表をするとその前後に有益なアドバイスも得られるので貴重な学びの機会にもなります。
(2)学術論文 投稿の流れ
続いて学術論文の投稿についての流れを見ていきましょう。
一般的に学術論文の雑誌投稿は次のようなステップで準備を進めていくことになります。
- 投稿先の学会誌・ジャーナルを選定する(査読付き/紀要系など)
学会発表を行おうと思っている学会の学会誌・ジャーナルに投稿することになります。
論文投稿にはその学会に加入することが必要なケースがほとんどです。 - 投稿規定に従って論文を構成(タイトル、要旨、本文、参考文献)
- (査読論文の場合)査読結果を受け取る
他の研究者が匿名で研究に対し「掲載可能」「修正したうえで掲載可能」「掲載不可」などとコメントするのを「査読」といいます。
査読結果を受けたうえで、そのまま掲載されるケースもあれば修正が必要ケース、リジェクト(却下)されるケースがあります。 - 雑誌掲載!
こちらは学会発表よりも少しハードルが高く感じるかもしれませんが、大学院の修了後も継続的に取り組む価値が大きい作業です。
特に、研究者としての実績は「どのレベルの雑誌に何本論文が載ったか」が重要な要素となります。
博士後期課程を進学する場合、査読付き論文が最低2本ないと博士論文の審査を行ってもらえないケースもあります。
ぜひ臆せず論文投稿に挑戦してみましょう!

論文がリジェクト(却下)された場合も、腐ることなく「修正して別の雑誌媒体に投稿できないか」考えてみるのもありです!
よくある不安
人によっては
「まだ発表する自信がない……」
「学会なんか自分が発表する場ではない…」
「論文の書き直しって難しそう…」
と不安を感じてしまうこともあるかもしれません。
こうした不安、誰もが感じるものです。
ですが、修士論文を完成させたという事実自体、あなたの研究力の証明でもあります。
不完全でもかまいませんので、ぜひ学会発表や論文投稿に挑戦してみましょう!
挑戦するからこそ見える世界があるはずです!
実際 私も初めて学会発表や論文投稿に挑戦したとき大変緊張したのを覚えています。
ですが、発表や投稿がうまく行った際、非常に大きな自信になりましたし、自分の書いた論文が他の研究者に引用されているのを発見した時、とても嬉しかったのを覚えています。
「あ、自分がやってきた研究はムダじゃなかったんだ」と思える貴重な瞬間でした。
修士論文は“資産”!活用してこそ価値がある
修士論文を書き上げる。
これは決してゴールではなく“新しいスタート”です。
せっかく作った修士論文をもとに学会発表や論文投稿することを通し、あなたの研究はさらに磨かれ、広がっていきます。
大変だった分、たくさんの可能性が詰まっている修士論文。
その可能性を「分割」して、「発表」して、「育てる」ことで、研究者として、また実務家としてのステージも一段上がるはずです。
ぜひ修士論文を書いて出すだけで終わらせず、次の一歩にぜひつなげてみてくださいね!
(修士論文の活用方法も体験授業などでアドバイス可能です!)
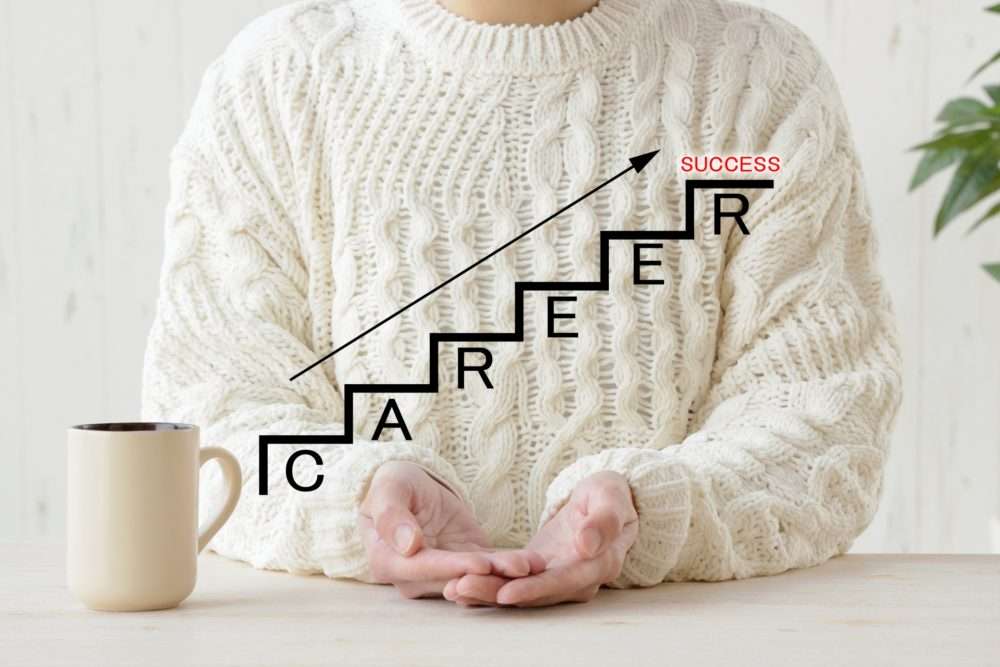
「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!
























修士論文は提出して終わりだともったいないです。一部を切り出して学会発表や論文投稿に活用することで、研究成果を広く発信することができます。それが自分の研究実績となり、キャリア形成にもつながります。ぜひ自身の研究を社会に届け、次のステップへとつなげていきましょう!