目次
大学院では学びの場を自分で作れる!
大学院では、自ら学びを深めるための環境が整っています。
大学院の講義やゼミ、指導教員との個別の指導というものもありますし、図書館や自習室などの学習スペースもあります。

ですが、それだけでなく自主的に勉強会や読書会を開催することもできます。
それにより、自分の知識を深めていくこともできます。
今回は、大学院において自主ゼミや勉強会を開催する意義やメリット、開催のポイントについてお伝えします!
自主ゼミ・勉強会とは?
大学院では通常の授業やゼミのほか、「自主ゼミ」や勉強会が開催されることがあります。
「自主ゼミ」とは、大学院生が主体となって企画・運営する学習会のことです。
通常のゼミのなかでは扱いにくい内容や基礎的な内容などを院生同士で自主的に集まり勉強していく場となっています。
「勉強会」のほうはその名の通り、院生同士で集まり基本文献を1章ずつ読んでいったり基礎的な学習をともに行ったりと一緒に勉強する場となります。
読書会のように、毎回本を決めて皆で読んできてから中身について議論することもあります。
「自主ゼミ」も「勉強会」も、学生同士でテーマを決めて発表したり文献を読んだり議論を交わしたりする点ではほぼ同じと言えます。

私自身、早稲田大学の大学院時代に自主ゼミや勉強会を開催していました。
もともと先輩方が立ち上げた自主ゼミに参加させていただいたのがきっかけで、そこでの学びが非常に有意義だったことから、自らも勉強会を主催するようになりました。
思えば自主ゼミや勉強会でいろんな内容を学びましたし、他の方がやっている自主ゼミや勉強会にもあれこれ参加しました。
「統計」の基本を学んだのも、社会学の基礎文献や哲学の基本書を読んだのもこういう場でした。
自主ゼミや勉強会だからこそ忌憚なく議論できたのが印象的でした。
自主ゼミ・勉強会のメリット
自主ゼミや勉強会には次の3つのメリットがあります。
1. 学びの深化と継続的なインプットが可能に!
大学院では、講義やゼミの時間だけではカバーしきれない学習内容が多くあります。
自主ゼミを開催することで、自分たちのペースでより深く研究を進めることができます。
例えば、特定のテーマに関する文献を共同で精読し、意見交換を行うことで、多角的な視点から理解を深めることができます。
特に、大学院の通常の授業では質問しづらい基礎的な内容についてを気軽に相談する場としてもこういう自主ゼミや勉強会は役立つのです。
2. 学びのコミュニティ形成
自主ゼミや勉強会を通じて、同じ興味・関心を持つ仲間とつながることができます。
大学院生活は個人での研究が中心になるため、ともに学ぶ仲間の存在はモチベーション維持に大きく役立つはずです。
試験前などは協力して試験対策をすすめることもできますし、このコミュニティがもとになって大きな研究を一緒に行うことも可能となります。
個人で研究を進めていると、どうしても視野が狭くなりがちです。
ですが自主ゼミや勉強会で仲間と議論することで、自分では気づかなかった視点を得ることができます。
3. アウトプットの機会を増やす
学んだことを言語化し、他者に説明すること。
これは理解を深めるうえで非常に重要です。
自主ゼミでは、自分の研究進捗を報告したりレジュメを作成して発表したりすることでアウトプットの機会を増やすことができます。
このプロセスを通じて、自身の研究内容を整理し、論理的に伝えるスキルを向上させることができます。

自主ゼミ・勉強会の開催方法
では自主ゼミや勉強会ってどのように開催すればいいのでしょうか?
次の4点を参考にしてみてください。
1. テーマを決める
まずは、何を学ぶのかを明確にすることが大切です。
例えば、「特定の学者の著作を読む」「最新の研究論文を検討する」「研究発表の練習をする」など、目的に応じたテーマを設定しましょう。
2. メンバーを募る
内容や頻度に応じて、参加者を募集するといいですね。
いまの大学院のゼミの有志で開催してもいいですし、同じ研究テーマを持つ他大学の院生や専門分野の人を交えて議論するのもいいですね。
私の1回目の大学院生時代(早稲田大学大学院時代)はすでに行われていた自主ゼミ(「サブゼミ」と言っていました)に加えて「プチゼミ」という追加の自主ゼミを企画・開催をしていました。
メンバーは大学院のゼミ生のうち何名かで開催したのを覚えています。
他にも、研究分野が近い院生同士で読書会形式の勉強会を開催しましたし、他の人がやっている勉強会にもあれこれ顔を出していました。
3. 進行役を決める
毎回の勉強会で進行役を決めるとスムーズな運営が可能です。
特定の人が負担を抱えすぎないよう、持ち回りで進行役を担当するのもおすすめです。
4. 資料やレジュメを準備する
自主ゼミや勉強会の充実度を高めるために、事前に資料やレジュメを準備すると良いでしょう。
発表者が簡単にでもいいのでレジュメ(配布資料)を作成し、事前に共有しておくと話し合いがよりスムーズになります。
(以前であればメーリングリストにPDFを添付して送っていましたが、いまではLINEグループやFacebookグループなどで簡単に共有ができるのでいい時代になりましたね…!)

まとめ
大学院生活では、学びを深めるための機会を自ら作ることができます。
その中でも自主ゼミや勉強会を始めることは知識の深化、学習仲間の形成、アウトプットの機会創出など、多くのメリットがあります。

こういう場を自分で始めることで、勉強や学びがより楽しくなることでしょう。
ぜひ、自ら学びの場を作り、積極的に参加してみてください。
こうした取り組みが、あなたの研究やキャリアに大きな影響を与えるはずですよ!
実際 私も大学院生の頃にあれこれ自主ゼミや勉強会・読書会を多数開催したことで「イベント」開催のノウハウも学ぶことができました。
いま起業して自分の塾を運営できているのも、また研修講師として人様の前で講座を担当できるのも、その原点は院生時代の自主ゼミや勉強会にあります。
専門分野の知識を深められるだけでなく、イベント運営や企画・進行なども学べるのが自主ゼミや勉強会なのでぜひ挑戦してみてくださいね!!!
「やらされ」で学ぶのと違い、やりがいと楽しさが大きいはずですよ!

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!












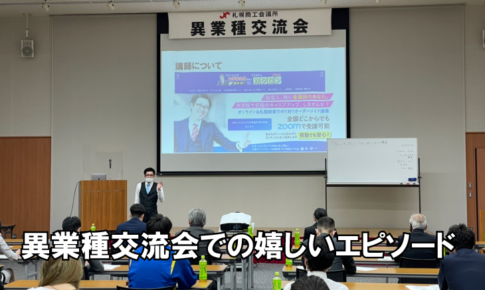











大学院では規定の授業やゼミだけでなく、自主ゼミや勉強会を自分で開催するのがオススメです!それにより知識を深め、学びのコミュニティを形成し、アウトプットの機会を増やすことができます。こうやって積極的に学びの場を作っていく姿勢、研究やキャリアアップに役立ちますよ!