目次
博士号取得は「夢のまた夢」か?
「大学院に行って博士号を取りたいけど、自分なんかではきっと無理じゃないかな…」
大学院に行って博士号を取る。
これって、大学院を目指す人にとってとても「憧れ」です。

大学院で博士号を取るには大学院での修士課程2年のあと、博士後期課程で少なくとも3年間は過ごす必要があります。
修士課程2年間を終えると修士号を取れますが、博士後期課程はたとえ3年間を経ても「博士論文」を書き切り、それが受理されなければ博士号は取れません。
文系の場合は3年間どころか5年、さらには追加で何年もかけてようやく博士号が取れるケースもあります。
場合によっては博士課程に何年もいたけれど博士論文を出すことなく「博士課程満期退学」として博士課程を終えるケースもあります。
こういう話を聞くと「博士号取得なんて私には無理…」と尻込みしてしまう人も多いかもしれません。
博士号取得と聞くと、「天才だけが到達できる境地」「凡人には難しすぎる」と思われがちなのです。
でも、本当にそうでしょうか?
今回はイギリスで出版されている名著『博士号のとり方』を紹介しながら、博士号取得の現実について見ていきます。
名著『博士号のとり方』
E・M・フィリップス/D・S・ピュー著の『博士号のとり方』(第6版)。

この本は35年以上前にイギリスで出版されて以来、版を重ねつつ世界中で読みつがれている名著となっています。
「誰も教えてくれなかった!ガイドの決定版」との帯紙は伊達ではなく、博士号を取るにはどうしたらいいか、どのように時間を使えばいいか、指導教員とどう関わればいいかが克明に描かれています。
☆本書の詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/3DrCadk
イギリスと日本とでは博士課程のあり方に異なるところがありますが、日本で博士号を取る際にも役立つ知見が散りばめられています。
博士課程は職人芸ではなく再現可能なゲームである。
本書の最も印象的なのは「博士号取得は職人芸ではない」というメッセージが描かれているところです。
博士後期課程に進学して博士論文を書く際、多くの人が「社会にインパクトを与えたい」「革命的な理論を生み出したい」と大きな理想を掲げます。
ですが、著者たちはこのような壮大な目標を持つことが博士論文執筆の妨げになり得ると指摘しています。
博士号というのは学術的に意味のある研究を一定の水準でまとめることができることを証明するものです。
それによって「プロの研究者である」ことを証明し、プロの研究者の仲間入りをするためのツールが博士号なのです。
場合によっては社会的な影響力や実用性よりも、学術的に新規性があるか、学術的に貢献があるかどうかが重要視されます。
博士論文を書いていると「この研究は役に立たないのではないか?」「もっと革新的な理論を作らないといけないのではないか?」と不安に思うことがあります。
ですが、この本では「博士論文のルールに沿った論文を書けばよい」というシンプルな考え方が成功へのカギとなることを伝えているのです。
つまり、「博士論文では「すごい」内容を伝えるべきだ」「天才でないと書けない」と尻込みする必要はまったくないのです。
下手に不安にならず淡々と論文をまとめていく。
それが博士号を取る際に求められる姿勢なのですね。
「インタビューした大学院生たちが、「研究を終わらせるために大事なことは、『頭のよさ』より『決意』、『決断力』だ」と述べたことを思い出そう」(174ページ)とあるとおりなのです。

アインシュタインもマルクスも、博士論文を書き上げたあと独創的な研究を行った。
博士論文を書く際、ついつい「自分オリジナルの斬新な研究をしなければならない」「独創性がなければならない」と意気込んでしまいがちです。
でも、こうやって自分を追い込むほど研究がなかなか進まない事になってしまうのです。
天才とされるアインシュタインやマルクスも、博士論文を書くときには博士論文のルールの中で研究を行い、博士号を取ったあとに自分が本当にやりたい研究・独創的な研究に手を付けていった事実が本書では描かれます。
「パラダイムシフトへの挑戦は、博士課程が終わってからでもよい。
実際、多くの博士課程の学生がそうする。相対性理論(よく知られた例ではポストニュートン物理学に関するパラダイムシフト)は、アインシュタインの博士論文ではない(彼の博士論文はブラウン運動の理論への貢献に関するものであった)。
「資本論」もマルクスの博士論文ではない(彼の博士論文は無名のギリシャ人哲学者二人の理論)。
もちろん、アインシュタインもマルクスも、博士課程にいる間も後の大きな発見につながる疑問を抱えていたに違いないが、彼らもまずは、既存の理論をマスターすることを優先したのである」(58ページ)
博士論文執筆はあくまで「学位」を得るためと捉え、博士論文に求められる要素だけをコツコツ執筆していけばいいのです。
感情・人間関係によって博士論文執筆が停滞する事実。
本書が興味深いのは博士論文執筆という「論理」に基づく作業が、「感情」「人間関係」によって成果が大きく左右されやすいという指摘をしているところです。
つまり「自分の研究に意味がないんじゃないか」という不安や「やっていても終わらないのでは」という焦り、指導教員や院生同士の人間関係によって博士論文執筆が停滞する現実が描かれています。
本書ではこういう「感情」や「人間関係」上の課題にどう対処すればいかも克明に描かれています。
これが博士論文執筆の際、大いに役立つのです。
さらには博士論文の手前にある「修士論文執筆」にも大いに得ることがあるはずです。

1日8時間の研究を3年間。
イギリスと日本とでは博士課程のあり方が若干違うところがありますが、本書では博士号を取得するための目安として「1日8時間 週5日の研究」をあげています。
ちょうど会社で1日8時間労働を平日5日行うのと同様、博士課程在学の3年間は同じだけの時間を費やすことを目安とすべき、と述べているのです。
「さて、ここまで話をすると、それでは博士課程学生として成功するには実際に何時間費やすべきなのか、という質問にたどり着く。
大まかにいえば、博士課程学生であることと、フルタイムで雇用されている状態とはほぼ同じであるといえる。
つまり、一週間に40時間を目安にすればよいだろう。
パートタイムの学生の場合は、働く時間に比例して割り出すとよい。」(200ページ)
そのため仕事をしながら博士課程に通う場合1日の研究時間をそんなに取れない場合は3年間でなくさらに時間をかけて博士課程の研究に取り組むこととなります。
そうであったとしても「起きている間はずっと研究に明け暮れないと博士号を取れない」わけではなく、毎日コツコツ研究することで博士号取得につなげられることを教えているのです。
つまり、博士号取得には「特別な才能」よりも、「一定の時間を研究に費やすこと」が大切なのです。
もちろん、日本の研究環境では、指導教員や研究費の状況などによって理想通りには進まないこともあります。
ですが、〈博士号取得は天才の証ではなく、一定の努力を続けることで手に入れられるもの〉という考え方は、多くの博士課程の学生にとって励みになるのではないでしょうか。
博士課程のハラスメント問題
本書が特徴的なのは博士課程におけるハラスメントや差別についての言及されている点です。

特に、女性進学者に対する偏見にどう立ち向かえばいいか、人種差別への対応方法、博士課程でのハラスメントへの対処法なども詳細に取り上げられているのです。
日本において、博士課程に関する書籍ではこうしたテーマが扱われることは少ない現状があるからこそこの指摘は非常に重要です。
実際、大学院でのハラスメント事例は修士課程においても課題として取り上げられることが多くあります。
(残念なことに、私もそういった事例を伺うこともあります)
こういった分野についても正しくメスを入れている本書は非常に学ぶことが多いと言えます。
まとめ!博士課程を目指すなら必読です!
本書『博士号のとり方』は、博士課程を目指す人、あるいは現在博士課程に在籍している人にとって非常に参考になる一冊であると言えます。
本書のポイントをおさえておけば、博士号取得に向けてより現実的な道筋が見えてくるはずです。
私自身、本書を読んで「博士号って意外と狙えるかも…」と思えるようになってきました。
博士号取得にいかなくとも、修士課程に進学して修士号を取るうえでも大いに役立つ1冊となっています。
博士号を目指す人も、現在修士課程にいる人も、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか?

☆本書の詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/3DrCadk
大学教授など研究者を目指す場合でなければ博士号取得は「徒労」に終わってしまうことが多い、と個人的には思っています。
特に、働きながら大学院をめざす社会人にとって、3年分の学費と時間をかけても確実に取得できるわけではない博士号はリスクが高いと私は考えるのです(取ったからといって大学教授に確実になれるわけではないですし)。
それに比べ、確実に2年で修了を狙える修士号の場合、取得後のキャリア形成も容易な上、仕事においても大いに役立つように思います。
でも、「リスクがあるからこそ挑戦したい」「博士号取得で自分の努力を証明したい」という方には本書を手に挑戦してみていただければ、と思います。
「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!














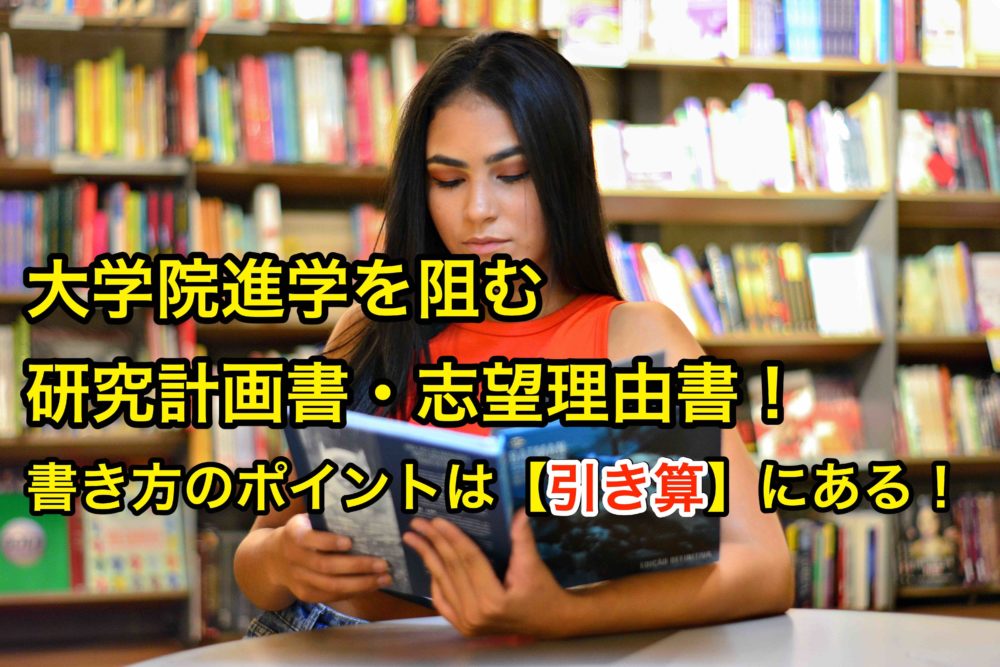









大学院で博士号を取得する。これ、天才でないとできない職人芸だと思われがちですが、大事なのはコツコツと研究を続けること。E・M・フィリップスとD・S・ピューの『博士号のとり方』では平日8時間の研究を3年続けることで博士号は十分取得可能であることを教えてくれます。コツコツ努力が重要なのですね!