目次
そのまま進学するより、社会人経験を経てからのほうが効果的なのが大学院進学!
現代社会において大学院への進学はキャリアを考えるうえの重要な選択肢の1つとなっています。
ですが、どのタイミングで進学するかは人によって異なります。

大きくわけて①大学を出てすぐに進学するパターンと、②社会人になってから進学するパターンの2つがあります。
①のパターンは大学院生の約9割、②のパターンは約1割となっていますが、どちらのほうが効果的なのでしょうか?
今回は『「再」取得学歴を問う』という専門書をもとに、〈社会人になってから進学するほうが効果的〉という事実を見ていきます!
あなたのキャリア形成の参考にしてみてくださいね!
固定モデルか流動モデルか
『「再」取得学歴を問う』という専門書があります。
サブタイトルの「専門職大学院の教育と学習」の通り、専門職大学院での学びをテーマにその効果を検証している本となっています。
(この本の編著者である吉田文先生は私の1回目の大学院修士課程時の指導教員です 笑)

本書では大学卒業後そのまま大学院に進学する大学院生を「固定モデル」、社会人経験を経てから進学する大学院生を「流動モデル」と説明します。

「固定モデル」と「流動モデル」の違い
まず、「固定モデル」と「流動モデル」の違いについて詳しく説明すると次のようになります。
- 固定モデル:大学卒業後、そのまま大学院に進学するモデルです。学部からの延長線として進学し、社会人経験がない状態で大学院生活を送り、学問を深めることが一般的です。
研究者養成を目的とする大学院に多いパターンです。 - 流動モデル:社会人経験を経てから進学するモデルです。社会人として一定の経験を積んだ後、改めて専門的な知識を深めるために大学院に進学するスタイルです。
この場合、社会での経験が学びに大きな影響を与え、現場で得た知識や問題意識を学問に結びつけることで、学びの深さや実践的な価値が増します。
研究者養成を目的とする一般的な大学院は「固定モデル」が多く、「流動モデル」の大学院生は少ない傾向があります。
ですが、社会人の進学も想定している専門職大学院では事情が異なります。
MBAスクールや法科大学院(ロースクール)・教職大学院・公共政策大学院などの「専門職大学院」では学生の約半数が社会人であり「流動モデル」の大学院生も多く存在しているのです。
結論!社会人経験を経た「流動モデル」のほうが効果が高い!
本書『「再」取得学歴を問う』では、純粋な大学院での学習成果について、社会人になってから進学する「流動モデル」の方が学習効果が高いということが示されています。
引用してみます↓
経営系、法科、 教職の3領域において、共通して指摘できることとしては、「流動モデル」の在り方はそれぞれに異なるが、「流動モデル」は「固定モデル」よりも、おおむね大学院での学習による効果を認めることができるということである。(223ページ)
吉田文(2014)「日本の流動モデルについてのインプリケーション」,吉田文 編『「再」取得学歴を問う : 専門職大学院の教育と学習』. 東信堂.219-232頁
ここではMBA(経営管理修士)やMOT(技術経営修士)などの経営系の専門職大学院や法科大学院・教職大学院が説明されていますが、社会人になってから進学する「流動モデル」のほうが学習効果が高く出ていることが説明されています。
続きも見てみましょう↓
「とくに 「流動モデル」のうち、大学院教育を積極的に利用している者、たとえば学習時間が長い、 学習に熱心である、大学院教育に対する満足度が高いなどの者は、より一層、知識・能力を伸ばしているということができる。
それは、経営系のように職業経験と大学院での学習の往還ができる者はもちろんのこと、教職における自由で保証された環境において勉学熱心な者にも、また、試験準備という点において他の学生よりも不利な状況下にある法科の就業継続者などにもみられる傾向である」(223-224ページ)
なかでも社会人になってから進学し「学習時間が長い」「学習が熱心である」「大学院教育に対する満足度が高い」社会人大学院ほど、大学院で多くの成果を得ることが出来ていることが描かれています。
自分の意志で/自分のお金で通っているからこそのやる気。
社会人大学院生の方の経験談を聞くと「大学院時代が人生で一番勉強した時期」と話されることが多いです。

それは学生時代ですとともすれば「親に言われて」勉強していることも多いので受け身なことも多いですが、社会人になってから進学する場合 自らの意志で勉強することになるからだと考えられます。
自らの意志で、さらにいえば自分のお金で進学をしている以上、サボったりダレたりするのは損です。
さらにいえば、忙しい日々の合間で勉強することになる以上、それだけ真剣に勉強することになります。
その上、MBAなどの専門職大学院では自分の仕事に直結した内容を学ぶことになります。
勉強に取り組むことで自分の仕事の成果を高めることができるのです。
学生の場合「この学問が将来役に立つかわからない」と考えてモチベーションが低下する傾向がありますが、社会人になってから進学すれば「これはキャリアアップに絶対役立つ」と実感できるのでモチベーションも高まるわけですね。
固定モデルと流動モデルの違いを実感した私の経験
ちなみに、私自身は大学からそのまま修士課程に進学した後、社会人経験を積んでから再度大学院修士課程に進学しています。
なので「固定モデル」でも「流動モデル」でもあるという例外的な立場にいます(笑)
両方経験しているので、どちらの立場もわかるというのが私の強みと言えるでしょうか。
私は、大学院の修士課程に進学した当初、いわゆる「固定モデル」の学生でした。
学部卒業後、迷うことなくそのまま修士課程に進学し教育学を研究していました。

その後、学校教員と独立してからの塾経営を経て再び大学院に進学することを決意しました。
このように、私は「固定モデル」と「流動モデル」の両方に当てはまっています。
2つの大学院を経験している側として言えるのは、社会人になってから再び大学院に進学したほうが学びの質が高まったということです。
社会人としての経験が学問に深みを与え、単なる知識の習得にとどまらず現実の問題にどのように学んだことを適用するかという視点が加わりました。
(机上の空論ではなくなりました)
いま私は北大の公共政策大学院という専門職大学院に通っていますが、そのなかで学問的な知識を得るだけでなく、実社会での問題解決能力も養うことができています。
このような「流動モデル」での学びのスタイルは、「固定モデル」の学生が抱える「ただ学問を深めるだけ」という印象とは異なり、非常に目的意識が明確であると感じます。
また、実際に自分のお金で学費を支払い、専門的な学びを深めることが、自分のキャリアにどのように役立つかを常に考えるようになりました。
社会人大学院への進学をお勧めする理由
私が最も強く感じていることは、社会人こそ大学院に進学するべきだということです。

特に、専門職大学院では、学んだ知識を即座に現場で活かすことができるため、学びの効果が非常に高いです。
また、社会人としての経験があることで、学問に対する深い理解が得られやすく、学びがより実践的になります。
社会人として、キャリアの方向性を明確にするために大学院進学を検討している方には、目的意識を持って進学することが大切だと強調したいです。
社会人として大学院に進学することでキャリアの可能性を広げることができますよ!
ぜひ、社会人のあなたこそ目的を持って大学院に進学し、学びを最大限に活用してみてはいかがでしょうか?

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!










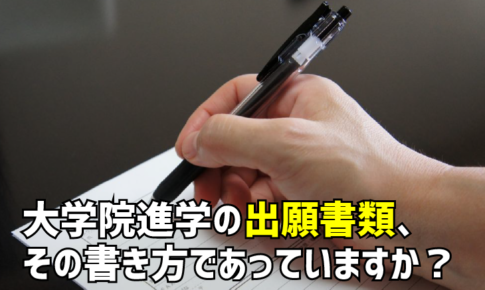



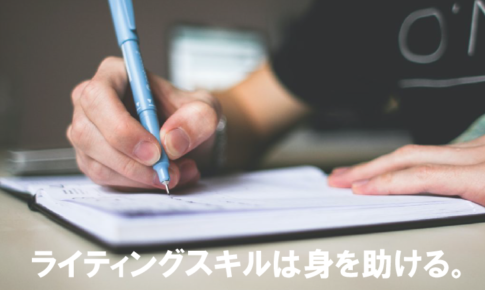









『「再」取得学歴を問う』には、大学卒業後そのまま進学するよりも社会人経験を経てから大学院に進学するほうが効果的であると書かれています。実際、社会人経験によって学びの意義が深まるほか、自分の意志・お金で進学するのでやる気も高まります。なので社会人こそ大学院進学がおすすめですよ!