目次
札幌は生活しやすいけれど…。
私はいま札幌で仕事をしています。

札幌、仕事をするのにも生活するのにも最適な場所であると日々実感しています。
夏は涼しいですし、冬は雪が降っても地下鉄・地下街があるので生活が快適です。
(北海道の他地域だとこうは行きません)
職住近接もできますし、楽しい人たちも多いです。
ただ、札幌には「起業家」「スタートアップ」が少ないのは前から実感しています。
札幌のスタートアップ界隈には、独自の歴史と波があります。
今回は札幌のスタートアップの歩みをたどりつつ、それをもとにキャリア形成において「自分は何をしたいのか」を見つめ直す重要性について考えていきます。
サッポロバレー構想とその波
札幌のスタートアップの歴史を語る上で欠かせないのが「サッポロバレー構想」です。
これは、アメリカのIT企業のメッカ・シリコンバレーに倣い、札幌をソフトウェアやインターネット関連の産業集積地にしようという試みでした。

スタートは1976年の北大マイコン研究会の設立から始まった、と言われています(大久保2020)。
厚別方面には「札幌テクノパーク」がありますが、これは80年代に札幌にIT企業の集積を目指して用意された工業団地となります。
この構想が生まれた背景には、かつてゲーム業界で一世を風靡した「ハドソン」という会社の存在があります。
(桃太郎電鉄やボンバーマンなど、懐かしいですね〜)
ハドソンが最も勢いを持っていた時期、札幌には数多くのIT関連企業が誕生し、「サッポロバレー」と呼ばれるムーブメントが生まれました。
これにより、札幌は一時的にIT産業の中心地として脚光を浴びました。
金融危機とサッポロバレーの失速
ですが1998年に起こった北海道拓殖銀行(拓銀)の破綻といった金融危機が、サッポロバレー構想に大きな打撃を与えました。
特に、ハドソンは拓銀1行に依存していたため経営が一気に傾きました。

この影響で、札幌のスタートアップ企業は相次いで姿を消すことになります。
(なんとももったいない・・・・)
この経験から学べることは、「外部環境への依存はリスクを伴う」ということです。
どれほど環境が整っていても、自社の強みを内側から育てていくことが求められます。
2000年代の再起 クリプトン・フューチャー・メディアの登場
札幌のスタートアップ界が再び注目を集めるのは2000年代に入ってからです。
この時期、音声合成ソフト「初音ミク」で世界的に知られる「クリプトン・フューチャー・メディア」が台頭しました(クリプトン・フューチャー・メディアは1995年創業)。
同社は、札幌を拠点にIT技術とコンテンツを融合させた事業を展開し、札幌の新たなスタートアップの象徴となりました。
クリプトン・フューチャー・メディアは、「No Maps」というイベントを札幌で主催し、スタートアップやクリエイターが集う場を提供しています。
このイベントは、単なるビジネスイベントに留まらず、札幌の文化・創造産業を活性化させる役割を果たしています。
民間の熱意が支える札幌のスタートアップ
札幌のスタートアップ界の特徴として、行政主導というよりも民間企業が主導する動きが活発であることが挙げられます。
2019年からStartup City Sapporoという行政のスタートアップ支援も存在しますが、それ以上に個々の起業家や民間企業が自発的に行動し、新しいビジネスを生み出している傾向があります。
起業もキャリアも「やりたいこと」が鍵
札幌のスタートアップの歴史を振り返ると、一度は「サッポロバレー構想」が成功するも拓銀破綻という外的要因で頓挫し、そこからしばらく「冬の時代」が続いたことが読み取れます。
現在、クリプトン・フューチャー・メディアなど民間企業によるスタートアップ支援の動き以外にも行政系の支援もで始めてきました。
一定の成果は出ているものの、まだまだスタートアップ数は少ない現状が続いています。
この動きを見て、「もっとスタートアップ支援をすべき」という意見も当然ありうるでしょう。
ですが、起業というのは本来「何の支援がなくても自分がやる!」というアツい思いが土台にあるべきだと思います。
私もいちおう「起業」した人間ではありますが、私が塾を起業した際 何らの外的支援を受けたわけではありません。
(当時はあまりに無知だったこともありますが…)
むしろ最初から支援を受けようと思っていたら、いまに至るまで起業しなかった可能性があります。
私の周りの企業家も、スタートアップ支援を経て起業に踏み切ったわけではなく、まずは自分一人でスタートした、という人が多いです。
始めた後でスタートアップ支援を受けるようになった人がほとんどです(受けていない人も多いですが)。
一方で、起業塾や育成プログラムに何度も参加しているのに、なかなか起業に至らない人もいます。
起業支援を大量に受けたにも関わらずあっという間に廃業する人もいます。
この違いは外的支援を最初から当てにするのではなく「何の支援がなくても自分はやるんだ!」というアツい思いの有無だと言えます。
「アツい思い」というと大げさですが、「とりあえずやってみる」という内発的な動機が、長続きするビジネスにつながるのです。

大事なのは自分の内発的動機
私の周りでも起業を目指している人が何人もいます。
中には「札幌には起業家支援が足りない」「スタートアップ支援が不足している」と文句を言う人もいます。
確かに札幌のスタートアップ支援は「まだまだ」なところがあるかも知れませんが、文句を言っていても始まらないといえるでしょう。
支援を当てにするより、まずは自分でなにか1つ結果を出す、自分でサービスを作り上げる気概が大事なのだと思います(自分のことはさておき…)。

キャリア形成における自発的行動の重要性
起業に限らず、キャリア形成においても同じことが言えます。
どれだけ支援制度が整っていても、自分自身が「こうしたい」と強く願わなければ前には進みません。
支援があろうとなかろうと、自分から挑戦し続ける・自分から学び続ける姿勢が重要です。
大学院進学を目指す人、資格取得に挑戦する人、キャリアチェンジを図る人など、道はさまざまですが、最も大切なのは「自分で何かを始める」という行動力です。

自分のアツい想いを大切に!
札幌のスタートアップの歴史から見えてくるのは「自分は何をしたいのか」を問い続けることの大切さです。
周囲の環境や支援はあくまで補助的なものであり、根本的な成長や成功の鍵は自分の内側にあります。
「何があろうと、自分でやり切る」というアツい想い。
その有無がすべてを決めるのです。
これからの時代、キャリアやビジネスの形はますます多様化していきます。
その中で、自分自身の情熱や興味を大切にし、まずは一歩踏み出してみることが、未来を切り拓く第一歩となるでしょう。
環境が整っているかどうか、支援があるかどうかはある意味「二の次」なのです。
もうすぐ新年になりますが、ぜひ新しい思いで挑戦する1年にしていきましょう!!!

☆こちらの「作文起業塾」もどうぞ↓

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!
参考文献
大久保徳彦(2020)「かつて”サッポロバレー”と呼ばれた街が、再びスタートアップシティになるために。」https://note.com/nori_okb/n/n79488faa2252(2024年12月29日確認)











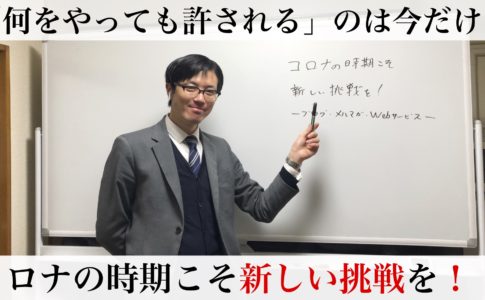



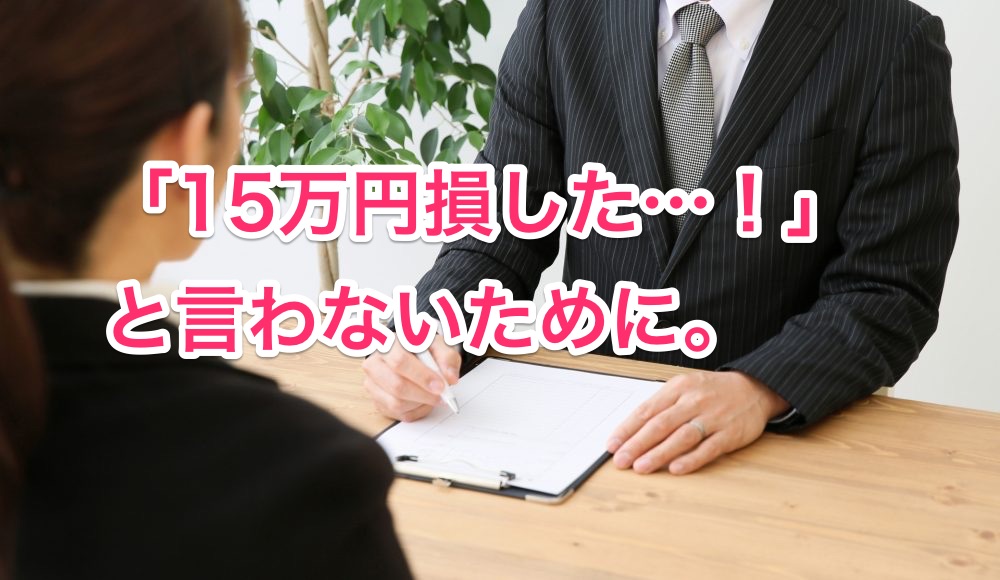

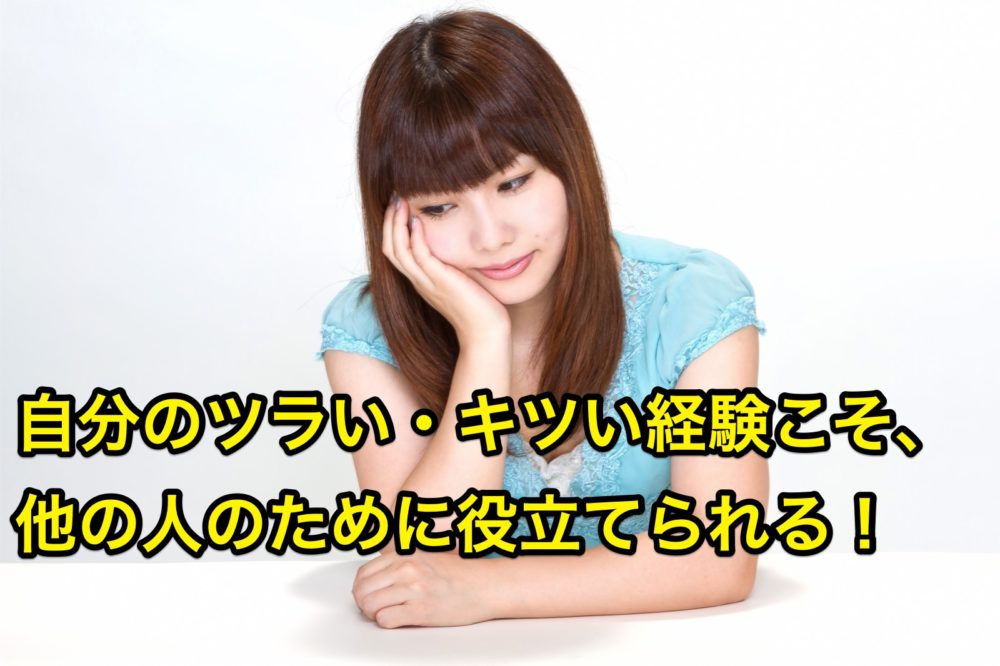






札幌のスタートアップ界隈は「サッポロバレー」の挫折後の
冬の時代を乗り越え、再びの挑戦をしている状態となっています。
ただ、大事なのは外的な支援を当てにするより、
「何があろうと自分でやる!」というアツい想いを持つことです。
キャリア形成も、「自分でやる」想いを大事にしてくださいね!