目次
大学院での学びは大学とどう違う?
「大学院って、大学の延長ですよね?」
時折、大学院についてこういう質問をいただくことがあります。
「大学院って、大学の「すごい版」みたいなものなんじゃないですか?」
「大学と大学院って何が違うんですか?」
こういう質問、伺うことが多くあります。
確かに言葉だけを見ると大学と大学院は似ています。
小学校→中学校→高校→大学というふうに学校の名前が発展していっているように、大学の「すごい版」が大学院であるように見えることも多いです。
ですが、大学と大学院は天と地ほど違っています。
大学と大学院では学び方や求められる姿勢に大きな違いがあるのです。

これを知らずに進学すると痛い目を見ることが多くあります。
(私もそのひとり…)。
特に社会人が大学院進学を検討する際、「大学の延長だろう」と軽く考えていると、入学後に戸惑うことも少なくありません。
この記事では、大学と大学院の学びの違いを解説し、大学院で学ぶ意義について考えていきます。
大学での学びは基礎知識と広い教養の習得が目的
大学の学びは、主に基礎知識の習得と幅広い教養を身につけることが目的です。
授業では講義形式が中心で、学生は教員から知識を「受け取る」立場になります。
試験やレポートの内容も、理解度の確認が主であり、自分の考えをまとめることはあっても、研究という観点では浅い段階にとどまることが一般的です。
また、大学では単位取得が進級・卒業の要件に過ぎず、学生生活の多くは授業や課外活動、友人との交流に時間を費やすことが多いでしょう。
あまり良くないことですが、大学が一種の「就職のための予備校」になってしまっている現状もあります。

大学院での学び:主体的に「研究」を進める場所
一方で、大学院の学びは「主体的に研究を進めること」が大きな特徴です。
修士課程では、特定のテーマについて深く掘り下げ、知識の応用力や問題解決能力を養います。
授業は専門分野に特化した内容が多く、ディスカッションやプレゼンテーション、論文作成が重視されることが一般的です。
立命館大学の桜井政成教授は次のように述べています。
大学院はカルチャーセンターより自動車運転教習学校に近いです。
これは私が一番最初にお伝えしていることです。大学院、特に博士課程というのは、現在、研究者の「普通運転免許」取得のための教習所なのです。
多くの大学が、教員としての採用に必要な最低条件として、博士号の所持を挙げています。
ですから多くの大学院(博士課程)では、博士号を書き上げることが、最終目的となっています。
そのため、自動車運転学校のメタファーを使うならば、細かい交通安全規則(調査方法や論文執筆のルール、研究倫理など)の習得や、運転実技(先行研究を読み、調査し、研究発表し、学術論文を実際に書いてみる)をすることが、大学院で行うもっとも重要な取り組みになります。
なお修士課程では授業が開かれ、それらの単位をいくつか習得する必要がありますが、そのウエイトは修士論文の執筆に比べれば比較的小さなものかと思います。
そしてそれらの授業も「修士論文にどう役立てるか」を目的としていることが多いかと思われます。
社会人で大学院入学を希望される方へ(再掲)
あなたの地元にもあるかもしれませんがカルチャーセンターでは「歴史学」や「文学」などの教養を講師から直接学ぶことができます。
ですが、カルチャーセンターに行くだけでは「教える側」「研究する側」になることはできません。
そうではなく大学院は自動車教習所のように自分の力で研究できるようになる場所なのです。
大学院では自力で研究できるようになることで「教える側」「研究する側」になるためのトレーニングをする場所となっています。
なので「本格的に●●学を学び直したい」と思って大学院に行くと、取れる授業は「研究法」や「ゼミ」の授業ばかりのため「思ってたのと違う」と感じてしまうことになるのです。
もし、あなたが「●●学を基本から学び直したい」思いだけを持っているのであれば、カルチャーセンターに行ったり(大学院ではなく)大学に入り直したりするほうが効率的です。
でも、「自分で論文を書けるようになりたい」「学会発表をしたい」「大学教員になりたい」と思うのであれば思い切って大学院の扉を開くほうがいいのです。
東京大学元教授で著名な研究者である上野千鶴子さんの著書に『情報生産者になる』があります。
単に学問を「受け取る」「学ぶ」側にとどまるのではなく、自分で「知を作り出す」「研究をする」「研究を発表する」側になること、いうならば「情報生産者になる」ことが大学院に行く目的なのですね。

(上野千鶴子さんの『情報生産者になる』、受講生の人にも教科書として提示しています。
たぶんうちの塾だけで数十冊は売上に貢献しているので、筑摩書房から感謝されてもいいような…笑)
大学院は“自分の問い”を見つけ、主体的に解決策を探る場所です。
大学の学びが“教わる”ことであれば、大学院の学びは“自ら学びを作る”ことでもあります。
大学院では与えられた課題をこなすだけでなく、自ら研究テーマを設定し、主体的にデータ収集や分析、考察を進め、成果を論文にまとめる姿勢が求められるのです。
(受身の姿勢だと、何もせずに終わってしまうのが修士課程2年の怖いところです…)

大学院での学習のポイント
ではここで大学院での学習のポイントを見てみましょう!
1. 自ら研究テーマを設定する
大学院では、「何を研究するか」を自分自身で決定することが基本です。
興味や問題意識をもとに独自のテーマを見つける力が必要です。
例えば、社会人が大学院に進学する場合、実務経験から得た疑問や課題意識が研究テーマになることが多いです。
自分の経験をもとに学問を深めることができる点が大学院の魅力です。
2. 批判的思考力と論理的な表現が求められる
大学院では、論文の執筆や研究成果の発表を通じて、自分の考えを論理的に構築し、他者に伝える力が求められます。
「なぜこのテーマを選んだのか?」「そのデータや方法は適切か?」「結果は何を示しているのか?」といった問いに対し、根拠をもとに説明する力が不可欠です。
このときのポイントは「根拠を明確にすること」。
単に自分が考える・感じるだけではなく「●●という論文に〜〜と書かれているから△△といえる」と根拠を明示して説明するのが求められているのです。
こういうロジカルシンキングに関する力を高めておくことが大学院での学びに必須です。
(私も講師としてロジカルシンキング研修を実施していますので、ロジカルシンキングに関してお気軽にご相談ください)
大学と大学院の違いを理解して準備しよう
大学院での学びは決して簡単なものではありません。
しかしその分、得られるものは大きく、キャリアや人生にとって貴重な経験になります。
大学院進学を考えている方は、「自分が何を学びたいのか?」「その学びをどのように活かすのか?」をしっかり考えた上で準備を進めましょう。
大学院は、自分の問いに真摯に向き合い、その答えを探求する場です。
一方的に教えてもらうのを期待するのではなく、自分で何を研究したいかを深めていきましょう!
大学院の中でもMBAスクールやアカウンティングスクール(会計大学院)やロースクール(法科大学院)などの専門職大学院では若干「大学」の色合いが強いです。
研究スキルよりもその分野の専門性や知識・スキルの習得が主目的になっているケースが多くあります。
まとめ
大学と大学院では、学びの目的やアプローチに大きな違いがあります。
大学が「知識を受け取る場」であるのに対し、大学院は「主体的に研究を深める場」です。
特に社会人にとっては、大学院での学びがキャリアアップや人生の転機となることも少なくありません。
大学院での学びは、人生を変える力を持っています。
ぜひ、自分の可能性を広げる一歩を踏み出してみませんか?

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!













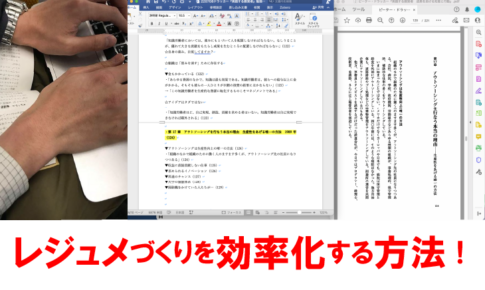

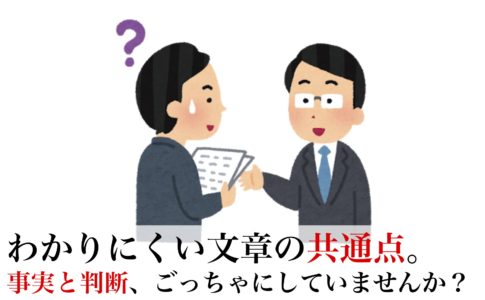








大学院は「大学の延長」ではありません。
大学が「知識を受け取る場」なら、大学院は「主体的に問いを探り研究する場」。
立命館大・桜井政成教授の言葉も紹介しつつ、大学と大学院の違いを解説しました!