目次
日本企業の経営は海外に比べて遅れている?
「日本企業の経営は海外に比べて遅れている」
こういう言い方、
よく聞くことはないでしょうか?
「これからはもっとリーンスタートアップが必要だし、
両利きの経営を実践すべきだ!」
こういうふうに
新しい経営実践の導入が必要だと主張する人も多いです。
(私もよくこう言っていました)
いま私は『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』という
新書を読んでいます。
世の中の風潮に対し本書は
「リーンスタートアップも両利きの経営も、
もとは日本発祥って知ってましたか?」
と水を差します。
一見 海外発祥のように見える経営理念も、
実は日本発祥のものが多いのです。

日本の経営実践は実は世界の先端を走っている!(走っていた)
日本企業って、
人口が減少しているとはいえ、
自由主義諸国としては世界2位のGDP
(中国をいれると世界3位)の経済大国です。
その国の経営技術が
他国に比べて圧倒的に遅れているということは
必ずしもありません。
当然、
「稟議制で決定までめちゃくちゃ時間がかかる」
「終身雇用制が維持不可能になっている」
など様々な課題は存在していますが、
「だから日本企業のやり方は
すべて間違っている」
と言えるほど他国に比べて遅れているわけではありません。
むしろ問題なのは
日本企業がせっかく苦労して作り出してきた経営技術が
経営学の分野で理論化されることがなかった現状を
本書では批判しています。
そして、アメリカの経営学では
他国の先進事例を貪欲に吸収し、
自らのものとできるよう積極的に理論化(コンセプト化)を
行っていることを受け、
日本の経営学関係者に警鐘を鳴らすのです。

リーンスタートアップは日本発祥なのですが・・・。
日本発祥であるにもかかわらず
アメリカ発だと思われている技術に
リーンスタートアップがあります。
まずは小規模であってもいいから
仮にはじめてみるという
プロジェクト遂行方法を
リーンスタートアップといいますが、
リーンスタートアップはもともと日本企業で行われていた
企業慣行をアメリカの経営学者が理論化したものです。

問題なのは
無意識的にリーンスタートアップを実践していた日本企業が、
〈我々のやり方はもう古い!
これからはリーンスタートアップを導入しよう!〉
と、いままで自社でやっていたのを忘れて
新しい手法として取り入れてしまうことです。
その結果、かつてから続いていた会社の強みが
新手法によってズタズタになってしまうという「悲劇」が
あちこちで起きている、というのです。
「読者によっては
「日本はいつもアメリカにしてやられているな」
という感想を持たれると思われる。あくまでも筆者の主観ではあるが、
ここで取り上げきれなかったものを含めても、
全体的に日本は経営実践や経営技術では
健闘しているものの、
コンセプトではほとんどボロ負けに近いという実感がある」
(Kindle版104頁/306頁)
引用した「コンセプト」というのが
ここまで紹介してきた理論化(コンセプト化)ということです。
日本企業では経営実践の中で
優れた手法を大量に作り出していても、
それを抽象化し、理論化することに関して
アメリカに遅れを取ってきたわけです。
その結果、
日本生まれの経営技術がアメリカで理論化され、
それを日本企業が
「アメリカ発の新しい経営技術だ」
と考えて安易に導入してしまうという笑えない現状が
あちこちで起きていると指摘するのです。
経営理念の逆輸入で、日本企業がズタズタに…!
この内容を読んでいて
少し怖くなってきました。
自分たちが無意識でやっていたことが
知らないあいだに理論化されており、
「いままでのやり方は古い!
この新しいやり方を入れよう!」
と高いお金を払ってシステムを入れ、
結果今までと同じことを
違うやり方で行っている可能性があるからです。
…実は私もこれ、覚えがあります。
私はけっこうセミナーに出るのが好きなんですけど、
「これからは●●という新しい手法をやるべきだ!」
という情報を聞き、
いままでのやり方を捨てて
新しい手法を取り入れることがよくあるからです。
しばらくやってみると、
「あれ、これ、以前やっていたのと
同じじゃないの…?」
と気づくことがあります。
新しい手法と思って、
すでにやっていることを
形を変えて取り入れてしまう。
そうなると、
二度手間な上に
セミナー参加料やら
導入費用やらがけっこうかかります。
新しい手法を取り入れる前に
「これ、今までやっていることと同じではないか」
という確認が必要ですね…!
☆岩尾俊兵『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』の
詳細とお求めはこちら。
今回のポイント
新しく何かを導入する際、
「これ、前からやっていないか」の確認を!
なぜアメリカはコンセプト化に強いのか?
日本企業がコンセプト化に弱い一方、
アメリカ企業やアメリカの経営学者がコンセプト化に強い理由について
筆者は次のようにまとめています。
「日本企業は、
経営技術の面で海外に一方的に負けているわけではない。コンセプト化の点で負けることが多かっただけなのである。
ただし、だからといってコンセプト化の力をあなどってはいけない。
日本企業や日本社会にはコンセプト化が苦手な構造的な原因がある。
すなわち、濃密な人間関係に根差したチームワークというある種の強みが、
文脈に依存したコミュニケーションに頼りきってしまうという
状況を作り出してしまったのである。これに対して、アメリカ企業やアメリカ社会は、
移民によって成り立っている。そこには多様な文化的・社会的・言語的背景を持つ人々が集まっており、
その中でなんとか協働を実現しなければいけなかった。
そのため、すべての人間に共通する「理性」「論理力」に
依存したコミュニケーションがおこなわれることが多かったと
考えられる。
文脈に依存できないために、
代わりに論理モデルに依存というわけである」
(Kindle版148頁/306頁)
日本企業はかつて同質性を前提に
同じ日本人・同じメンバー内での「阿吽(あうん)の呼吸」で
コミュニケーションができていました。

そのため、自社の経営技術についても
特に言語化・コンセプト化しなくても
共有ができていたのです。
一方、アメリカ企業は多様な人種・文化を持つ人々が居るため
同質性を前程することができません。
その結果、異なる他者にも伝わるよう
言語化・コンセプト化が不可欠だったのです。

そのため日本企業の経営技術の
言語化・コンセプト化がアメリカで進み、
みすみす日本企業は自らの強みを
奪われていると指摘するのです。
日本企業の言語化・コンセプト化の弱さを
同質性前提の企業文化に求める筆者の説明は
多少強引な気もしますが、
言っていることはもっともだな、と思います。
ともあれ、
日本企業が経営技術コンセプト化が苦手な点について
対策を考えていく必要がありますね…。
ではまた!












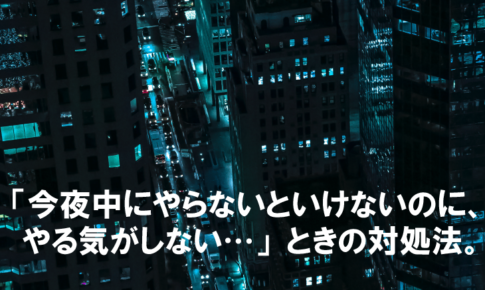
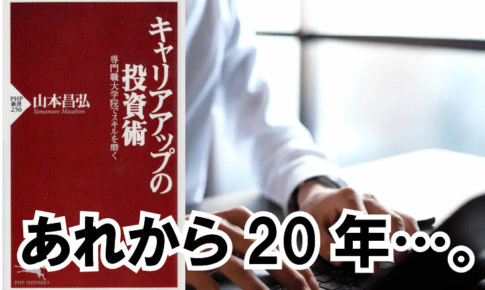
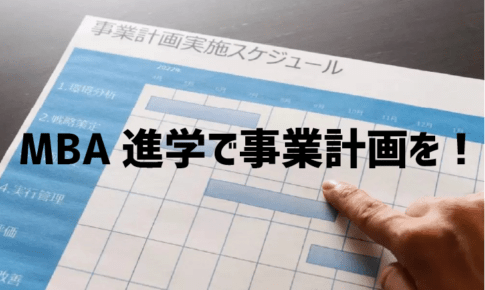








Digest!
岩尾俊兵『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』を読むと
リーンスタートアップ・両利きの経営など
一見アメリカ発祥にみえる経営理念が
実は日本発祥であるという事実を知ることができます。
日本企業が無意識でやっていたことが
アメリカの研究者によって理論化され、
日本に逆輸入される。
残念なのはすでにやっていたことを捨て去り、
逆輸入した理論によって職場がズタズタになる現象が
すでに日本で起こっていること。
この「もったいなさ」に自覚的でありたいですね!