本書は『はじめて読むドラッカー』シリーズ
三部作の2冊目です。
「自己実現編」
「マネジメント編」
「社会編」と続く「マネジメント編」が本書です。
「企業はマネジメントが大事だ」
とよくいいますが、
そもそも「マネジメント」という概念を
作り出したのがドラッカーなのです。
読書会の中で
ドラッカーのマネジメント理論を
一緒に学んでいければ幸いです!
ドラッカー『チェンジ・リーダーの条件』読書会vol.5
2019年1月25日(金)13:00-15:00
@札幌駅前 作文教室ゆう
☆お申込み・詳細はFBイベントまたはこちらからどうぞ!
【範囲】
Part4 3章〜5章(159-190ページ)
☆は藤本のコメントです。
目次
Part 4 マネジメントの基礎知識
3章 目標と自己管理によるマネジメント(159-174)
出典:『現代の経営』(1954)
「第11章 目標と自己管理によるマネジメント」
▼何に焦点を合わせるか(159)
・「組織はチームをつくりあげ、
一人ひとりの人間の働きを一つにまとめて
共同の働きとする。
組織に働く者は、共通の目標のために貢献する」(159)
・「事業が成果をあげるには、
一つひとつの仕事を、
事業全体の目標に向けなければならない」(159)
・「仕事は、全体の成功に焦点をあわせなければならない」(159)
・「組織に働く者は、
事業の目標が自らの仕事に対し
求めているものを知り、
理解しなければならない。
上司もまた、
彼らに求め期待すべき貢献を知らなければならない」(159)
・「これらのことが行われないならば、
組織に働く者は、方向づけを誤る。働きは無駄となる」(159)
・3人の石工の話
→「一流の腕は重視しなければならないが、
それはつねに全体のニーズと関連付けなければならない」(160)
☆石工の例がこの章のポイントですので確認しておきましょう。
・「全体としての事業が、
自らに何を求めているかを理解することを要求する」(160)
・「新しい技術は、一人ひとりの人間が卓越性を追求するとともに、
共通の目標に向けて方向づけされることを必要不可欠とする」(160)
☆単なるスタンドプレーヤーではなく、
共通の目標に向けての方向付けが必要である
▼方向づけを間違えるおそれ(160)
・「マネジメントの階層的な構造が、
危険を大きなものにする」(160)
→「ポストを手に入れるのは、
経理への報告をうまく書けるものだ」(161)という
文句が聞かれてしまうように
・仕事の本質的なものでなく
間接費の削減や経理への数字ばかりが
重視される傾向がある
・「この手の問題の解決には、
組織に働く者の意識を、
それぞれの上司にではなく、
仕事が要求するものに向けさせることが必要である」(161)
,→「経営書の多くが説いているように
行動パターンや姿勢を強調しても、解決は得られない。
逆に、人間関係に意識過剰となって、
問題を大きくしてしまうおそれがある」(161)
▼何を目標とすべきか(162)
・「社長から工場の現場管理者や事務主任にいたる
全員が、明確な目標を持つ必要がある。
それらの目標は、
自らの部門が生み出すべき成果を
明らかにしなければならない。
他の部門の目標達成を助けるために、
自らや自らの部門が期待されている貢献を
明らかにしなければならない。
そして、自らの目標を達成するうえで、
他の部門からいかなる貢献を期待できるかを
明らかにしなければならない」(162)
→「言いかえるならば、
最初の段階から、
チームワークとチームの成果を重視しなければならない」(162)
→「マネジメントとは、
自らの行動によって全体への責任をとるもの、
すなわち石を切ることによって教会を建てる者のことである」
(162)
☆ドラッカーといえば「貢献」の話
・「目標は、事業の繁栄と
存続に関わりのあるあらゆる領域について、
果たすべき貢献を明らかにしなければならない」(162)
・「もちろん一人ひとりの目標は、
長期と短期の観点から明らかにすることが必要である。
そして目標は、事業場の定量化できる目標とともに、
人材開発、働く人たちの仕事ぶりや姿勢、
社会的責任など、定量化できない目標を
含むことが必要である」(163)
▼キャンペーンによるマネジメントは失敗する(163)
・「マネジメントを的確に行うためには、
目標間のバランスが必要である」(163)
・やってはいけないこと:
危機感をあおるマネジメント
キャンペーンによるマネジメント
・「キャンペーンによるマネジメントを行っている組織では」
「本来の仕事の手を抜く下、
キャンペーンをサボって本来の仕事をするか、
いずれかしかない」(164)
▼一人ひとりの目標を明らかにする(164)
・マネジメントとは
「企業全体に対して行うべき貢献について
責任を持つ者である」(164)
・「目標は、その属する上位部門の成功に対して
行うべき貢献によって規定される」(164)
・「マネジメントたるものは、
自らが率いる部門の目標を
自ら設定しなければならない」(165)
→「マネジメントであるということは、
現実に責任をもつことである」(165)
・「目標は、好みではなく、
組織の客観的なニーズによって設定しなければならない」(165)
☆自分の好きなことだけで目標を立てても、
それが組織の貢献につながらないなら意味がない
→「「自らに何が求められ、それがなぜであるか」
「自らの成果は、何によって、いかに評価されるか」を
知り、理解しなければならない」(165)
・「上位の部門の目標設定に参画して初めて、
彼らの上司も、
「彼らに何を期待し、
どれだけ厳しい要求を課すことができるか」
を知ることができる」(165)
・マネージャーズ・レターの例:
部下が次の5つを書く
ⅰ「上司の仕事の目標と、
自らの仕事の目標を明らかにする」
ⅱ「自らに要求されていると思う仕事の水準を書く」
ⅲ「自らの目標を達成するために、
自らが行うべきことを列挙し、
自らの属する部門におけるそのための障害を列挙する」
ⅳ「上司や会社が行っていることのうち、
彼の助けになっていること、
障害になっていることを書く」
ⅴ「自らが目標としたものを実現するために、
今後一年間に自らが行うべきことを提案する」(166)
→この方法が明らかにすること:
①上司が無意識的に部下を混乱させ、
誤り導いていることを明らかにする
②組織の要求と上司の要求の矛盾を明らかにする
☆組織で働いていると、たしかにこの矛盾はたくさんありました。
・「共通の方向づけを行うだけではなく、
間違った方向づけをなくすための努力が必要である」(166)
☆この文の後段を書いている部分が
ドラッカーの強みだと思う。
・下から上へのコミュニケーションが必要:
「上司が進んで耳を傾ける意志をもつとともに、
部下が話を聞いてもらえる特別の仕組みが必要である」(167)
☆はやりの360度評価も重要である
▼自己管理によるマネジメントに必要なもの(167)
・目標によるマネジメントの最大の利点:
「自らの仕事ぶりを自らマネジメントすることが
可能になること」(167)
→「目標によるマネジメントは、
一人ひとりの人間の方向づけや
仕事の一体性のためには不要だとしても、
自己管理によるマネジメントのためには必要である」(167)
☆私のようなフリーランスは
自己管理が本当に必要です
・「目標によるマネジメントの最大の利点は、
支配によるマネジメントを自己管理による
マネジメントに代えるところにある」(167)
・自己管理によるマネジメントには
「そのための道具立てが必要である」(167)
→単に自分の目標を知っているだけでなく、
「自らの仕事ぶりとその成果を、
目標に照らして評価測定することが必要である。
したがって、事業のあらゆる領域について、
明確な共通の評価基準を与えることが必要である」(168)
☆ご自分の目標はなんですか?
その目標をどうやって評価測定できますか?
基準は明確ですか?
ダメな例「今年はなるべく早起きする」
→「いつ起きたら早起きか」という指標が曖昧
→評価測定し、「早起きできたかどうか」を
評価できる、「早起き」の基準を明解にするようにする。
たとえば「7:00までに起きたら早起き」などのように明確にする
・「もちろん、自らの仕事ぶりを評価測定するための情報を
もつことが必要である」(168)
→「情報は、自己管理の道具であって、
上からの管理の道具であってはならない」(168)
・「自己管理こそ、高い仕事の基準を設定する」
「それらの成果をあげるための仕事は、
彼ら自らが、そして彼ら自らのみが管理する」(170)
・「人は、自らの仕事についてあらゆる情報をもつとき、
初めてその成果について全責任を負うことができる」(170)
☆自分のやることについて知識・情報を得ていくことで
はじめて自分としてやるべきことができるようになります
▼報告と手続きに支配されるな(170)
・「自己管理によるマネジメントを実現するには、
報告・手続き・書式を根本的に見直すことが必要である」(170)
・報告と手続きの誤った使い方3つ
(1)手続きを規範とみなすこと:
(2)手続きを判断の代わりにすること:
→手続きが有効なのは判断が不要な時
☆手続きどおりにするのは官僚的になってしまう
(3)上からの管理の道具として使うこと:
→書類を書くことに追われ、
本来の仕事ができなくなる
☆学校教員の仕事がまさにこれです
・「報告と手続きの数は最小限にとどめ、
時間と労力を節約するためにのみ使うべきである。
それは、可能なかぎり簡明なものにとどめておくべきである」(172)
☆とても1954年の本とは思えない現代性をもっている
・「あらゆる企業が、
現在使っている報告と手続きのすべてについて、
本当に必要かどうかを
定期的に検討する必要がある」(173)
・「報告と手続きは、
記入する者自身にとっての道具でなければならない。
記入者を評価するための道具にしてはならない」(173)
→「確実にする唯一の方法は、
彼ら自身が成果をあげるうえで必要な書式と報告以外は、
いっさい書かせないことである」(173)
▼個人の目標と全体の利益を調和させる原理(174)
・「今日必要とされているものは、
一人ひとりの人間の強みと責任を最大限に発揮し、
彼らの視野と努力に共通の方向性を与え、
チームワークを発揮させるためのマネジメントの原理、
すなわち、一人ひとりの目標と全体の利益を調和させるための
マネジメントの原理である」(174)
→「これらのことを可能にするゆういつのものが、
目標と自己管理によるマネジメントである」(174)
→「誰かの意志によってではなく、
自ら行動しなければならないという
自らの決定によって行動させるようになる。
言いかえるならば、自由な人間として行動させる」(174)
☆心理学で言う内発的動機づけである。
・「目標と自己管理のマネジメントこそ、
まさにマネジメントの哲学と呼ぶべきものである」(174)
→「成果の達成を確実なものにするために、
客観的なニーズを一人ひとりの人間の目標に変える。
心の自由を実現する」(174)
4章 人事の原則(175-184)
出典:『マネジメント・フロンティア 明日の行動指針』(1986)
「第13章 経営管理者の人事 その基本原則」
▼一流の人事はどこが違うか(175)
・「マネジメントは、人事に時間をとられる。
そうでなければならない。
人事ほど長く影響し、かつもとに戻すことがむずかしい
ものはない」(175)
→成功が1/3、まあまあが1/3、失敗が1/3
・人事の成功を10割に近づけることは可能である
しかし、こと営業に関してでは 「それどころか、言語的知能テストの成績が高い者は むしろ大事なのは
統計データ的には
「全般的なビジネス特性」は
「高学歴」で「ハキハキ対応」できる人が高いそうです。
「高学歴」で「ハキハキ対応」できる能力は
そんなに影響しません。
むしろ営業成績が低い、という結果すら
得られているのである」
(『統計学が最強の学問である ビジネス編』
Kindle版No.1426/4016)
「営業という仕事に興味と適正があり、
誠実で仕事を最後まで達成しようとする」
(同No.1437/4016)人のほうが
営業としての成績が高く出ることが
統計的に明らかになっているそうです。
▼共通する4つの原則(176)
(1)「ある仕事につけた者が成果をあげられなければ、
人事を行った自分の間違いである」(176)
☆それくらいの真剣さで行う必要がある、ということ
(2)「兵士には有能な指揮官をもつ権利がある」(176)
→責任感のある者が成果を挙げられるようにする
(3)「人事は正しく行わなければならない」(176)
(4)「外部からスカウトしてきた者に、
初めから新しい大きな仕事を与えてはならない」(176)
☆太平洋戦争中の日本の人事は
けっこうめちゃくちゃだったみたいですね。
▼踏むべき手順(177)
(1)「仕事の中身をつめなければならない」(177)
→役職や地位が変わらなくても、
「仕事の中身は、つねに、そして思いもかけず
変わっていくことを知っておかなければならない」(177)
☆意味なくポストに人をあてがうことを行うのでなく、
「このポストにはどんな職務内容を与えるか」
を考える必要がある
(2)「複数の候補者を検討しなければならない」(178)
→仕事には相性があるので、
つねに3〜5人から検討するようにする
(3)「強みを中心に検討しなければならない」(178)
→「重要なことは、何をできないかではない。
強みは何か、その強みはその仕事の中身に
合致しているかである」(178)
→「弱みを中心に見ていたのでは、
いかなる成果も生み出せない。
成果を生むものは、強みである」(178)
(4)「候補者について知っている者から、
考えを聞かなければならない」(179)
→「人の評価に際しては、
ひとりだけの判断は無効である」(179)
(5)「新しいポストにつけた者に、
仕事の中身を理解させなければならない」(179)
→3ヶ月したあとに、
「新しいポストで成功するには
何をしなければならないか」(179)を聞いていく。
「これまでやってきた仕事のやり方では、
新しいポストはこなせない」(180)と言っていく
→「このプロセスを踏まないかぎり、
新しいポストについた者の仕事ぶりが満足できなくとも、
責めることはできない。自らを責めるべきである。
人事を行った者として、
行うべきことを行っていないからである」(180)
・人事担当者としてやるべきこと:
「新しいポストが、それまでとは違うやり方、
考え方、人との関わり方を要求しているということを」(180)
相手に理解させること。
▼失敗したらどうするか(181)
・これらのプロセスを踏んでも、
人事の失敗はなくならない
・「専門分野のマネジメントの人事には
リスクがつきものである」(181)
→「したがって、昇進や異動がうまくいかなかったときには、
ただちに再異動させる必要がある」(181)
→「間違った人事をされてしまった者を、
そのままにしておくことは温情ではない。
意地悪である」(181)
☆この辺、日本的な組織でもよくある話。
・必ず失敗するポスト(「後家づくり」)の存在に気をつける:
「優秀な者さえ失敗させてしまうポストは、
組織が急速に成長したり、
変化したりしたときに現れる」(182)
→「前のポストで立派な業績を上げていた二人の人間が、
たて続けに失敗したときには、
「後家づくり」のポストと見なければならない」(182)
→その時は「ポストそのものをなくすべきである」(182)
▼人事には姿勢が現れる(182)
・「マネジメントの究極の手段は、人事である」(182)
・「むかしから知られているように、
組織の人間というものは、
他の者がどのように報われるかを見て、
自らの態度と行動を決める」(183)
→「したがって、仕事よりも追従のうまい者が
昇進していくのであれば、
組織そのものが、業績のあがらない追従の世界となっていく」(183)
・「公正な人事のために全力を尽くさないトップマネジメントは、
組織の業績を損なうリスクを冒すだけではない。
組織そのものへの敬意を損なう危険を冒していることになる」(183)
☆日本海軍では山本権兵衛がいたからこそ、
単に「薩摩出身」というだけで地位が上がっていた軍人を
撤廃することができました。
結果、合理的な判断を行える組織となりました。
しかし、日本陸軍には山本権兵衛的な人がいないため、
明らかに勝てない戦争に突入してしまうこととなりました。
(司馬遼太郎『坂の上の雲』の指摘より)
☆ビジネスパーソンの一番の「関心」は
今も昔も「人事」です
5章 同族企業のマネジメント(185-190)
出典:『未来への決断』(1995)
「第4章 同族企業経営」
▼生き残りを左右する原則(185)
・「先進国では、企業の大半を同族が所有し、
マネジメントしている。
同族経営は、中小企業に限らない。
世界最大級の企業もある」(185)
☆言ってしまえば、
ユニクロも同族経営の会社です。
ジャパネットたかたもそうですね。
ベネッセ(旧 福武書店)もそうです。
・「ところが、マネジメントについての本や講座のほとんどが、
経営のプロによってマネジメントされる上場企業だけを
扱っている」(185)
・「同族企業と他の企業の間に、
研究開発、マーケティング、経理などの仕事で
違いがあるわけではない。
しかし、同族企業はマネジメントの構成に関して、
いくつかの原則を必要とする」(185-186)
▼できの悪いものは働かせるな(186)
(原則1)「少なくとも同等以上に働く者でないかぎり、
同族企業で働かせてはならない」(186)
→「できの悪い甥を働きにこさせて給料を払うくらいならば、
働きに来ないよう金をやったほうが安くつく」(186)
▼トップマネジメントに一族以外からも採用せよ(187)
(原則2)「トップマネジメントのポストの一つには、
必ず一族に属さない者をあてなければならない」(187)
→「一族に属しておらず、
仕事と私事を混同することのない尊敬すべき人間を、
トップマネジメントのなかに
最低ひとりは入れる必要がある」(188)
▼専門的な地位には一族以外の者も必要(188)
(原則3)「専門的な地位には一族以外の者を必要とする」(188)
▼適切な仲介人を外部に用意せよ(189)
・この3原則を守っていても問題が起こることがある:
特に後継者問題
→「解決の方法は一つしかない。
すなわち、後継者問題に関わる意思決定は、
一族の者ではなく、
しかも利害関係をもたない外部の者にゆだねることである」(189)
・「しかし、後継者問題が深刻化してから
外部の人間を招いても手遅れである」(190)
(原則4)「同族企業は継承の決定を迫られるはるか前、
できれば一族の人間が後継者について
それぞれ考えをもつようになる前に、
適切な仲裁人を外部に見つけておかなければならない」(190)
・「中堅企業の多くは同族企業である。
したがって、社会にとって、
同族企業を支援し、
その継承を容易にすることは、
起業家精神の観点からも重要である」(191)
・「今日、前述の4つの原則を守り、
その根底にある理念を理解している同族企業は
ほとんどない。
その理念とは、同族企業にせよ、
それを所有する一族にせよ、
一族が同族企業に奉仕するときにのみ、
生き残り、繁栄することができるということである。
一族に奉仕すべくマネジメントしたのでは、
同族企業も一族も、生き残り、繁栄することはできない」(191)
・「「同族企業」という言葉で鍵となるのは、
「同族」のほうではない。「企業」のほうである」(191)
☆黒字なのに後継者がいないため
会社を潰さなければならない会社が60万社あると言われています。
事業承継が本格的に議論されているのです。
その事からも、ドラッカーに
先見の明があることがわかります。
☆札幌の経営者のうち
社長の勉強会に出ている人は
基本的に「二代目・三代目」社長が多い印象があります。
☆ちなみに、『ドラえもん』の
スネ夫のお父さんは社長です。
スネ夫も将来社長なのは
「同族企業」だから、ということになります。

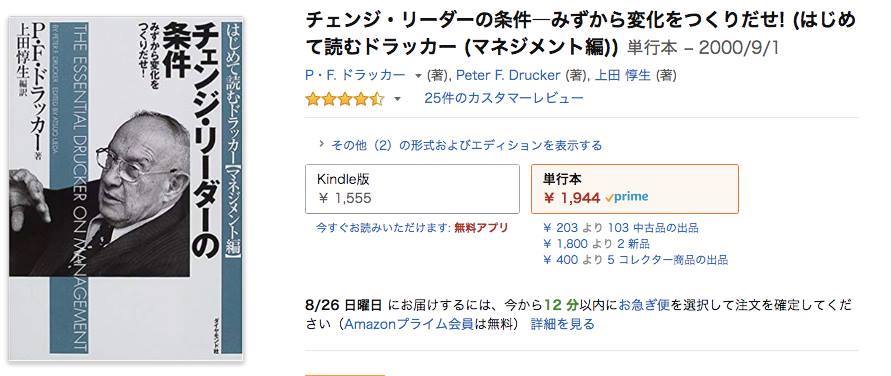








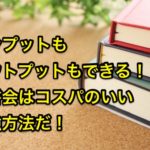
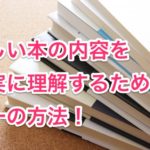
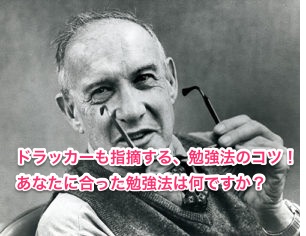
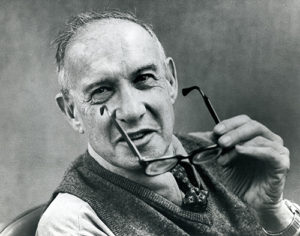
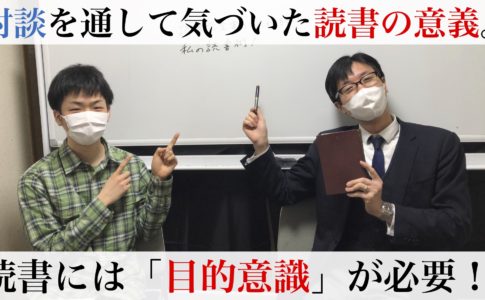

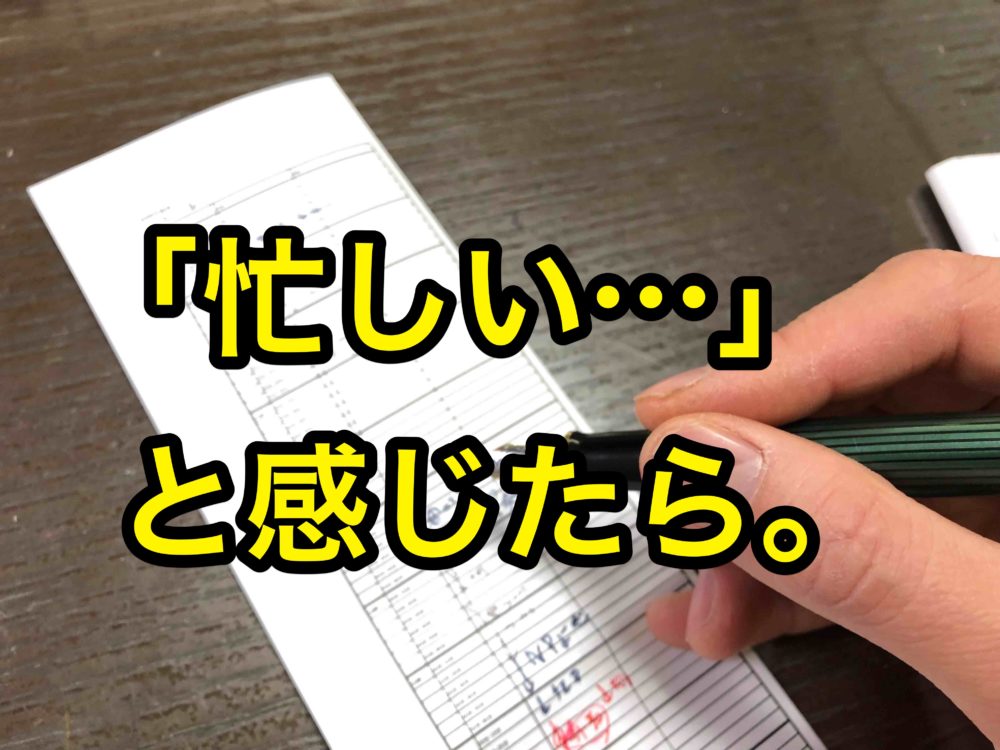
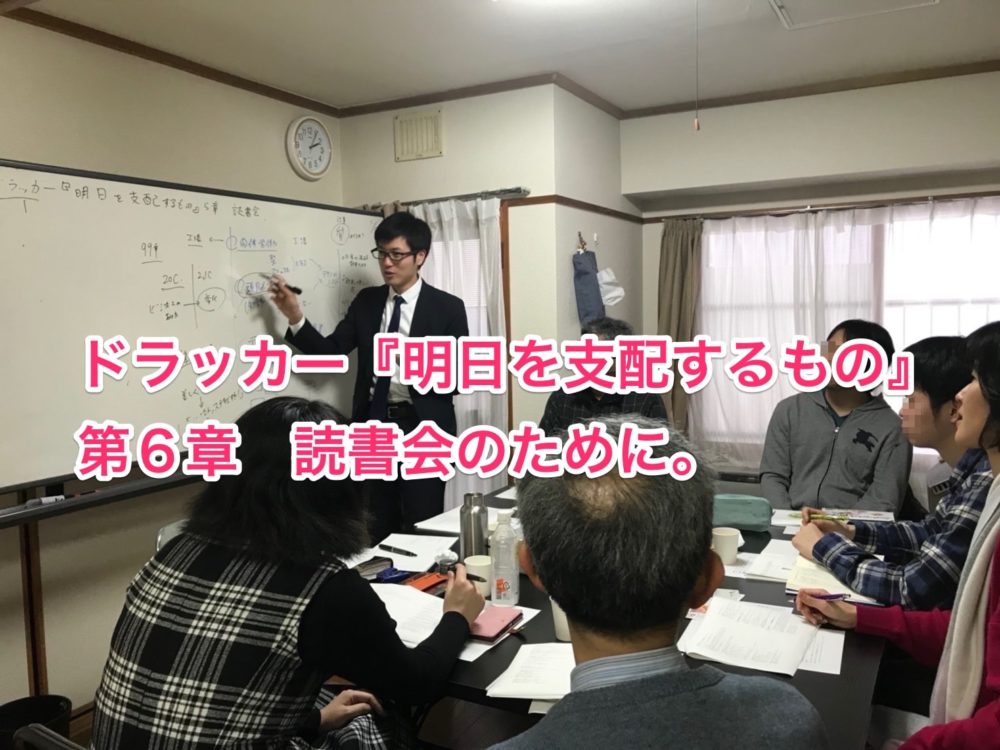

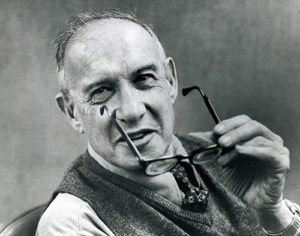






コメントを残す