目次
「論文って、どう書いたらいいかわからない…」解消法!
大学院に入ると、修了時の修士論文や授業レポートなどで論文を書くことが増えます。
なかには学会誌に投稿するための論文を執筆する人も多くいらっしゃいます。

論文を書くことで自分の研究を多くの人に知ってもらうことができます。
また、論文を何本投稿しているかが自分の学術業績となっていきます。
ある意味で大学院修士課程は「修士論文をはじめとする論文の書き方を学ぶ」場所であると言えます。
でも、どうやって論文を書けばいいか学ぶのはなかなか大変です。
実際、論文を書く際 多くの大学院生が「どこから手をつければよいのか分からない」と感じることが多いです。
特に、初めて本格的なアカデミックライティングに取り組む場合、文章構成や引用をどうすればいいか途方に暮れることもあります。

そこで、本記事では論文執筆のための実践的な方法を紹介します!
ぜひ最後まで読んでみてください。
まずは優れた論文をお手本にする!
論文執筆の第一歩として、自分が書こうとしている分野で著名な論文を探し、それを徹底的に分析することをおすすめします。
これは『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』でも推奨されている手法でもあります。

☆本書の詳細とお求めはこちら→https://amzn.to/4bdgjCK
なお、『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』では論文の書き方を科学的・再現可能な方法で分析しています。
読んだら絶対トクするおすすめ本ですよ!
お手本論文の分析方法3ステップ!
では、ここからはお手本とする論文を分析する方法を3ステップでお伝えします!
『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』では以下の手順で論文に引用された文献の分析を行うことが提唱されています。
(1)文献表または注釈にある引用文献を種類別に色分けする
「文献表または注釈にある引用文献を研究書とジャーナル論文で2色に分けてハイライトしよう。
つまり、引用元が一冊の書籍か、雑誌などに載った単体の論文かという違いである」(Kindle版118/246ページ)
まずは蛍光ペンなどのマーカーを持ち、引用文献が書籍か論文かの色分けをしていきます。
「この作業から得られるのは、その既出版の論文が最終的に何本の論文と何冊の研究書を引用して完成したのかについての数値的なデータである」
「その相場が、あなたが論文を書くときに書籍何冊・論文何本を引用できればよいのか、つまりどのくらい読めばいいのかについての指標となる」(119/246ページ)
この作業により、どういう種類の文献をどれだけ引用すればいいかを知ることができます。

(2)本文中の引用箇所を色分けする
文献表や注釈に塗ったマーカーと同じ色を、今度は本文での引用箇所に対して塗っていきます。
「たとえば文献一覧または注釈で、書籍を赤、論文を青でハイライトしたとすると、こんどは本文中の引用箇所を同じ色でハイライトしてほしい」(120/246ページ)
このメリットとして次のことが挙げられています。
「この作業から手に入る情報は、それぞれの資料からどのくらいの分量を本文に組み込んでいるのかについての数値的なデータだ」(120/246ページ)
こうすることでどれくらいの引用を行っているかを体感的に知ることができるのです。
(3)引用元の文献を実際に読んでみる
「本文のハイライトを終えたら、参照されている文献そのものを可能な範囲で手に入れ、書籍な論文のどの箇所から引用しているのかを調べてほしい」(120/246ページ)
お手本論文が引用している文献を実際に用意し、どこから引用しているかを調べていきます。
「うわ、大変そう…」と思うかもしれませんが、論文ではタイトルだけではなくページ数も書かれているのでそこだけ見ればいいので意外と楽です。
引用しているのが論文のどういう場所なのか(序文なのか本文なのか結論なのか)などを確認していきます。
この作業を通じて、論文執筆に必要な文献の選び方や適切な引用方法が見えてくるのです。

お手本論文から学ぶことはたくさんある!
『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』ではこの項目のあと、お手本論文でのアーギュメント(主張)を読み取る方法について解説が続いていきます。
お手本論文がどのように議論を進めているのか。
どういう分析方法を用いているのか。
こういった部分を徹底的に分析していくことが良い論文を書くためのポイントになります。
大学院のゼミではお手本論文の精読が行われることがありますが、お手本となる論文を細かく読んで分析することを通して論文の書き方が身についていくのです。
私も1回目の大学院(早稲田大学大学院 教育学研究科)のゼミでこういう分析を行ったのが懐かしいです。
いきなり論文を書くのは大変ですが、まずはお手本論文を細かく分析してみることで書き方のポイントが身についていきます。
ちょっと大変かもしれませんが、やった分必ずメリットがありますので挑戦してみてくださいね!!
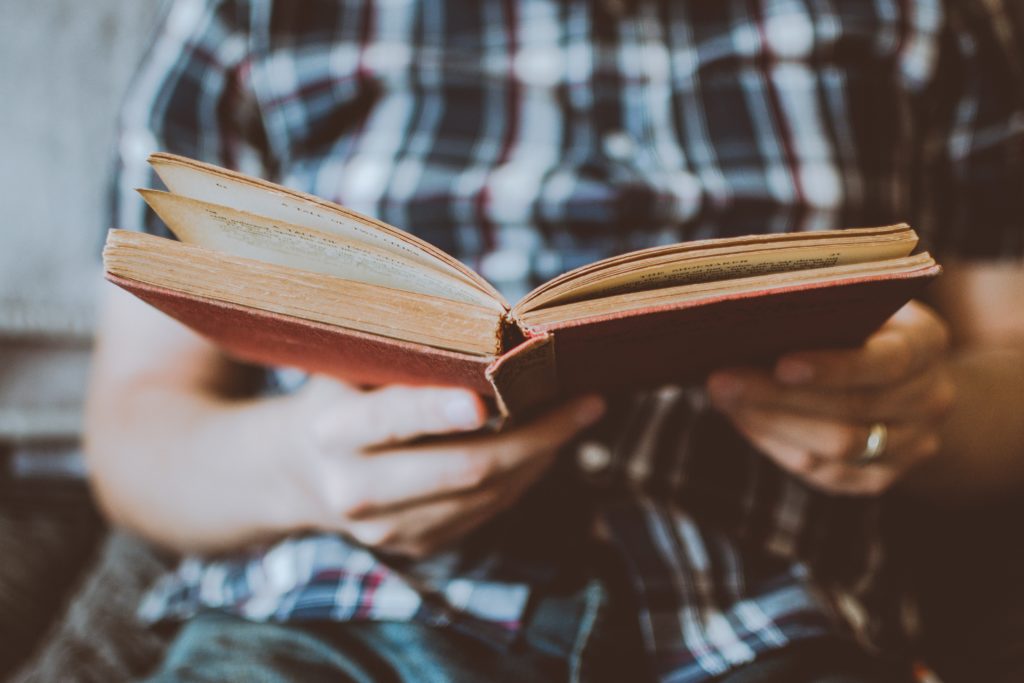
お手本論文の探し方。
「でも、お手本論文ってどうやって探せばいいかわからない…」
そういう方もいらっしゃるかもしれません。
お手本にする論文を探すには、以下のような方法があります。
- (1)Google Scholar や CiNii Articles でキーワード検索する:
無料のデータベースであるGoogle ScalarやCiNii(サイニー)などでキーワード検索をすると関連する論文が簡単に見つかります。
なかには無料でPDFが読める論文もありますので、見つかったもの・一致度が高いものを実際に読んでみてください。 - (2)自分の研究分野の学会誌(例:日本教育学会・日本教育社会学会)に掲載されている論文を読む:
自分が所属したい学会や興味のある学会では毎年学会誌が発行されています。
言うならば「論文集」ですね。
この論文集に載っている論文、なかでも「原著論文」(査読付きの論文)は質が高い事が多いのでお手本にしてみることをおすすめします! - (3)指導教員や先輩からおすすめの論文を教えてもらう:
ふつうに教員や先輩からおすすめの論文を教えてもらうのもいいでしょう。
こうやってお手本論文を見つけ、まずは気軽に分析してみてください!!
まとめ
論文を書く際には、まずはお手本論文を見つけ一度分析してみるのがおすすめです。
特に、論文の引用の仕方などを色分けして視覚的に分析することで論文を書く力(アカデミックライティングのスキル)を大きく向上させることにつながります。
ぜひ論文を書く「前」にお手本論文の分析をしてみてくださいね!!!
そうすることで効率的に執筆を進めることができるはずです。
最終的には時間のモトも取れますので、ぜひ時間を作ってやってみましょう!!!
応援しています!

「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!










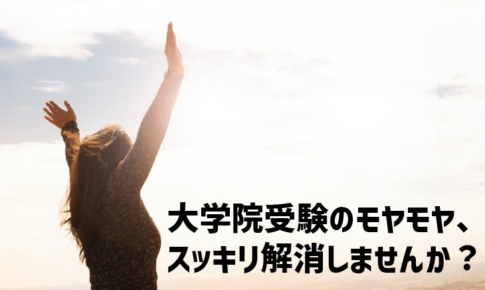



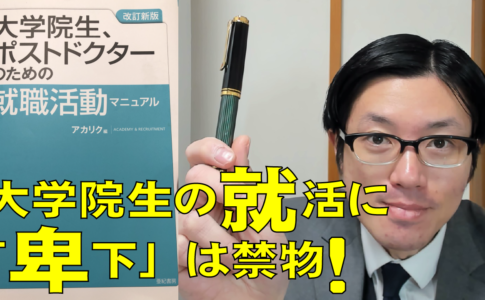

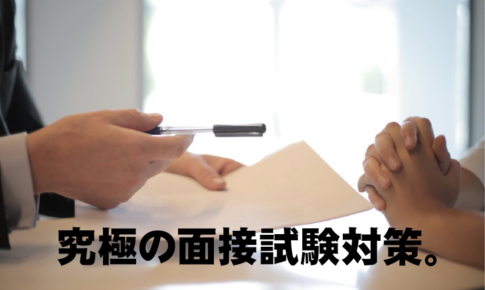
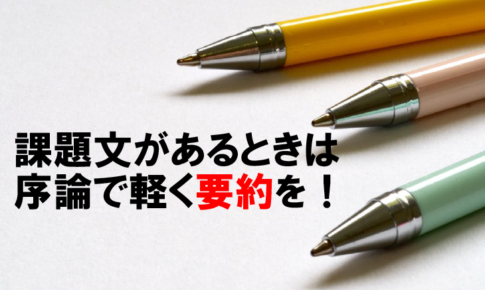






「論文の書き方がわからない…」。そんなときはお手本になる論文を探し、徹底的に分析してみましょう!『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』にあるように参考文献に書かれている論文を色分けし、本文でどう引用されているか、もとの論文のどの箇所からの引用かを調べてみるのがおすすめです!