「絶望の大学」のなかにも、希望はある!
今後をより良くする取り組みをするため、
ときにはマクロな視点の本も読む!
目次
失敗し続けてきた日本の「大学」
☆本日の内容は動画でもお伝えしています。
動画にしかない内容もありますので
気軽に聞き流してみてください。
いま吉見俊哉さんの
『大学は何処へ』を読んでいます。
この本、とても面白いです。
この本の内容を
一言でいうと
「日本の大学は
戦後以来一貫して
【失敗】し続けてきた」
ということ。
ここでは代表的な「失敗」を3つ
あげていきます。
(1)エリート教育の「失敗」
戦前の日本には
エリート層対象の教養教育の場面である
「旧制高校」がありました。

吉見さんは
旧制高校を母体にした
リベラルアーツ・カレッジを作っていれば
日本の戦後教育はさらに違ったものになった、
と指摘します。
…ところが、GHQからの圧力と
大学教員側の「ポスト」「利権」獲得の思惑が一致し、
あらゆる教育機関を
一緒くたにして
新生大学へと移行してしまいました。

結果、これまで「大学」に値しなかった学校が
「大学」となるほか、
本来的な意味での「大学」だった場所に
違う目的が入ってきてしまいました。
…そのため戦後の日本は
エリート層向けの教育機関がなくなり、
大学教育の「大衆化」が
進行することとなりました。
表面的に見れば
「平等」の実現になりますが、
現在に至るまで
日本のエリート層が人材不足で
悩むことになってしまいました。
(官僚や政治家の「劣化」が時折言われますが、
その遠因には大学の「大衆化」が挙げられます)
(2)大学教育と職業教育の接続関係の「失敗」
日本の場合、
大学教育と仕事現場との
乖離が甚だしいことは
以前から指摘されていました。
だからこそ、
一昔前では「企業内教育」が
重視されていたわけです。
大学はレジャーランドとして
遊んでいてもよく、
職場に入ってから
会社の中で職場教育を積めばいい。
そういう発想が
これまで企業の世界で支配的でした。
終身雇用制が維持されていた時期には
この発想は成立していました。
ところが。
いまや全く成り立たなくなって
しまいました。
…この指摘がされて
はや20年が過ぎますが、
それでも一向に状況は変わらないまま、
です。
その点でも「失敗」し続けているわけです。
(3)若手研究者の職が不安定であるという「失敗」
以前から言われる
「若手研究者の不遇」についても
指摘がなされています。
ちょっと引用します↓
「日本社会全体では、
25~34歳の男性の非正規雇用社の割合は
10~15%程度であるのに対し、
大学職の非正規率は50%を超える。さらに、博士課程修了者の1年半後の状況では、
雇用されている場合でも6割が任期制だという。つまり、大学進学者の中でも成績が良く、
大学院入試に合格して博士課程まで進み、
苦労をして論文を書きあげた若手研究者が、同世代の若者たちよりもはるかに不安定な
雇用環境に置かれているのだ。不条理としか言いようのない現実がここにある」
(229−230頁)
ここの内容、
生々しいですね…。
実は私が「博士課程進学」を断念した理由も、
こういう
〈苦労して博士号をとっても
非正規雇用しかない現実〉
を先輩たちの姿から知ったため、
…でもあります。
吉見俊哉さんの
『大学は何処へ』を読むと
「絶望の大学」
という言葉が思いついてしまいます。
☆『大学は何処へ』の詳細とお求めはこちら↓
今回のポイント
今回のポイントです。
今後をより良くする取り組みをするため、
ときにはマクロな視点の本も読む!
失敗の中での「希望」
『大学は何処へ』において
日本の大学教育は
一貫して「失敗」し続けてきたと
指摘されています。
しかしながら、
この「失敗」乗り越え、
今後変化していける「チャンス」を
示しているものが2つある、
とも指摘されています。
それが「通信制大学」と「高専」です。
通信制大学は
日本において社会人が
「学び直し」をする際に活用される
中心的な機関となっています。
働きながらでも、
また地方にいても学べるという点で
今後の「リカレント教育」(社会人の学び直し)の
柱となる存在である、とも指摘されています。
一方、「高専」は
吉見さんが注目する「旧制高校」とも
近しい特徴を持っています。
それは単なる「専門教育」を行うだけではなく、
リベラルアーツ的な学びを
計画的に学習する制度が
整っている点です。
「絶望」の中にも
まだ希望はあるのです。
現実を「直視」するからこそ、対応策が見つかる!
…今回、現在の日本の大学が抱える状況を
『大学は何処へ』をもとにまとめてみました。
私は塾経営の立場で
大学進学や大学院進学を
応援する立場でもあります。

ですが、現状の大学・大学院を
手放しで礼賛することなく
「どういう大学教育が望ましいか」
を考え続ける視点を大事にしたい、
と思っているのです。
そのためにも、
現在の日本の大学の
「絶望」を直視することでしか
対応することはできないように思うのです。
私も、こういった現状を直視した上で
「どうやったらよいか」
「どうやって対応していけるか」
考えていきたいと思っていますので
どうぞ今後ともよろしくお願いします!
ではまた!







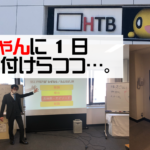

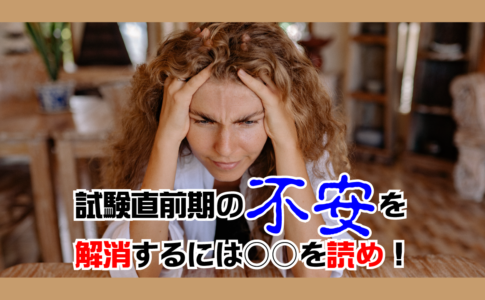
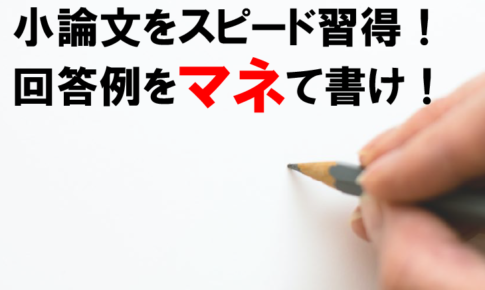

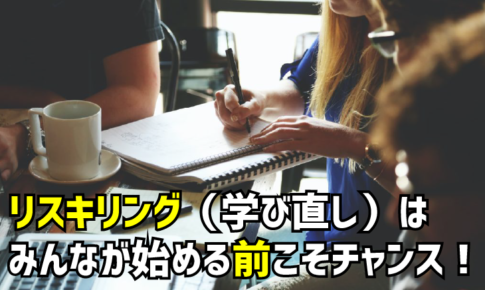










コメントを残す