目次
AIを使った小論文試験対策だと不十分な理由!
「小論文って、AIでも添削できる時代ですよね?」
最近、こういった声をいただくことが増えてきました。
ChatGPTなど文章生成AIを使うと、小論文の原案を作ってくれたり文章のアドバイスをしてくれたりします。
大学院受験に求められる小論文執筆の練習などもしやすくなっています。
たしかに、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場によって、小論文の下書きを作ったり、アイディアを広げたりすることはとても簡単になりました。
実際、私の塾でも、ChatGPTを活用して小論文対策を進めている場面はたくさんあります。

ですが――。
小論文指導において、「人間でなければできないこと」は、今の段階でも数多く残されています。

今回はAI時代においても人間の講師から小論文対策の仕方を教わったほうがいい理由について解説します!
AIが得意なことと、人間でなければ難しいこと
ChatGPTなどの文章生成AIでは小論文のテーマを入力することで「それなり」の原稿を作ってくれます。
出題されたテーマに対し、「このテーマでどういう構成にすれば良いか?」という問いにも的確に応えてくれます。
論理展開もある程度整っています。
ですが、ChatGPTなどの文章生成AIにできるのはそこまで、です。
「その人が書いた原稿のどこに課題があるか」
「どのように直せば、その人らしさがより伝わる文章になるか」
という「書き手」自身に関わる内容のアドバイスについて、現時点(2025年)では人間の指導が不可欠だと感じています。
また、生成AIを使うとそれこそ数秒で原稿が作成されますが、出来上がった原稿を見ても「試験当日どのように考えたら小論文の答案を書くことができるか」はわかりません。
まして、60~120分という制限時間内でどのような手順で原稿を書けば良いかもアドバイスしてくれないのです。

「どこを直すか」「どう書き直すか」は人間の講師のアドバイスをもとに!
小論文は単にテーマについて知識を並べればいいものではありません。
むしろ大切なのは、「書き手がそのテーマについて、どのように考え、どういう経験からその考えに至ったのか」という“個人の思考”の部分です。
さらに限られた時間内で答案を最後まで書ききる力も求められています。
私は高校教員時代から数えると14年近く小論文指導をしています。
単に知識を並べるだけでなく、書き手の考え方・人生観も伝わる論理的な回答を作り上げるアドバイスを受講生に提供してきたわけです。
単に文章を見て「ここは言い回しを変えましょう」と指摘するだけではなく、
- 書き手がどういう経験をしてきたのか
- どのような価値観や問題意識を持っているのか
- それをどう文章に組み込めば、相手(面接官・試験官)に伝わるのか
といった点に目を配る必要があります。
さらには限られた時間内でどのような手順で組み上げれば良いかもアドバイスする必要があります。
書き手がどのように自分の経験を言語化し、それを時間内で論理的にまとめる技法を伝えられることこそ、人間の講師による小論文指導の強みだと私は考えています。

手書き原稿だからこそ見える「書き方のクセ」
大学院受験本番では大抵の場合「手書き」で原稿を作り上げることが求められます。
スマホやタブレット・パソコンで原稿を作ることが多くなった現代社会において手書きで原稿を書くのには、文章構成の仕方・情報整理の仕方に独特なノウハウが必要です。
さらには誤字脱字・原稿用紙の使い方などを正しく知らなければ試験当日の点数が下がってしまいます。
ChatGPTなどの生成AIはこのような点のアドバイスを行うことはできません。
1対1大学院合格塾では毎回 講師が1対1で小論文試験のアドバイスや添削を行っています。
手書き原稿をもとにするからこそ「どう書くと小論文の回答がよりよくなるか」「書き手の強みや人生経験をどう原稿に盛り込むか」を一緒に考えながらアドバイスすることが可能です。
こうやって対面・オンラインで1対1での添削を行っているからこそ、限られた試験時間内でベストの小論文を書くための力を習得することができるのです。
実際、うちの塾で学んだ方から「小論文が書けるようになりました!」「進学後も先生から教わった小論文のノウハウが役立っています!」と感想をいただくことが多くあります。
生成AI全盛の時代ではありますが、小論文指導はまだまだ人間の講師から学ぶべきことが多いと言えるのです。

小論文を書く力が役立つのは“試験対策”だけではない!
さらに、小論文を書く力は試験に受かるためだけに役立つのではありません。
小論文指導によって、自分の考えを整理する・自身の経験をことばで表現する・他者に伝わるように書く力をつけることは自分の思考を訓練することでもあります。
つまり、小論文の指導を通して得られるのは、合格という目先のゴールだけではなく、「自分自身の考えを自分の言葉で語れる力」でもあるのです。
この力は、大学院進学後も、自身のキャリアを形成する上でも、かならず役立つ場面が出てくるのです。
面接試験でも「人間によるサポート」が必要
小論文と同じように、面接試験の対策においても、「人間のサポート」が重要です。
ChatGPTは面接試験の模擬質問を出したり、答えの例を提示したりすることはできますが、「その人の話し方」「伝え方」「考え方の癖」など、回答全体を把握し、それに応じたアドバイスを行うことはまだ難しいのが現実です。
だからこそ、1対1大学院合格塾では面接練習の中で
- 声のトーン
- 話すスピード
- 内容の説得力
- 自己PRの内容
などを総合的に見ながらアドバイスを行っています。

「AI×人間」のハイブリッドが最適解
もちろん、私はChatGPTのようなAIツールの可能性を否定するつもりはありません。むしろ、今の時代、AIを使いこなすことこそが重要だと考えています。
私の塾でも、アイディア出しや構成の下書き、例文づくりにはChatGPTを積極的に活用しています。
それによって、受講生の思考の幅が広がり、効率的に準備を進めることができるようになっています。
ですが、それだけでは不十分です。
AIで出てきた文章を、
- 自分の言葉にする
- 自分の経験に引き寄せる
- 試験時間内でまとめあげる
という最終工程においては、やはり人間による丁寧なサポートが欠かせません。
「あなたらしい進路」を一緒に考える存在でありたい
大学院進学は、単なる学び直しではなく、「これからどう生きていくか」を真剣に考える転機でもあります。
だからこそ私は、ただ合格するための技術的なアドバイスだけでなく、
「あなたが一番輝ける進路とは何か?」
「これまでの経験を、どう未来につなげるか?」
といった視点を大切にしながら、面談や添削を行っています。

AIではなく“人間”である私だからこそできること。
それをこれからも磨き、あなたを支える存在であり続けたいと思っています。
一緒に大学院受験合格を目指していきましょう!
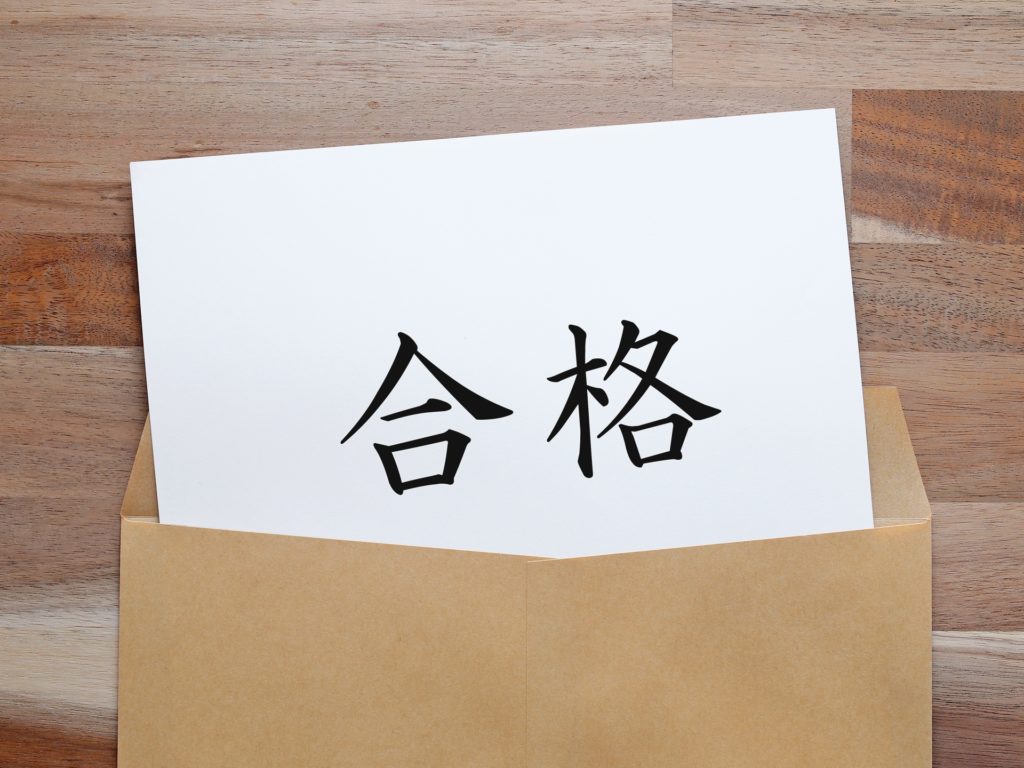
「大学院受験の対策方法をもっと詳しく知りたい…」
そういうあなたのために、
「本当に知りたかった!社会人が大学院進学をめざす際、知っておくべき25の原則」という小冊子を無料プレゼントしています!
こちらからメルマガをご登録いただけますともれなく無料でプレゼントが届きます。
データ入手後、メルマガを解除いただいても構いませんのでお気軽にお申し込みください。
なお、私ども1対1大学院合格塾は東京大学大学院・早稲田大学大学院・明治大学大学院・北海道大学大学院など有名大学院・難関大学院への合格実績を豊富に持っています。
体験授業を随時実施していますのでまずはお気軽にご相談ください。
(出願書類の書き方や面接対策のやり方のほか、どの大学院を選べばいいのかというご相談にも対応しています!)
お問い合わせはこちらからどうぞ!











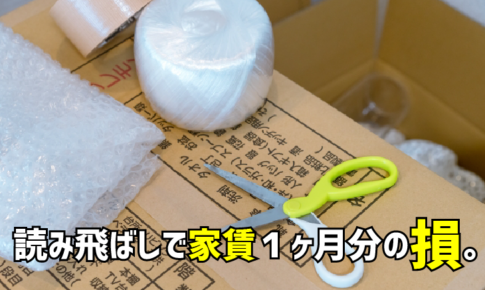




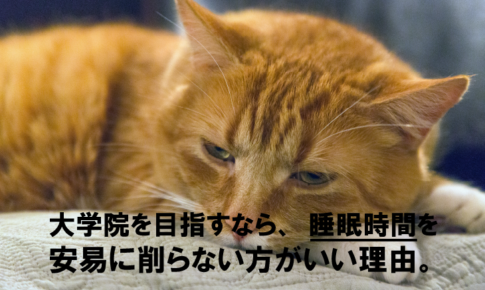
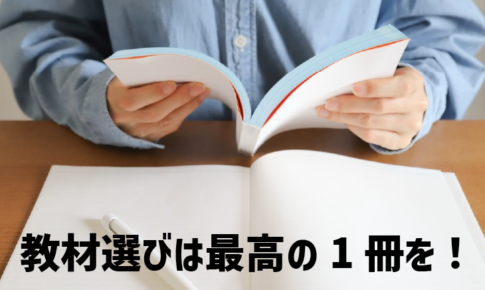






小論文対策にChatGPTなどの生成AIは役立ちますが、「書き手の魅力が伝わる文章」を作ったり、限られた時間内で書き切るためのノウハウを学んだりするのは生成AIではカバーできません。そのため大学院受験の小論文対策にはまだまだ人間の講師による1対1の指導が役立つのです。