「作文のコツ」も、お陰様で「60」まで来ました!
大変にありがとうございます!
まとめて読みたい方はこちらからどうぞ!
さて、曲がりなりにも「60」まで来れたのは
「作文」や「書くこと」を自分自身「好き」だからなのだと思います。
「好き」なことについて書くことはけっこう楽しいです。

私は小さいころ図鑑が好きでした。
工作の本も好きでした。
「いつか、こんな本を書きたい」と純粋に思っていました。
高校生・大学生のころはエッセイを書くのにハマりました。
「いつかエッセイ集を出したい」
「エッセイを連載したい」と思っていました。
これらの夢は「ブログ」の登場によって叶えられたわけです。
(科学技術に感謝!)
好きなことを人に話すのは意外に面倒です。
話を聞いてくれる人を見つけるのは大変です。
相手に興味が無いことを話すのは気が引けます。
あまりにもマニアックすぎると、誰もついてこれません。
そんなときは「好き」をとことんまで極めた文章を書きましょう。
ブログであれば「検索」で読み手が見つけ出してくれます(たぶん)。
Web賛美がまだまだ高い頃、私に影響を与えた本に齋藤孝・梅田望夫の『私塾のすすめ』があります。
本書には、(1)「好き」を極めることの大事さ、(2)ブログが「私塾」として機能するのではないか、という指摘があります。
梅田:僕が「好きなことを貫く」ということを、最近、確信犯的に言っている理由というのは、「好きなことを貫くと幸せになれる」というような牧歌的な話じゃなくて、そういう競争環境のなかで、自分の志向性というものに意識的にならないと、サバイバルできないのではないかという危機感があって、それを伝えたいと思うからです。(145)
齋藤:梅田さんの言われた「志向性の共同体」に、二十一世紀の希望を感じます。参加していることそれ自体が幸福感をもたらすもの。学ぶということには、そういう祝祭的幸福感があります。学んでいることそれ自体が幸福だと言い切れます。共に学ぶというのがさらに楽しい。できれば、先に行く先行者、師がいて。それが「私塾」の良さです。(195)
「好きなことを貫く」個人があつまると、
「こんなことをやってみたい!」という「志向性の共同体」が生まれます。
「好き」を極めたブログに読者が集まる様子が「志向性の共同体」の一つの現われです。
その部分を「私塾」とも言い換えているわけです。

(本書について、かつての私は書評ブログを書いています。こちらからどうぞ。
「好きじゃないと、もたない」時代の就労観)
ですが、「好き」を極めることはけっこう大変です。
「好きなものをとことんまでやってみたい!」
「これをやってみたい!」と思うのは簡単です。
やろうとすると「仕事だから・・・」「忙しいから・・・」「部活だから・・・」という
言い訳が始まります。
それでも、「好き」を極めていくことを梅田望夫や齋藤孝は「サバイバル」の方法として指摘します。
梅田:最近本当に感じるのは、情報の無限性の前に自分は立っているのだなということです。圧倒的な情報を前にしている。そうすると、情報の取捨選択をしないといけない、あるいは、自分の「時間の使い方」に対して自覚的でなければならない。流されたら、本当に何もできないというのが、恐怖感としてあります。何を遮断するかを決めていかないと、何も成し遂げられない。ネットの世界というのは、ますます能動性とか積極性とか選択性とか、そういうものを求められていくなと思う。無限と有限のマッピングみたいなことを本当に上手にやらない限り、一日がすぐに終わってしまう。(183)
齋藤:これからは、梅田さんのおっしゃるように、ここまで社会がスピードアップしてしまうと、「好きじゃないともたない」。「好き」が伴わないと仕事ができないというのは、ある意味で厳しくなってきたというか、がまんすればそれですむという感覚を超えてきたといえますね。そういう厳しい状況になってきたときに、僕は「心の自己浄化装置」が必要になってくると思います。「タフ」というと、最初から動じないという感じですが、タフであるかどうかというより、自分で処理するシステムをもっているかどうか、ということです。(中略)要するに、「なんとか職人」という感じの自己規定をしてみると、腹が決まるというか、逃げ出せなくなって、そうなると、細部に楽しみを見いだすことができるというメリットがあります。(150)
「好き」を極めるには、文を書くことが大切です。
自分はどこまでその対象を知っているのか。
どこまで興味があるのか。
書いて整理してみることではじめて見えてくるからです。
そしてその「好き」を極めている文章、ぜひブログなり本なりにまとめて欲しいと思います。
「好き」を極めたあなたでないと、届かない言葉があります。
「好き」を極めたあなたでないと、届けられない人がいます。
どうぞその人のために、書いてみてください。

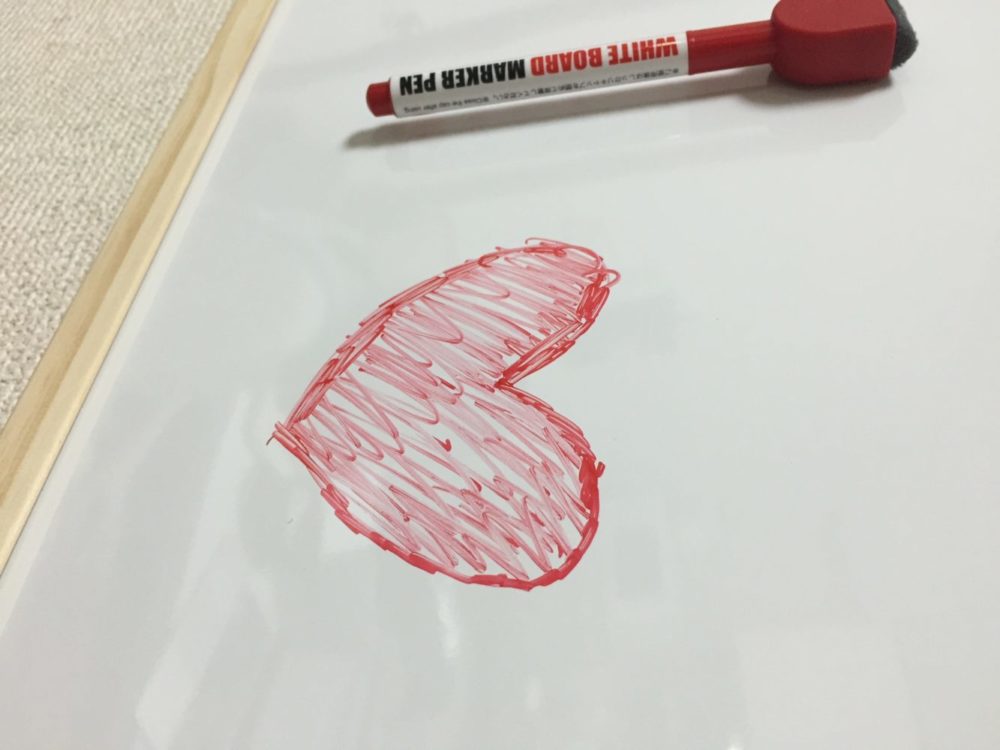







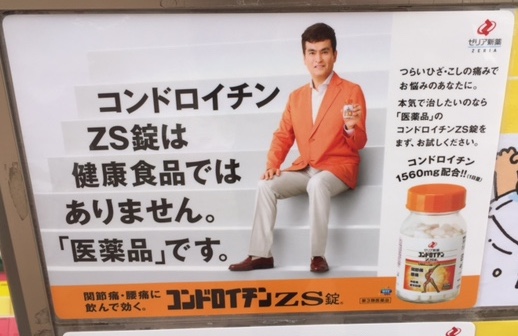
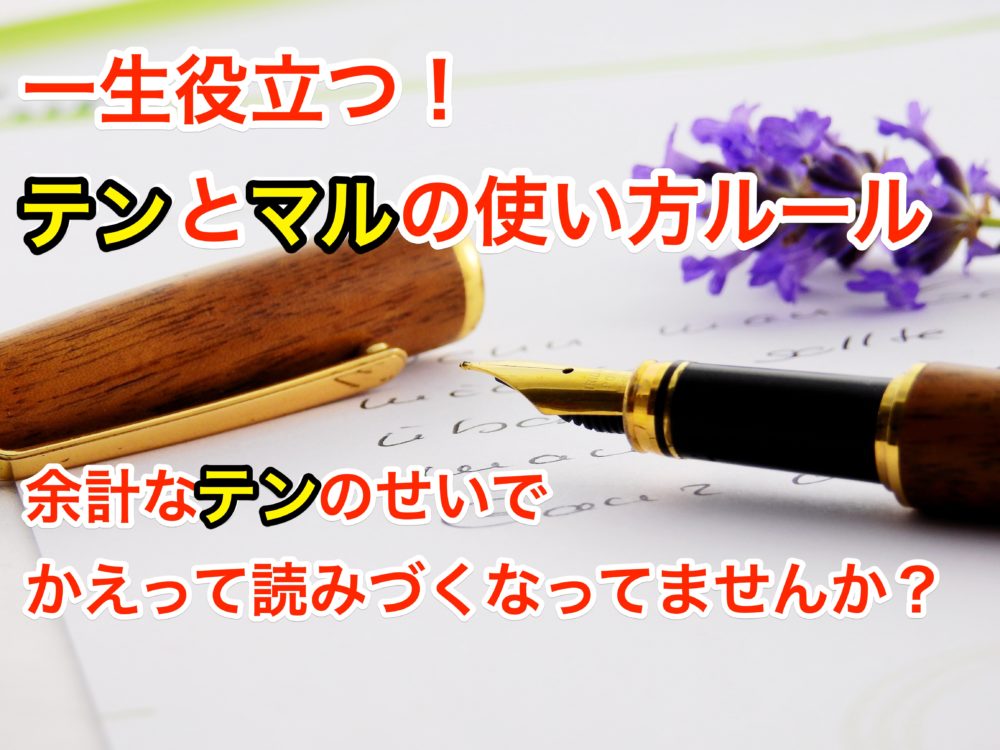
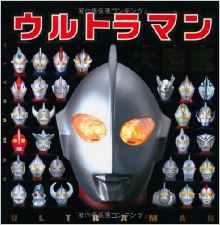
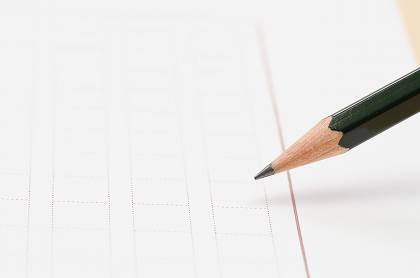
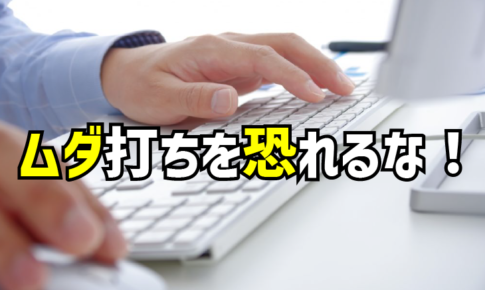
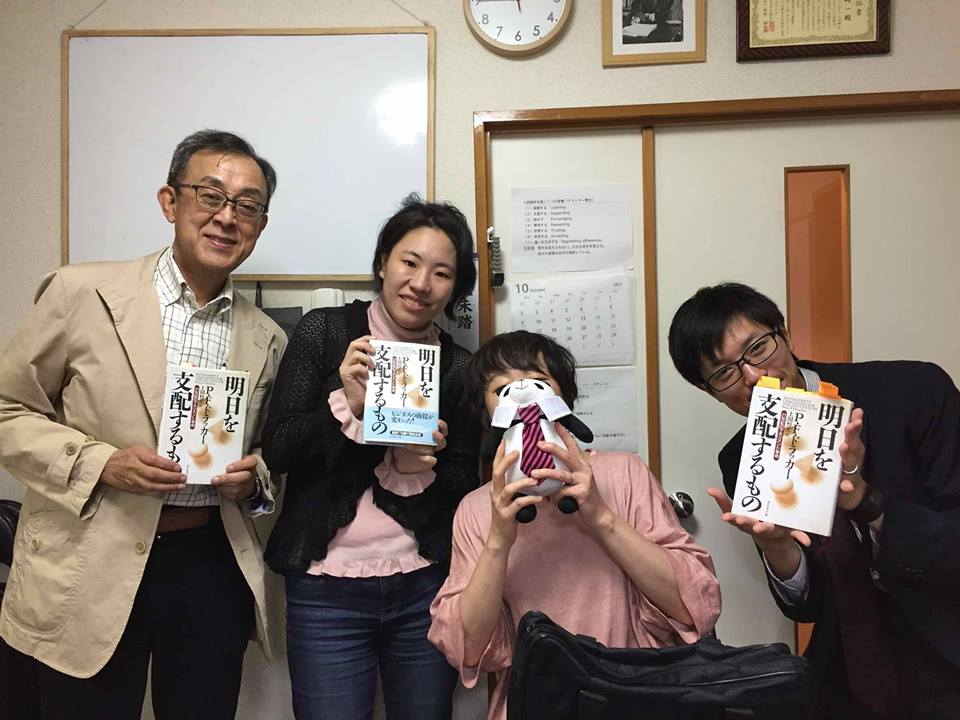
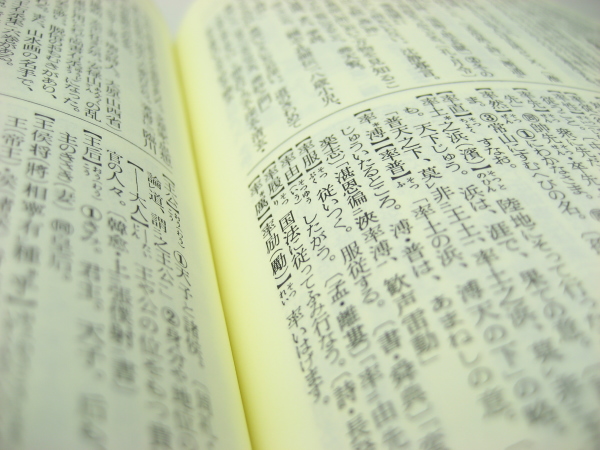
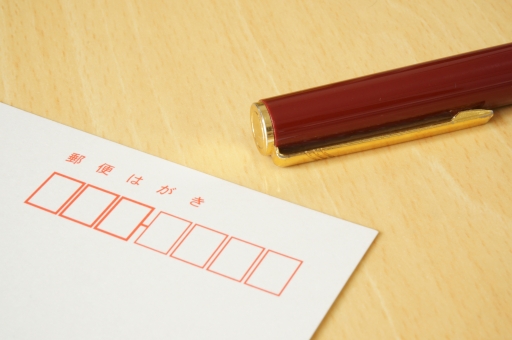






コメントを残す